業務委託の勤怠管理はどこまでOK? 違法リスクを回避するポイントと注意点
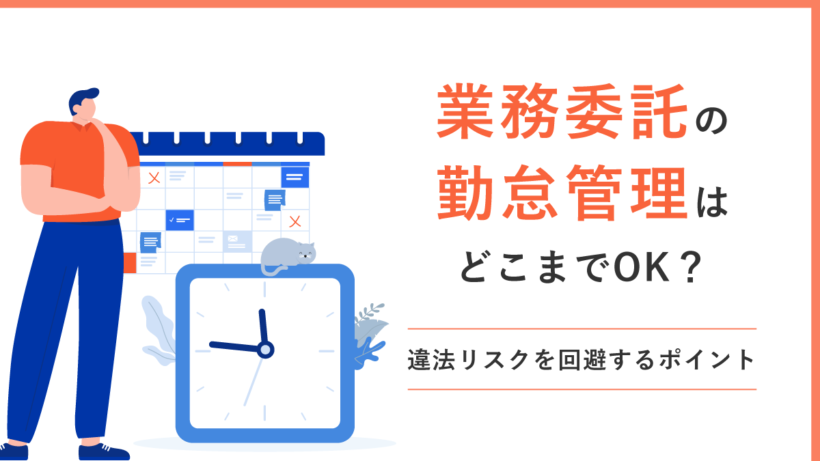
業務委託のフリーランスに「勤怠報告を求めたら違法になる?」業務委託を活用する企業が増えるなかで、不安を感じる担当者もいるのではないでしょうか。
業務委託における勤怠管理は、原則として違法になる可能性が高いです。偽装請負と判断されるリスクがあります。
本記事では、業務委託の勤怠管理の問題点と、違法リスクを回避するポイントを解説します。労務トラブルを防ぐためにお役立てください。

 目次[表示]
目次[表示]
業務委託契約の基本をおさらい
業務委託契約とは、企業が特定の業務を外部の企業や個人に委託する際に結ぶ契約です。
委託者と受託者は対等な立場で業務を進め、受託者は委託者の指揮命令を受けずに自身の裁量で業務を遂行します。
業務委託契約の種類
業務委託契約は民法上の「請負」「委任」「準委任」の契約を総称したものであり、法律で明確に定義された契約形態ではありません。契約形態には以下のような特徴があります。
| 種類 | 特徴 | 例 |
|---|---|---|
| 請負契約 | 受託者が特定の仕事の完成を約束し、委託者がその結果に対して報酬を支払う契約 | ・特定の設計書通りにプログラム開発をする業務 ・特定期限までに荷物を届ける業務 |
| 委任契約 | 委託者が受託者に対し、法律行為を委託する契約 | 弁護士への訴訟代理依頼 |
| 準委任契約 | 法律行為ではない事務処理を委託する契約 | ・コンサルタントの業務分析 ・医師の診察 |
雇用契約との違い
業務委託契約と雇用契約の違いは「労働法による保護」と「指揮命令関係」の有無です。
雇用契約では、労働者は企業の指示のもと、労働法によって守られながら働きます。企業の指揮命令下で労働力を提供し、対価として企業は賃金を支払わなければなりません。勤務時間や勤務場所も企業によって管理されます。
一方で業務委託契約では、労働法による保護はなく、委託者と受託者は対等な関係にあります。委託者は受託者に対して、業務のやり方や作業場所・作業時間に関する指示ができません。受託者は自分の裁量で仕事を進め、成果物や業務遂行の内容に応じて報酬が支払われます。
▼業務委託と雇用契約の違いを詳しく知るには、以下の記事もご確認ください。

業務委託契約における受託者の勤怠管理は違法
業務委託契約では、委託者と受託者は対等な立場にあり、雇用契約のような指揮命令関係は存在しません。委託者が受託者に対して勤怠管理を行うことは、指揮命令権の行使による偽装請負とみなされ違法になる可能性が高いです。
業務委託契約において勤怠管理が違法とされる理由は明確です。委託者には受託者の働き方について口出しする「指揮命令権」がないため、出退勤の時間管理や勤怠報告を求めることは契約の本質に反します。
タイムカードやICカードによる出退勤管理、勤怠管理システムへの登録なども、委託者が受託者の労働時間を管理する行為にあたるため避けましょう。
「偽装請負」とみなされるリスクがある
業務委託で勤怠管理をすると、偽装請負と判断されるリスクがあります。
偽装請負とは、本来は雇用関係にある労働者を「業務委託先」と見せかける違法な契約形態のことです。社会保険料の回避や、労働法規の適用逃れが問題視されています。
偽装請負は労働者派遣法、職業安定法、労働基準法違反となる可能性があり、発覚すれば、委託元・受託先の双方に罰金や懲役刑が科されるおそれがあるため注意しましょう。
- 職業安定法違反:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 労働者派遣法違反:1年以下の懲役または100万円以下の罰金、または6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
- 労働基準法違反:1年以下の懲役または50万円以下の罰金
直接かかわった人だけでなく、組織の代表者や管理職も処罰の対象です。厚生労働大臣からの改善措置命令が出されたり、社名が公表されたりと、社会的な信用も大きく損なわれるため、リスク管理の点から避けなければなりません。

業務委託の勤怠管理は「指揮命令」にあたるおそれ
業務委託との付き合い方において、とくに注意したいのは、指揮命令の有無です。勤怠管理は労働時間を把握し、働き方を管理することであり、労働者の雇用契約における指揮命令権の行使にあたります。
勤怠管理を通じて、受託者である業務委託の労働時間を把握し、報酬を支払うと、実質的に「時間給」による報酬支払いとなり、雇用契約の特徴を持つことになります。
自社に常駐させる場合の勤怠管理も違法
IT業界などでは、業務委託の人材が委託先企業に常駐して働く「客先常駐」の形態がよく見られます。客先常駐でも、委託者が業務委託である受託者の勤怠管理をすることは原則として違法です。
たとえば、発注者の都合で「月曜〜水曜の10時〜17時は出社」「休日出勤してほしい」といった時間や勤務場所の指示は出せません。
勤怠管理は、受託者の雇用主(受託企業や本人)が行うものです。フリーランスでも、他社に雇用されている人材でも、委託先が直接管理することはできません。
ただし、業務の性質上どうしても特定の時間や場所を指定する場合は、業務委託契約書に理由と条件を明記し、双方の合意が取れていれば、基本的に問題ないと考えられます。常駐のエンジニアも含めて、飲食店や運送会社などで発生するケースです。それでも勤怠管理そのものは認められません。

業務委託の勤怠管理が必要な場合の対処法
業務委託契約では勤怠管理が違法となるリスクがありますが、業務の円滑な進行のためには何らかの進捗管理が必要です。ここでは、法律に抵触せず適切に業務を管理する方法を紹介します。
成果物の進捗を管理する
業務委託では、勤怠管理の代わりに成果物の進捗で管理しましょう。労働時間を把握しようとすると指揮命令とみなされ、偽装請負に該当するおそれがあります。
たとえばWebサイト制作なら、「サイトマップの提出」「デザイン案の確認」など、段階的に成果物を確認することで、業務の進み具合を把握できます。
労働時間ではなく成果物を基準にするため、偽装請負のリスクを回避できます。ガントチャートなどのプロジェクト管理ツールを活用すると、進捗の可視化に効果的です。
受託者に進捗報告を求める
進捗報告の頻度や方法は、あらかじめ契約書で明確に決めておくことが重要です。そもそも業務委託者の勤怠管理をしたいと考えるのは、仕事ぶりが見えづらく、不安を感じているからではないでしょうか。
たとえば「毎週金曜にメール進捗報告」「月末に月次報告書を提出」など、具体的な方法を明文化しておくと、やり取りがスムーズになります。
報告内容もポイントです。進捗だけでなく、発生した課題と対策や今後の対応予定を含めると、進捗の中身がわかり安心でしょう。
業務委託契約書には、例として以下のような条項を入れておくと、法的な根拠になります。
| 委託者は、受託者に対し、委託者が必要と認めるときは、本件業務に関し報告及び資料の提出を求めることができる |
コミュニケーションを密にとる
業務委託契約では、受託者との円滑なコミュニケーションも欠かせません。進捗の把握や課題の共有が遅れると、後工程に大きな影響が出るためです。
週次・月次のミーティングを設けたり、チャットでこまめにやり取りしたりすることで、小さな課題にも早期に気づけます。
ただし、指揮命令と取られるような一方的な指示は避け、あくまでも「依頼」「相談」「共有」の姿勢を心がけましょう。対等な関係を意識し、信頼関係を築きながら、連携することで業務の質と効率を高められます。

業務委託の勤怠管理に関する注意点
業務委託契約では委託者と受託者は対等な立場であり、委託者には指揮命令権がありません。
業務委託契約において勤怠管理は指揮命令権の行使による偽装請負とみなされ違法になる可能性が高いですが、業務の性質によっては一定の管理が必要なケースもあります。
そのような場面でも法的リスクを避けながら業務を進めるには、どのように対応すべきか、4つの注意点を見ていきましょう。
- 作業時間の指定が必要な場合は契約書に明記する
- 報酬計算方法の違いに注意する
- 自社への専属性が高くならないよう気をつける
- タイムカードは使用しない
作業時間の指定が必要な場合は契約書に明記する
業務委託契約では、基本的に受託者の作業時間を指定することはできません。ただし、業務の性質上、時間帯の指定であれば、契約書で明示したうえで、双方の合意を得る必要があります。
たとえば、「飲食店の営業時間内」や「クライアントとの打ち合わせ対応時間」などの指定が可能です。
| 業務委託契約書の記載例 |
|---|
| 業務の性質上、〇〇の理由により△△時〜□□時の作業が必要 |
なお、指定時間は、業務の遂行に必要な最小限の範囲にとどめましょう。委託者の都合で、一方的に時間を指定したり、変更したりすることは避けなければなりません。受託者の裁量を尊重する姿勢が大切です。

報酬計算方法の違いに注意する
業務委託の報酬は労働時間ではなく、成果物や業務遂行に対して支払うものです。報酬体系が雇用契約と似ていると、偽装請負と判断されるリスクが高まるため注意が必要です。
請負契約では、成果物の完成に対して報酬が支払われます。たとえば、「Webサイト1ページの制作につき〇万円」「記事1本の執筆につき〇円」といった契約です。作業時間は報酬に直接関係しません。
準委任契約は、業務の遂行自体に対して報酬が支払われます。時間給ではなく「月額固定報酬」や「業務ごとの固定報酬」といったルールが一般的です。時給で設定したい場合も、労働時間の対価ではなく、専門性や難易度に基づいて、かかった工数に対する報酬であると明確にしなければなりません。
時給という契約がすぐに偽装請負と判断されることはありませんが、実態が労働時間に対して賃金を支払う性質を持つ場合は問題となる可能性があります。
業務委託の報酬は、雇用契約における「労働時間に対する賃金」とは異なります。
自社への専属性が高くならないよう気をつける
業務委託契約において、受託者が実質的に自社の仕事だけに従事していると、偽装請負と判断されるおそれがあります。他社との契約を妨げないことが、業務委託契約の原則です。
たとえば、拘束時間が長くほかの業務を受けにくい状態や、固定給のような報酬であると、自社への専属性が高いとみなされます。契約書に他者との取引を制限する条項は設けられません。
専属性を避けるために、業務量や納期を調整し、他社業務と並行できるように配慮しましょう。成果物や報酬の内容を明確にし、受託者の独立性を尊重することが大切です。
タイムカードは使用しない
業務委託契約でのタイムカードを使用した勤怠管理は、雇用関係と誤認される一因となります。タイムカードは労働時間の管理を目的としたツールです。雇用契約における指揮命令権の行使を象徴しているといえるでしょう。
タイムカードでの勤怠管理は、自由な業務遂行を制約してしまうため、委託者と受託者の対等な関係に反します。
業務委託の進捗を確認したい場合は、プロジェクト管理ツールや定期報告など、成果物を基準とした方法をとる必要があります。
タイムカードに限らず、ICカードによる入退室管理や勤怠管理システムへの登録も避けなければなりません。業務委託契約の本質を理解し、本人の裁量と独立性を尊重した進捗管理を心がけましょう。
偽装請負を回避するためのポイント
業務委託契約では、勤怠管理以外にも実態として注意したいポイントが3つあります。
- 指揮命令関係がないことを明らかにする
- 業務実態を把握する
- 関係者に周知する
もし偽装請負と判断された場合、委託元が受託先の従業員に対して労働契約を申し込み、直接雇用になったとみなされます。
社会保険料の負担・残業代の支払い・有給休暇の付与といった労働基準法上の義務が発生するため、適切に運用していきましょう。

指揮命令関係がないことを明らかにする
業務委託契約書には、指揮命令関係がないことを明示したうえで、受託者の裁量を具体的に保障する条項を盛り込みましょう。例として以下のような項目が挙げられます。
- 作業時間・方法・場所について、受託者側の裁量に委ねること
- 就業規則や服務規律を適用しないこと
- 成果物・納期・報酬に関する条件
- 仕様書(依頼書)を添付するが、詳細な指示命令にならないように注意すること
- 報酬は時間給ではなく、成果物または業務量に応じた支払方法とすること
- 発注者と受託者に管理責任者を設けること(直接指示しない)
以上のような契約内容を設定することで、雇用契約との違いを明確にし、将来の労務トラブル防止につながります。
業務実態を把握する
業務委託契約書に指揮命令関係がないと明記されていても、実態として発注者が受託者を労働者のように扱っていれば、偽装請負と判断されるリスクがあります。とくに以下のような行為がないか、現場で定期的に確認することが重要です。
- 発注者が受託者の従業員に直接指示を出していないか
- タイムカードなどで勤怠管理をしていないか
- 受託者の従業員が発注者の社内ルールや就業規則にしたがわされていないか
また、次のような典型的な偽装請負のパターンに該当していないかもチェックしましょう。
- 代表型:受託者が形式的に代表を置いているが、実態は個人契約に近い
- 形式だけ責任者型:責任者が存在するが、実際には委託元が個々に指示をしている
- 使用者不明型:指揮命令の所在があいまい
- 一人請負型:実態が個人への直接指示に近い状態
なかでも「形式だけ責任者型」はトラブルが多く、責任者を通していても実質的に個別指示をしている場合は、偽装請負とみなされるため、とくに注意が必要です。
関係者に周知する
偽装請負のリスクを組織として回避するには、契約担当者や現場責任者だけでなく、実際に受託者とかかわる従業員全員に、リスクと対応を周知することが不可欠です。具体的には以下のような内容を浸透させる必要があります。
- 偽装請負の定義・リスク・違法事例を共有する
- 適法な委託契約の運用方法を教育する
- 「直接指示はNG」「勤怠管理はしない」などの基本原則を明確にする
- 指示を出せる範囲(納期や成果物による依頼にとどめる)を確認する
研修・マニュアル配布・チェックリストの活用を通じて、組織全体での理解を促進しましょう。
まとめ
業務委託契約における勤怠管理は原則として違法であり、偽装請負と判断されるリスクにつながります。
業務委託契約では、委託者と受託者は対等な立場にあり、委託者には指揮命令権がありません。タイムカードなどによる勤怠管理や作業時間の指定は、契約の本質に反する行為です。
万が一、実態が雇用契約と判断されると、違法とみなされ、直接雇用が成立するおそれや罰則を受ける可能性もあります。
自社の契約と運用に問題がないかを見直し、関係者への教育や運用ルールの徹底を通じて、法的リスクを回避し、適正に業務委託との関係を維持していきましょう。
