労働基準法とは【内容を簡単に】実務に影響する要点をわかりやすく解説
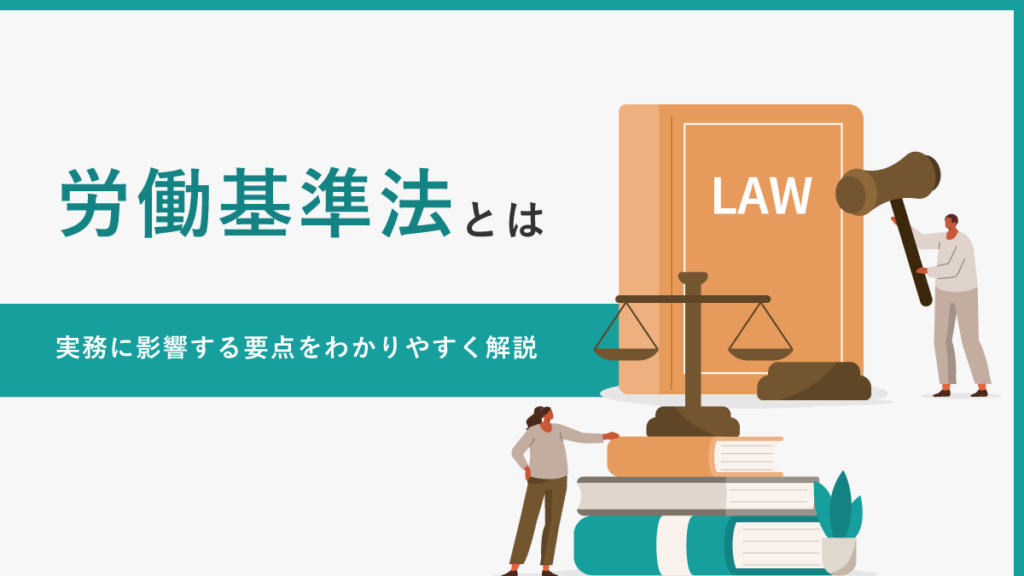
「労働基準法の条文を読んでもよくわからない」「労働基準法に沿った管理ができている自信がない」と感じたことはありませんか。労働基準法は労働時間・賃金・休暇などの最低ラインを定めた、労務管理において避けては通れない法律です。適切な労務管理を行い、従業員の権利を守ることは、結果として安定した経営につながります。
本記事では、労働基準法の基本原則から実務に直結するポイントまで、経営者や人事担当者にもわかりやすく解説します。

 目次[表示]
目次[表示]
労働基準法とはどんな法律? わかりやすく解説
労働基準法は、企業が労働者を雇用する際に最低限守らなければならない労働条件を定めた法律です。
以下のような領域において働くうえでの基本ルールが規定されています。
- 労働時間
- 休憩
- 休日
- 休暇
- 時間外労働
- 有給休暇
制定は1947年と古く、時代に合わせて同法を補完する政令や規則が整備されてきました。
たとえ事業主と労働者が合意しても、強行法規の労働基準法基準を下回る契約は無効です。
違反すると、企業には罰則が科されるほか、企業名が公表されるおそれもあるため、実務に影響する要点は最低限理解しておかなければなりません。
まずは労働基準法について、適用範囲や役割、基本の7原則を紹介します。
適用範囲・対象者
労働基準法は原則として、日本で働いている「労働者」すべてに適用されます。
企業の種類や雇用形態、国籍は問われません。正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイト、契約社員なども対象です。日本の事業場で働く外国人も、労働者であれば含まれます。
ただし例外もあり、以下にあてはまる人は適用除外となります。
- 一部の船員
- 家族経営(同居する親族のみで経営している企業に勤める人)
- 家事使用人
- 一般職または特別職の国家公務員
- 一般職の地方公務員
一部の船員は船員法により保護されています。家事サービス代行会社で働く人は家事使用人とは呼ばれないので注意しましょう。国家公務員の特別職とは、裁判所職員・国会議員・防衛省の職員などです。
まれに誤解されるのが、労働者とは企業に雇用される人を指すので、個人事業主や役員、フリーランス(請負契約・委任契約)で働く人は労働基準法の適用範囲に含まれません。
目的や役割
労働基準法の主な目的は「労働者の保護」と「労働条件の向上」です。
同法が制定された1947年当時、戦後復興期において、長時間労働や低賃金といった労働環境が社会問題となっていたことを背景に、労働者を守るための最低基準が明文化されました。
そもそも使用者(企業)と労働者の間には立場上、交渉力に大きな差があります。
労働基準法は労働者の立場を守り、適切な労働環境を確保するための「盾」としての役割を果たしているのです。
企業が不当な労働条件を課さないように最低限のルールを定め、違反した場合には罰則を科すことで、労働者を守っています。
具体的には以下のような役割があります。
- 労働条件の最低基準を定める
- 労使間の公平な関係を築く
- 労働者の健康と安全を守る
- 人間らしい生活を保障する
- 社会全体の労働環境を整える

労働基準法の基本7原則
労働基準法には7つの重要な基本原則があります。実務にかかわる要点をおさえるために、まずは以下の原則の内容を、大まかに確認しておきましょう。
| 条文 | 原則名 | 禁止事項・ルールの要点 |
|---|---|---|
| 第1条 | 労働条件の原則 | 人間の尊厳を守り、生活水準の向上を目指すものでなければなりません。 |
| 第2条 | 労働条件の決定 | 労使が対等な立場で決定する必要があります。 |
| 第3条 | 均等待遇 | 国籍、信条、社会的身分による差別的取扱いを禁止しています。 |
| 第4条 | 男女同一賃金の原則 | 性別を理由とした賃金差別を禁止しています。 |
| 第5条 | 強制労働の禁止 | 暴行や脅迫による労働強制を禁止しています。 |
| 第6条 | 中間搾取の排除 | 他人の就職に介入して利益を得ることを禁止しています。 |
| 第7条 | 公民権行使の保障 | 労働者の市民としての権利行使を保障しています。 |
基本の7原則は、現代の労働環境における基本的人権の尊重と公平性を確保するための重要な指針となっています。
次からは労働基準法の要点を、人事労務担当者が知っておきたい部分だけ抜粋して簡単に紹介していきます。勤怠管理、給与計算、雇用・労務管理と分野ごとに分けているので、気になる業務範囲だけでもぜひお読みください。
労働基準法の内容:勤怠管理に関連する要点
勤怠管理は企業の労務管理の基本です。労働基準法では、労働時間や休憩、休日について詳細な規定を設けています。
1.労働時間(第32条)
労働基準法では、1日8時間、1週40時間を法定労働時間として定めています。法定労働時間を超えて労働させる場合は、労使協定(36協定)を締結し、届け出が必要です。
変形労働時間制やフレックスタイム制を導入する場合は、就業規則で明確にルールを記載しなければなりません。
いずれも制度の対象となる基礎期間を規定する必要があります(変形労働時間制は1か月単位や1年単位、フレックスタイム制は3か月以内の清算期間)。
特例として、小規模事業場(10人未満の特例事業)は、週44時間まで法定労働時間が認められています。
フレックスタイム制や変形労働時間制についての詳しいルールは、以下の記事よりご確認ください。
▼労働時間の管理方法に不安がある方は以下の資料もぜひご活用ください。

2.休憩時間(第34条)
労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与える決まりです。
休憩時間は「労働時間の途中で付与すること」「一斉に付与すること(例外あり)」「自由に利用できること(例外あり)」が原則です。
電話番をお願いしたり、業務指示をしたり、行動を制限してしまうと休憩とはならないので、完全に業務から離れて休息をとれる時間を設けなければなりません。
労働基準法で定める休憩時間について、例外事項も含め、さらに深く知るには以下の記事もご確認ください。
3.休日(第35条)
労働基準法によると、企業は毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません(=法定休日)。
休日は原則として暦日(0時から24時まで)単位で与えなければならないので、日勤・夜勤交替制ではシフト管理に配慮しましょう。
法定休日にあてはまらない、企業が独自に定める休日は法定外休日であり、扱いが異なります。
職場の事情でやむを得ず、法定休日に労働を命じると休日労働となり、特別な配慮が必要です。
4.時間外労働、休日労働(第36条)
労働基準法に定める、法定労働時間を超えて労働させる場合や、法定休日に労働させる場合は、労使協定(36協定)の締結と労働基準監督署長への届け出が必要です。
時間外労働の上限は原則として月45時間、年360時間です。特別な事情がある場合でも、年720時間を超えることはできません。
時間外労働・休日労働について詳しく知るには以下の記事もご確認ください。
5.年次有給休暇(第39条)
労働基準法では、6か月以上継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、最低10日の有給休暇を付与する決まりです。
勤続年数に応じて付与日数は増加し、最大20日まで付与されます。条件を満たせばパート・アルバイトも対象です。
基本的に労働者は自由に有給休暇の取得時季を決められますが、企業側が時季変更権を行使できる場合もあります。
労働基準法の改正によって2019年4月から、年10日以上の有休が付与される労働者に対して、企業は最低5日を取得させることが義務付けられました。
未消化分は翌年に繰り越せるものの、取得状況の管理が重要となります。
有給休暇について詳しく知るには以下の記事もご確認ください。
労働基準法の内容:給与計算に関連する要点
給与に関する規定は、労働者の生活保障においてとくに重要です。適切な賃金支払いは使用者の基本的な義務となっています。
6.賃金(第24条)
賃金は「通貨」で労働者に「直接」、「全額」を「毎月」1回以上、「一定の期日」を定めて支払わなければなりません。
この賃金支払い5原則は、労働基準法で定められ、労働者の生活の安定を守る重要な規定です。
- 通貨払い(原則現金。労働者の同意があれば銀行振込可※デジタル払いは労使協定の締結が必要)
- 直接支払い(仲介者を介して労働者本人に支払う)
- 全額払い(法律の定め又は労使協定を締結した場合以外の天引き不可)
- 毎月払い(月に最低1回以上の支払いが必要)
- 一定期日払い(支払い日を明確に定める)
給与の控除は、税金や社会保険料など法令で定められたものを除き、労使協定を締結しない限り認められません。
2023年4月より賃金のデジタル払いが解禁されました。デジタル給与払いについて知るには以下の記事もご確認ください。
7.休業手当(第26条)
労働基準法に基づき、会社の都合で労働者を休業させる場合、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要があります。
経営不振・業績悪化などの理由が該当します。
ただし、以下のような不可抗力による休業は対象外です。
- 自然災害(地震・台風)
- 政府命令による休業(感染症のまん延防止措置)
休業手当の支払いについて詳しく知るには以下の記事をご確認ください。
8.割増賃金(第37条)
労働基準法では、法定労働時間を超える時間外労働や休日労働、深夜労働(22時から翌5時)に対して、通常の賃金に上乗せして割増賃金の支払いが必要です。
- 時間外労働:25%以上
- 休日労働:35%以上
- 深夜労働:25%以上
- 時間外労働+深夜労働:50%以上
- 休日労働+深夜労働:60%以上
- 月60時間超の時間外労働:50%以上
中小企業の人事労務担当者は、2023年4月から、中小企業でも月60時間を超える時間外労働に50%の割増賃金が適用されていることを覚えておきましょう。
割増賃金の計算について詳しく知るには以下の記事をご確認ください。
9.減給(第91条)
労働基準法では、懲戒処分としての減給を行う上限を定め、過度な減給を禁止しています。
1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはいけません。さらに複数回の減給の合計額は、一賃金支払い期における賃金総額の10分の1を超えることはできません。
10.賃金台帳(第107条)
企業は労働者ごとに「賃金台帳」を作成し、賃金の支払い状況を詳細に記録する必要があります。
労働基準法で定める記載項目は、労働者の氏名や労働日数、労働時間、賃金額などです。
賃金台帳は「賃金を支払うたびに作成・記録」し、「5年間(当面3年)の保存義務」があります。
記載内容に不備があると、労働基準監督署の指導や罰則の対象となるため、慎重に対応しましょう。
賃金台帳の作成について詳しく知るには以下の記事をご確認ください。
労働基準法の内容:雇用・労務管理に関連する要点
雇用・労務管理に関する規定は、労働者の生活保障においてとくに重要です。
11.労働条件の明示(第15条)
労働契約を結ぶ際、労働基準法により、使用者は労働者に対して以下の条件を明示しなければなりません。書面(電子交付可)で通知する義務があります。
- 労働契約期間
- 仕事の場所と内容
- 始業・終業時刻
- 所定労働時間を超える労働の有無
- 休憩時間・休日・休暇
- 就業時転換に関する事項
- 賃金に関する事項
- 退職に関する事項
2024年4月1日からは必須事項が追加されています。新たに追加された内容を詳しく知るには、以下の記事をご確認ください。
12.解雇(第20条)
企業が労働者を解雇する場合、労働基準法に定める最低30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う義務があります。
ただし、以下の場合は解雇が制限されます。
- 業務上の傷病による休業期間とその後30日間
- 産前産後の休業期間とその後30日間
「解雇権濫用の法理」(労働契約法第16条)に基づき、合理的な理由がない場合は無効となる可能性があるため、慎重な判断が求められます。
正当な解雇理由について知るには以下の記事をご確認ください。
13.就業規則の作成(第89条)
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則の作成と労働基準監督署長への届出が義務づけられています。
就業規則には以下の事項を必ず記載しなければなりません(絶対的必要記載事項)。
- 始業・終業時刻
- 休憩時間・休日・休暇
- 就業時転換に関する事項
- 賃金に関する事項
- 退職に関する事項
会社で規定がある場合に記載すべき相対的必要記載事項として、退職手当や休職に関する事項などがあります。
就業規則は、企業と労働者の双方が遵守すべき労働契約の一部となるため、実態に即した内容にすることが重要です。変更するには労働者代表の意見を聴取しなければなりません(第90条)。
就業規則の作成について詳しく知るには以下の記事をご確認ください。
14.ルールの周知(第106条)
労働基準法や就業規則、労使協定の内容は、職場ないの見やすい場所に掲示するなどして、周知する必要があります。
方法は、見やすい場所への掲示または書面配布、電子媒体のいずれかです。
周知を行うことで、労働者が自身の権利や義務を理解し、職場でのトラブル防止につながります。
周知義務を怠ると、労働基準監督署の指導を受けたり、罰則を科されたりする可能性があるため、単に作成するだけでなく、内容を把握できるように環境を整えましょう。
15.書類の保存(第109条)
労働者名簿や賃金台帳などの法定帳簿は、労働基準法で定められた一定期間、保存する義務があります。
- 賃金台帳:5年間(当面の間3年間)
- 労働者名簿:退職後5年間(当面の間3年間)
- 出勤簿:5年間(当面の間3年間)
- 雇用契約書(労働条件通知書):退職後5年間(当面の間3年間)
近年は、クラウド型の勤怠管理システムや電子書類による保存が普及しており、法律に沿った管理方法であれば、電子データでの保存も認められています。
勤怠管理システムの機能や費用は以下でご確認ください。
労働基準法の違反例と罰則
労働基準法では、労働者の権利を守るためにさまざまな規定が定められており、違反には厳しい罰則が設けられています。
違反の程度によっては、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金だけでなく、最大で10年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されるケースもあります。
以下では、労働基準法に違反する具体的な例と、それぞれの罰則について解説します。
男女など身分で差別する(労働基準法第3条・第4条違反)
労働基準法では、性別や国籍による賃金差別、募集・採用における差別的取り扱いを禁止しています。
同一労働同一賃金の原則に反するような不合理な格差を設けることも違法です。
| 例 |
|---|
| ・同じ業務をしているにもかかわらず、女性の給与を男性より低く設定する ・外国人労働者という理由で、昇進や昇給の機会を与えない ・採用時に「女性は応募不可」「外国籍の方はお断り」という条件を設ける |
差別を行った場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科される可能性があります(労働基準法第119条)。
違約金や賠償予定額を定める(労働基準法第16条違反)
労働契約の不履行に対して、あらかじめ損害賠償額を予定する契約をしてはなりません。また、あらかじめ契約で違約金を定めることも認められません。労働者の自由な意思決定を妨げる行為だからです。
| 例 |
|---|
| ・「一定期間内に退職した場合は、研修費用を全額返還する」という契約 ・「辞めるなら損害賠償を請求する」と圧力をかける ・労働組合に加入した従業員に対し、「組合活動によって会社に損害を与えた」として賠償請求をする |
違反行為を行った場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科される可能性があります(労働基準法第119条)。
突然解雇する(労働基準法第20条違反)
30日前の予告なく突然解雇することは労働基準法違反です。正当な理由なく解雇を行うことも、解雇権の濫用として無効となります。
| 例 |
|---|
| ・「明日から来なくていい」と一方的に解雇を通告する ・「業績が悪いから」と説明するだけで、解雇の具体的で正当な理由を示さない ・病気療養中の労働者を回復の見込みがあるにもかかわらず解雇する |
不当解雇を行った場合、企業には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科される可能性があります(労働基準法第119条)。
労働条件を明示しない(労働基準法第15条)
労働契約の締結に際して、労働条件を明示しない場合、労働基準法第15条に違反することになります。また、労働条件の絶対的明示事項のうち、昇給を除く事項を書面等で明示しない場合も違反です。
| 例 |
|---|
| ・労働契約締結に際して、賃金や労働時間などの労働条件を明示しない ・労働条件の明示を口頭で行い、書面を交付しなかった |
労働条件を適切に明示しなかった場合、企業には30万円以下の罰金を科される可能性があります(労働基準法第120条)。
以下の記事ではほかにも、さまざまな事例を紹介しています。
近年実施された労働基準法の改正要点
労働基準法は、労働環境の変化や社会のニーズに対応するため、継続的に見直しされています。とくに近年は、働き方の多様化や長時間労働の是正を目的とした改正が進められ、2024年4月には複数のルールが変更されました。
【近年の主な改正】
- 時間外労働の上限規制猶予期間の終了
- 労働条件の明示ルールの強化
- 裁量労働制の運用改善
以上の3つのポイントに焦点をあてて解説します。
人事労務にかかわる法律は労働基準法だけではありません。2025年も重要な法律の改正が控えています。法改正の要点と、人事労務に影響する実務対応は以下の資料でご確認ください。

時間外労働の上限規制猶予期間の終了
2024年4月より、猶予されていた業種に対して時間外労働の上限規制が適用されました。業務の特性を踏まえた一部例外はあるものの、基本的にはほかの一般業種と同様の規制となっています。
| 建設業 |
|---|
| ・原則として時間外労働は月45時間・年360時間が上限 ・特別条項付き36協定を締結した場合でも、年間720時間を超えられない ・時間外労働と休日労働の合計時間は、月100時間未満、2~6か月平均で80時間以内 ・月45時間を超える時間外労働は年6回まで ※災害復旧・復興事業を除いて一般業種と同様の上限規制が適用 |
| 自動車運転業務 |
|---|
| ・特別条項付き36協定を締結した場合、年間960時間が上限 ・時間外労働と休日労働の合計時間は、月100時間未満、2~6か月平均で80時間以内 ・月45時間を超える時間外労働は年6回まで |
| 医師 |
|---|
| ・勤務医の時間外・休日労働の年間上限は1,860時間 ・医療提供体制を考慮し、例外規定も設けられている |
参照:『建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制 (旧時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務)』厚生労働省
労働条件の明示ルール
2024年4月に施行された改正労働基準法では、全労働者に対する就業場所と業務の変更範囲を書面で明示することが義務づけられました。
条件の透明さを高め、「聞いていなかった」「そんなつもりじゃなかった」といったトラブル防止効果が期待されています。
有期契約労働者に対しては、契約更新の上限の有無とその内容を明確に示すことが追加され、将来の雇用の見通しが立つようになっています。
さらに無期転換申込権と、無期転換後の労働条件についても具体的に伝えなければなりません。
労働者との情報共有を徹底し、公正でわかりやすい雇用管理が求められるようになりました。
参照:『令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます』厚生労働省
裁量労働制のルール
裁量労働制に関する運用も、2024年4月施行の改正労働基準法で一部見直しが行われました。専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制について、新たな要件が追加されています。
両者に共通するのは、労働者の同意の撤回手続きに明確な規定が設けられた点です。
| 専門業務型裁量労働制 | 企画業務型裁量労働制 |
|---|---|
| 同意撤回手続きの明確化(制度適用には労働者本人の同意が必須に) | |
| ・M&Aアドバイザリー業務が新たに適用業務として追加 | ・労使委員会の運営規程に賃金・評価制度を説明 ・労使委員会は制度の実施状況の把握・改善を行う ・6か月以内ごとに委員会を開催・定期報告の頻度変更 |
参照:『企画業務型裁量労働制の解説』厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
参照:『裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です』厚生労働省
労働基準法は労働者保護を目的とする最低限のルール(まとめ)
労働基準法は、すべての労働者の基本的な権利を守るための「最低限のルール」です。
同法で定められた基準を下回る労働条件は無効となり、代わりに法律の定める基準が適用されます。
企業は以下の点にとくに注意を払う必要があります。
- 労働時間管理の適正化
- 賃金支払いの適正な実施
- 労働条件の明示と周知
- 各種法定帳簿の作成と保存
コンプライアンス経営が重視される現代において、労働基準法の理解と遵守は企業の社会的責任の基本です。
従業員が安心して働ける職場づくりのために、経営者や人事担当者は労働基準法の本質を理解し、適切な労務管理を実践することが求められます。
労働基準法に沿った労務管理をサポート|One人事[労務]
One人事[労務]は、労働基準法を遵守しながら、効率的な労務管理をサポートするクラウドシステムです。
労務処理のペーパーレス化を達成し、担当者の負担を軽減。One人事[勤怠]との連携により、企業全体の「働きやすさの実現」を支えます。
One人事[労務]の初期費用や気になる操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門スタッフが、貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、労務管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。労務管理をシンプルにして「本来やりたい業務」に集中したい企業は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
