労使協定を結んでいないとどうなる? 罰則とリスクや有給・育休の扱い、確認方法を解説
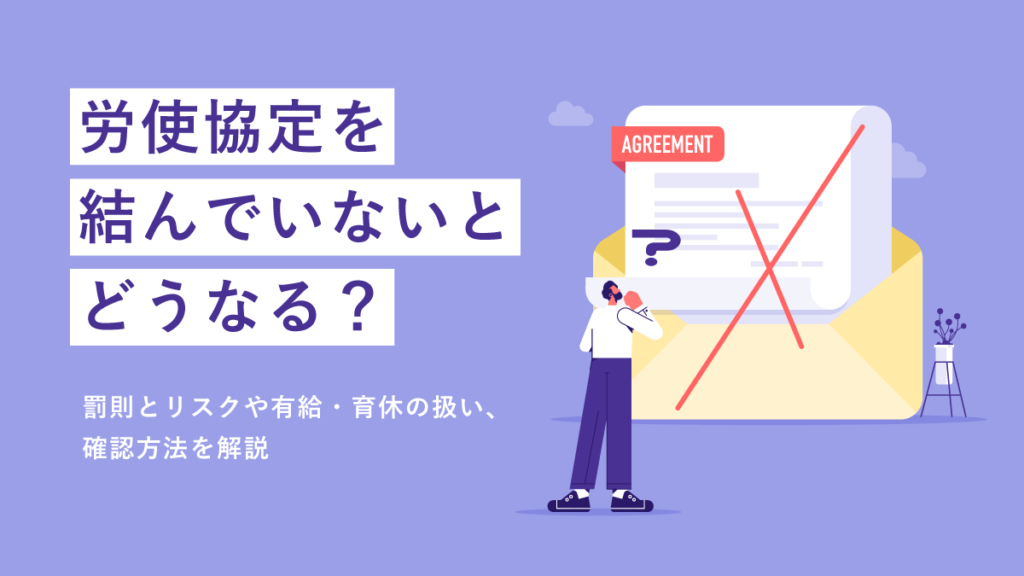
労使協定を結んでいないと、企業に罰則や行政指導が発生することをご存知でしょうか。 労働時間や休日労働に関する協定を結んでいないと、法的リスクが高まり、有給や育休の扱いにも混乱が生じます。
本記事では、労使協定を結んでいない場合に起こる問題や締結方法、現在適切に結ばれているかを確認する方法を解説します。自社の状況をチェックしながら、必要な対応を進めていきましょう。

 目次[表示]
目次[表示]
労使協定とは?締結は義務?
労使協定とは、企業と労働者の過半数代表者(または過半数労働組合)との間で労働条件に関して取り決めた約束のことです。働き方のルールは労働基準法をはじめとする労働関係法令に基づきますが、実際はさまざまな例外を設けなければ運用できません。
特定の労働条件や制度を導入するためには、労使協定を結ぶ必要があります。例外的なルールを設けて協定を結び、就業規則への明記とあわせて実施することで、法定義務が免除されるのです。
ただし、労使協定は常に締結が義務というわけではなく、労働者の残業のほか休日労働を予定している場合など、具体的な条件を満たす場合にのみ必要です。締結は任意ですが、働かせ方によって義務が生じる点をおさえておきましょう。

36協定は代表的な労使協定の一つ
ー般的に聞きなじみのある労使協定といえば「36協定(サブロク協定)」ではないでしょうか。
36協定とは、企業が従業員に法定労働時間を超えた残業や休日出勤をさせる前に、結んでおかなければならない協定です。
36協定を結んでいない状態で、残業や休日労働をさせると、労働基準法違反となり、罰則が科されるおそれがあります。
法定労働時間を超える労働が発生する職場では、必ず36協定を締結し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
▼36協定について基礎からおさらいするには以下の記事もご覧ください。
労使協定の種類・具体例
労使協定は、企業と従業員(またはその代表者)が労働条件について話し合い、合意する取り決めです。
労使協定には結ぶだけでよいものと、届け出が必要なものがあるので、対応を間違えないように詳しく見ていきましょう。
届け出が必要な労使協定の例
必ず届け出なければならない労使協定の例は、以下のとおりです。
| 届け出が必要な労使協定 | 関連する労働基準法 |
|---|---|
| 貯蓄の管理に関する協定 | 第18条 |
| 1カ月単位の変形労働時間制に関する協定 | 第32条の2 |
| 1年単位の変形労働時間制に関する協定 | 第32条の4 |
| 1週間単位の非定型変形労働時間制に関する協定 | 第32条の5 |
| 事業場外労働に関する協定 | 第38条の2 |
| 専門業務型裁量労働制に関する協定 | 第38条の3 |
| 企画業務型裁量労働制に関する協定 | 第38条の4 |
届け出を怠ると、協定は結ばれていない状態とみなされて法的に無効となります。たとえば、36協定や任意貯蓄に関する協定は、届け出が法的効力を持たせるための要件となっているため注意が必要です。
届け出が不要な労使協定の例
届け出が不要な労使協定の例は、以下のとおりです。
| 届け出が不要な労使協定 | 関連する法令 |
|---|---|
| 賃金から法定控除以外の控除を行う場合の協定 | 労働基準法第24条 |
| フレックスタイム制に関する労使協定※清算期間が1か月を超えない場合 | 労働基準法第32条の3 |
| 休憩の一斉付与の例外に関する協定 | 労働基準法第34条 |
| 年次有給休暇の時間単位で付与する協定 | 労働基準法第39条 |
| 年次有給休暇を計画的付与する協定 | 労働基準法第39条 |
| 年次有給休暇の賃金を標準報酬日額で支払う場合の協定 | 労働基準法第39条 |
| 育児休業、看護休暇および介護休業ができない者の範囲に関する協定 | 育児介護休業法第6条・第12条 |
以上の労使協定は労働基準監督署長への届け出は不要ですが、労働者代表の合意をとる必要があります。書面の作成や保存が不十分だと、将来のトラブルにつながる可能性もあります。
とくに、賃金の控除や有給休暇の取り扱いに関する協定は、従業員から納得されなければなりません。労使協定を結ぶ際は、合意形成の過程を記録に残しておくと安心でしょう。
必要な労使協定を結んでいないとどうなる?
労使協定は、企業が法定労働時間を超える時間外労働や休日労働をさせる際に必要な取り決めです。協定を結ばずに労働させると、法的リスクを抱えることになります。
どのような問題が発生するのか2つの視点から紹介します。
罰則が科される
労使協定、たとえば36協定を結ばずに時間外労働や休日労働を命じると、労働基準法違反となります。違反すると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
すぐに違反認定されるのではなく、まず行政指導が行われるのが一般的です。「是正勧告」のあと、勧告にしたがわないまま放置すると、最終的に罰則の対象となるリスクがあります。
適切な勤怠管理ができない
労使協定を結ばないと、労働時間や残業の管理があいまいになり、勤怠管理において次のようなリスクが発生します。
- 時間外労働が違法になるリスクが高まる
- 従業員の働き方に対する信頼が損なわれる
- 勤怠管理がずさんになり、トラブルが発生しやすくなる
労使協定を結ぶことで、企業は適法に労働時間を管理し、従業員との信頼関係を構築できます。
▼ずさんな勤怠管理を放置すると何が起こるのか? 7つのリスクを紹介

本来結ばなければならない労使協定の締結がもれているというケースは、そう多くはないかもしれません。しかし、36協定をはじめ労使協定は効力を発揮する期間が定められているものもあります。更新対応も確実に行うようにしましょう。
労使協定を結んでいないとできないこと
労使協定を結んでいないと、企業は以下のような制度を導入できません。当たり前の運用されている制度も、労使協定の締結が前提となっているということを理解しておきましょう。
時間外労働・休日出勤
法定労働時間を超えた時間外労働や休日出勤は、労使協定(36協定)を結んでいない場合には原則として禁止されています。
36協定を締結してはじめて、企業は従業員に対し月45時間、年間360時間を上限に、時間外労働や休日労働を指示できるのです。
また、特別条項付き36協定を結んでいても、年720時間や月100時間未満の制限を守らなければなりません。
▼36協定の特別条項を詳しく知るには以下の記事をご確認ください。
1年単位の変形労働時間制における法定労働時間を超えた労働
1年単位の変形労働時間制を導入するためには、労使協定の締結が必要です。
業務の繁閑に応じ、年間を通じて柔軟に労働時間を設定する1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、労働基準監督署長に届け出る必要があります。
育休の取得条件の設定
育児休業についても、労使協定を結ぶ必要があります。未締結の場合、育休の取得条件を制限できません。たとえば、短期雇用者が育児休業の対象外となることを定める場合には、協定の締結が必要です。
年次有給休暇の計画的付与
労使協定を結ぶことにより、年次有給休暇の計画的付与が可能になります。
計画的付与とは、企業が従業員と協議し、あらかじめ特定の日に有給休暇を取らせる仕組みです。有給休暇の消化を促す制度として、多くの企業が協定を結んでいます。
計画的付与制度について詳しく知るには以下の記事をご確認ください。
時間単位での年次有給休暇
労使協定を結ぶことで、有給休暇を時間単位で取れるようになります。
通常、有給休暇は1日単位での取得が基本です。時間単位で使えるようにすると、より柔軟に休みを取得でき、仕事とプライベートが両立しやすくなります。
通院や家庭の事情で数時間だけ休みたいときも、制度を利用すれば便利になり、従業員が働きやすい環境をつくれるでしょう。
有給休暇の時間単位について詳しく知るには以下の記事をご確認ください。
社宅家賃などの賃金控除
賃金の控除に関しても、労使協定が必要です。たとえば、社宅の家賃や福利厚生費などを給与から控除する場合は、労使協定に基づいて行う必要があります。
労使協定の締結方法【5つのステップ】
労使協定を締結するには、次の5つのステップを踏む必要があります。「何を」「どの順番で」「どうすればいいのか」 確認しておきましょう。
1.協定内容の作成、内容の協議
企業側(使用者)は協定の内容を作成し、労働者代表または労働組合と協議します。協定内容が労働基準法に準拠していることを確認しなければなりません。
2.労使協定の締結
労使協定を正式に締結します。
3.就業規則の変更
就業規則は、協定内容と矛盾がないように整備します。
4.労働者への周知
労使協定を結んだあと、企業には内容を労働者に周知する義務があります。
5.労働基準監督署長への届け出
36協定は、労働基準監督署長への届け出により、正式に効力を持ちます。
労使協定を結んだら周知する義務がある
労使協定を結んだら、労働基準法第106条1項に基づいて、内容を従業員に周知しなければなりません。周知方法には以下の3種類が認められています。
- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示、あるいは備えつける
- 書面を労働者に交付する
- 磁気テープや磁気ディスクに準ずるものに記録し、内容を常時確認できる機器を設置する
従業員が必要な情報を得られるようにわかりやすく交付します。従業員から質問や意見を受けつけるなど、一方的な通知にならないように注意しましょう。
以下のような場合には、周知義務を果たしたことにはなりません。
- 朝礼において口頭で説明した
- 特定の人物のみが入れる部屋に書面を掲示した
- 周知後、記録を消した
労使協定の周知は、従業員との信頼関係を築くプロセスでもあります。「やったことにする」だけではなく、内容理解を促し、必要なときに閲覧できる状態を維持しましょう。
労使協定が結ばれているか確認する方法
万一「うちの会社、ちゃんと労使協定を結んでいるのか?」と感じたら、以下の方法で確認できます。適切に手続きが完了していれば、次のいずれかで確認できるはずです。
| 一人ひとりへの交付 | ・会社が労使協定を締結した際に個別に交付された書面 |
| 誰でも手に取りやすい場所 | ・作業場に保管してあるファイル ・掲示板 ・書類の保管棚 |
| いつでも閲覧できるデジタルデータ | ・社内ポータルサイト ・イントラネット ・社内クラウド |
万一、労使協定が見つからない場合は、総務や法務と連携して確認してみましょう。「あるはず」と思い込まず、実際にすぐ取り出せる状態になっているかが周知のポイントです。
労使協定の締結に関する注意点
労使協定を結ぶ際は、企業ごとに必要な協定が異なることや、締結後の管理にも注意が必要 です。以下のポイントをおさえ、適切に手続きを進めましょう。
締結すべき労使協定は企業により異なる
労使協定は、企業の業務内容や規模に応じて締結が必要なものが異なります。36協定は残業や休日出勤がある場合に必須ですが、変則的な働き方を採用する企業は、裁量労働制やフレックスタイム制導入のための労使協定が必要です。
労使協定は事業所単位で締結する
労使協定は、原則として事業所ごとに締結しなければなりません。企業単位ではない点に注意しましょう。各事業所の労働条件や勤務形態に対応した協定を結ぶことで、適切な労働管理が実施されます。
たとえば、本社と支社で異なる労働時間制度を採用している場合、それぞれの事業所で別の協定を締結する必要があります。
また、労働者の過半数代表者の選出にも注意が必要です。使用者側の意向で選ばれた者が、代表者になることは認められていません。
定期的に届け出をし直す
労使協定には有効期間が定められているため、期限が切れる前に再度協定を締結し、労働基準監督署長へ届け出なければなりません。36協定も定期的な更新が義務づけられており、怠ると罰則の対象となります。
まとめ|労使協定を確実に結び働きやすい環境を整備
労使協定は、企業と労働者が対等な立場で合意し、労働条件や働き方を定める重要な取り決めです。
労使協定を結んでいないまま各制度を運用しても、制度は効力を持ちません。協定の種類によって、罰則の対象となる場合もあります。
労使協定を結ぶことで、労働者は安心して働ける環境が整い、企業も効率的に組織を運営できるようになります。
従業員の意欲やワークライフバランスにかかわるため、双方の意見を尊重しながら、安心して働ける職場環境を整えましょう。
