早退・遅刻が多い社員にどう対応する? 指導法や解雇の判断に関する注意点を解説
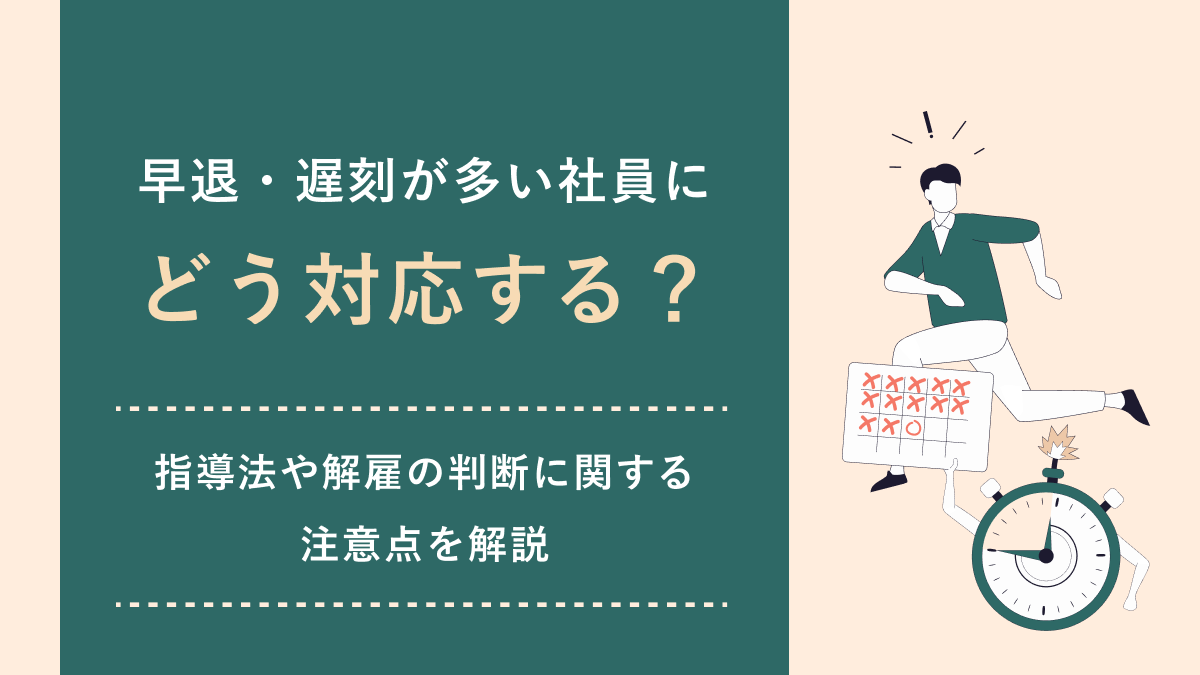
早退・遅刻が多い社員に、どのように対応すべきか悩んでいませんか。「また遅刻か……」と思いながらも、声のかけ方や指導の仕方に迷う場面は少なくありません。注意しても改善しない場合には、指導や処分の判断に悩むこともあるでしょう。
本記事では、早退・遅刻を繰り返す社員への指導法から対応のステップ、改善がみられない場合の対応策、解雇を検討する際の法的な注意点まで詳しく解説します。

 目次[表示]
目次[表示]
早退・遅刻を繰り返す社員への指導方法
早退・遅刻を繰り返す社員への対応は、単に叱責するだけでは効果がなく、根本的な原因を探り、適切な指導を行うことが重要です。ここでは、早退・遅刻を繰り返す社員に対する段階的な指導方法について解説します。
- まずは原因を把握する
- 改善すべきだということを明確に伝える
- 改善が必要な理由を考えさせる
- 一緒に対策や目標を考える
- 改善がみられたら褒める
まずは原因を把握する
早退・遅刻が多い社員への指導で最初にすべきは、原因の把握です。頭ごなしに叱っても問題は解決しません。まずは1対1の面談や人事部を交えた面談、本人の話をじっくり聞くことから始めましょう。
遅刻の理由には、寝坊や時間管理の甘さといった本人の問題のほか、介護・育児などの家庭事情、うつ病や睡眠障害など健康上の要因が潜んでいる場合も考えられます。
とくに本人も気づいていない体調不良が背景にあるケースでは、産業医の受診を促すなど、会社としての配慮も必要です。表面的な行動だけでなく、遅刻の背景にある事情を理解する姿勢を示しましょう。

改善すべきだということを明確に伝える
社員の遅刻の原因がわかったら、今後は改善すべき行動であることを明確に伝えましょう。単に「遅刻はダメ」と伝えるのではなく、どのような影響を周囲に与えているかを具体的に示すのが効果的です。
たとえば「あなたが遅れると、朝礼が始められず、ほかの社員の予定にも支障が出る」と伝えると、当事者意識が芽生えやすくなります。日付や時間など数字や実例を交えると、より説得力が増すでしょう。
| 伝え方のポイント | 声かけ例 |
|---|---|
| 影響を具体的に伝える | 1週間毎日5分の遅刻で、合計30分近くの労働時間が無駄になります。 |
| 周囲への影響を説明 | 朝の会議が遅れ、チーム全員のスケジュールも遅れます。 |
遅刻・早退に関するルールや、違反した場合の懲戒処分の可能性についても、就業規則に沿って冷静に伝えることで、問題の重大さを認識してもらえます。
改善が必要な理由を考えさせる
指導する際は、遅刻や早退がなぜ問題なのか、本人自身に考えさせることも有効な指導法です。会社や上司から一方的に伝えるよりも、問いかけを通じて気づきを促すことで、内面からの意識変化を引き出せるかもしれません。
| 問いかけの例 | 狙い |
|---|---|
| あなたが遅刻をすると、誰が仕事をカバーすると思いますか? | 周囲への負担に気づかせる |
| この状況が続いたら、チームにどんな影響があると思いますか? | 規律の意味を考えさせる |
遅刻の常習化は、職場のモラルや生産性に直接影響を与える行為です。本人の行動が「悪い手本」となり、周囲に与える影響を説明し、改善の必要性を自覚させましょう。

一緒に対策や目標を考える
遅刻・早退を繰り返す社員に改善を促すには、上司だけで対策を決めるのではなく、本人と一緒に考える姿勢も大切です。行動を変えるには、当事者意識を高めることから始めましょう。
たとえば「目覚ましを2つ使う」「前日の就寝時間を1時間早める」など、具体的で現実的な方法を本人から引きだすことがポイントです。目標は「1か月遅刻ゼロ」など、短期で達成可能なレベルから設定すると効果的です。
また健康や家庭の事情がある場合は、フレックス勤務や時短制度など、柔軟な働き方の導入も検討します。必要に応じて人事部とも連携し、無理のない範囲で働ける環境を整えましょう。
定期的なフォローアップ面談を通じて改善状況を確認し、本人の改善努力を認めながら、対策を見直し、行動をサポートしていくことが重要です。
改善がみられたら褒める
繰り返しの遅刻・早退に改善がみられたときは、なるべく早く前向きなフィードバックを伝えましょう。ほめられることで、行動の定着が促進され、本人のモチベーションにもつながります。
注意したいのは「周囲に配慮した伝え方」です。恥ずかしさや反感を避けるため、1対1で具体的に何がよかったのかを伝えます。
| 声かけの例 | ポイント |
|---|---|
| 今週は毎日定時出社でしたね | 具体的な成果に触れる |
| 朝の準備を工夫した成果が出ていますね | 本人の努力を認める |
一時的な改善であっても、変わったことに気づいて評価することが大切です。万一、再び遅刻が増えた場合も、あらためて原因を確認し、指導方法を見直す柔軟な対応が求められます。

早退・遅刻が多い社員に対して避けたい対応
遅刻・早退が多い社員には、状況を正しく把握し、適切な指導と改善支援を行うことが基本です。しかし、対応の仕方を誤ると、本人のモチベーションを下げたり、職場全体の雰囲気を悪化させたりするおそれがあります。
遅刻・早退の問題は、体調不良や家庭の事情など、本人なりの事情が隠れていることも少なくありません。
遅刻・早退時に、ついやってしまいがちな3つのNG対応と、その理由を解説します。
- 指導を諦める
- 頭ごなしに叱る
- 人前で叱る
それぞれの対応がもたらす影響を理解することで、より適切な指導につなげられるでしょう。
指導を諦める
何度遅刻・早退を注意しても改善が見られない社員に対し、「もう言っても無駄」と指導をやめてしまうことがあります。しかし、これは避けたい対応の代表例です。注意しないまま放置すれば、本人は「遅刻しても何も言われないから問題ない」と誤解し、遅刻・早退が常態化する可能性があります。
さらに、真面目に出勤している他の社員の不満が高まり、不公平感から職場の士気が低下することも考えられるでしょう。規律が崩れると、ほかの社員にも悪影響が波及しかねません。
一度ゆるんだ勤務意識を元に戻すのは困難です。「言っても仕方ない」「何度も言うのは気が重い」と感じたときこそ、冷静に事実と期待を添えて、根気よく対応することが大切です。
頭ごなしに叱る
遅刻や早退を繰り返す社員に対して、「また遅刻か」と頭ごなしに叱りつけるのも逆効果です。感情をぶつけても、本人は「否定された」と受け止め、防衛的になったり反発したりするだけです。今後の改善の意欲はむしろ下がります。
近年はハラスメントへの意識が高まっており、感情的な叱責はパワハラと判断されるリスクもあります。叱ることは必要でも、冷静に事実と影響を伝え、改善策を一緒に考える姿勢が欠かせません。
怒りを感じたら、怒りのピークといわれる6秒深呼吸して、気持ちを落ち着けるとよいでしょう。まずは冷静さを保つことが、指導の成果につながります。
人前で叱る
早退・遅刻が多い社員を、ほかの社員がいる前で注意するのは避けるべき対応です。公の場で叱ると、本人の自尊心を傷つけ、反発や恨みを抱かせることになります。
人前で叱られると、パワハラとみなされる可能性もあり、職場全体の雰囲気が悪化する原因になります。周囲の社員も、叱られるとさらし者にされると萎縮してしまうかもしれません。
遅刻・早退の注意や指導は、必ず1対1で、プライバシーが確保された個室で行うのが基本です。「あとで少し話しましょう」と事前にひと言かけ、落ち着いた場所で対話するようにしましょう。
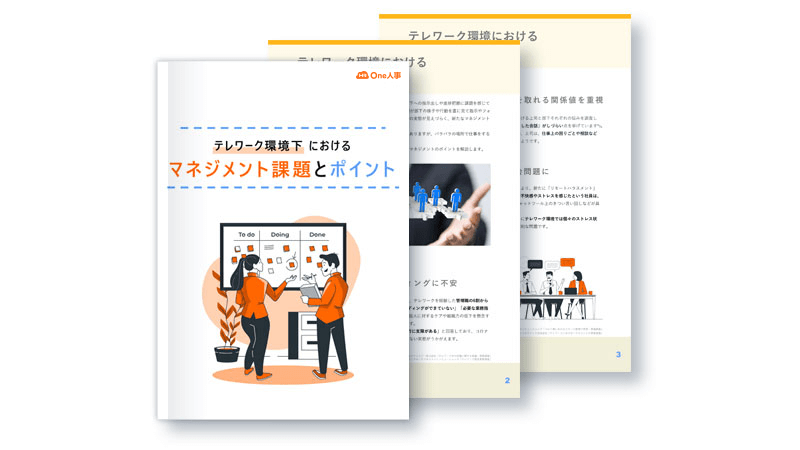
遅刻・寝坊が多い社員の特徴
遅刻や寝坊を繰り返す社員には、いくつかの共通した特徴があります。特徴を理解すれば、感情的に叱るのではなく、冷静で建設的な指導がしやすくなるでしょう。
ここでは、職場でよく見られる「遅刻・寝坊が多い社員」の代表的な3つのタイプを紹介します。
- 出社までの時間配分が正しくできない
- マイペースで楽観的
- こだわりが強い
出社までの時間配分が正しくできない
遅刻を繰り返す社員にもっとも多いのは、時間を逆算して行動できないタイプです。時間配分や予測が苦手で、支度や移動の所要時間を大雑把に考える傾向があります。
たとえば「通勤に30分かかるから、30分前に出れば間に合う」と考えても、玄関での準備や駅までの信号待ち、電車の混雑などを見込んでおらず、結果的にギリギリになるのです。
また、忘れ物や天候といったちょっとした想定外にも弱く、予備時間を確保できないことで遅刻につながります。予測能力が低い人には、「もっと早く起きなさい」と言うだけでは根本的な改善は難しいでしょう。予測力や計画力をどう補えるか、一緒に対策を考えなければなりません。
マイペースで楽観的
遅刻が多い社員で次に多いのが、マイペースで楽観的な性格のタイプです。出社時間よりも自分のルーティンを維持しようとする傾向があり、遅刻が周囲に与える迷惑に無自覚なこともあります。
「たぶん大丈夫だろう」「間に合わないなら焦っても仕方ない」といった甘い考えから、朝食をゆっくりとる、身支度に時間をかけるといった行動に走りやすくなります。
遅刻の注意を受けても、「まあいいか」と聞き流してしまうため、何度も遅刻を繰り返すケースも少なくありません。
マイペースな従業員には頭ごなしに叱るよりも、遅刻によってチームにどんな影響が出ているかを相手の立場に立って伝えると、自覚を促すきっかけになります。
こだわりが強い
遅刻が多い社員の最後の特徴は、身だしなみや習慣に対してこだわりが強すぎるタイプです。服装やメイク、髪型が思い通りに決まらないと納得できず、出発時間が後ろ倒しになるケースがあります。
「完璧にしたい」「気に入らないと外に出られない」といった強いこだわりから、何度も着替えたり、メイクをやり直したりするうちに遅刻してしまうのです。
こだわりが強いタイプには、前日に服を選んでおく、支度のタイムリミットを決めるなど、時間を守る工夫を一緒に考えることをおすすめします。こだわりを否定するのではなく、まずは「そのままの自分を活かしつつ時間も守るにはどうするか」という視点で支援していくのがよいでしょう。
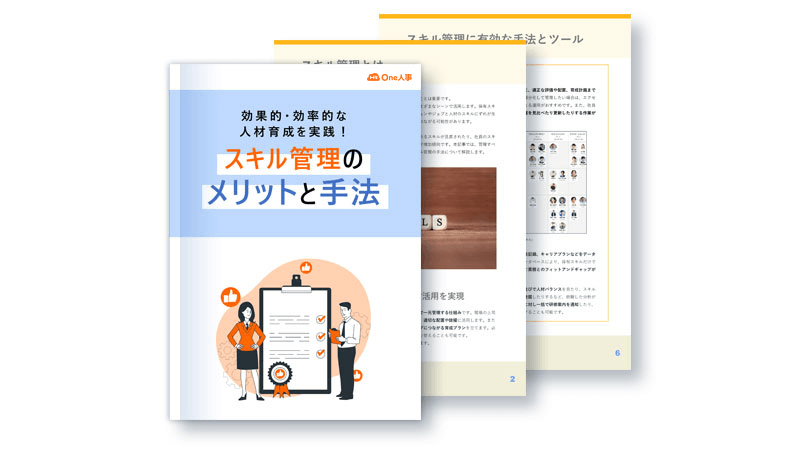
早退・遅刻が多い社員がいる企業が検討したいポイント
遅刻や早退が多い社員への対応は、本人への個別指導だけでなく、組織としての仕組みづくりも欠かせません。制度やツールを見直すことで、再発防止や職場全体の生産性向上にもつながります。ここでは、企業として検討したいポイントを2つ紹介します。
勤怠管理システムの導入
まずは勤怠管理システムを活用して、遅刻や早退の実態を正確に把握することが重要です。アナログな勤怠管理の方法では、問題が放置されてしまう可能性も否定できません。
勤怠管理システムを活用し、仕組みを整えましょう。クラウド型の勤怠管理システムであれば、従業員の出退勤や遅刻・早退の状況をリアルタイムで確認でき、問題が常態化する前に対応できます。
また、労働時間の自動集計やアラート機能により、管理業務の効率化と不正防止にもつながります。勤怠を透明化し、職場全体の時間意識を高める必要があります。
→使いやすい勤怠管理システムOne人事[勤怠]の特長はこちら

柔軟な働き方への対応
遅刻や早退の原因が生活環境や体調にある場合、フレックスタイム制などの柔軟な働き方を導入するのも有効な解決策です。
フレックスタイム制は、一定期間内の総労働時間を前提に、始業・終業時刻を従業員が自由に調整できる制度です。朝に弱いタイプの社員でも、自分のリズムにあわせて午後の出勤にできるため、遅刻という概念がなくなります。
本人が集中しやすい時間帯を選んで働けるため、生産性や効率の向上にもつながるでしょう。育児や介護といった事情を抱える社員の離職防止にも効果的です。
勤務制度の導入や見直しは、社員の働きやすさを高めるだけでなく、組織全体のパフォーマンス向上も期待できます。

寝坊による遅刻や、早退を繰り返す社員を懲戒処分(解雇)にできる?
寝坊や早退を繰り返す社員に対して、懲戒処分や解雇ができるのか悩む企業もいますよね。
労働者には、就業時間を守る義務があり、遅刻や早退の常習化は企業秩序を乱す行為として、適切な対応が求められます。
ただし、懲戒処分を行うには就業規則への明記が必要です。労働契約法第15条では、懲戒の種類とその事由をあらかじめ就業規則に定めておくことが義務づけられています。
多くの企業では「正当な理由なく繰り返し遅刻・早退を行った場合」などを懲戒事由としています。また処分は「けん責」「減給」「出勤停止」「懲戒解雇」と段階的に対応しなければなりません。
懲戒解雇を正当とするには、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要です。頻繁な遅刻・早退により業務に重大な支障が出ており、会社が繰り返し注意・指導を行っても改善が見られない場合に限られます。
早退・遅刻が多い社員を懲戒処分にする際の注意点
懲戒は従業員にとって不利益となる処分であり、安易に決めると訴訟や労使トラブルに発展するリスクがあります。遅刻や早退を繰り返す社員に対し、懲戒処分を検討する場合も、慎重に進めなければなりません。
ここでは、遅刻・早退に対する懲戒処分を実施する際の手続きと、注意点について解説します。
- すぐに懲戒処分を判断してはいけない
- 注意指導記録を残す
- 雇用契約書や就業規則を確認する
- 弁明の機会を与える
- 段階的に処分を与える
すぐに懲戒処分を判断してはいけない
遅刻・早退を理由にいきなり懲戒処分を行うのは避けましょう。懲戒には「客観的・合理的な理由」が必要であり、「社会通念上の相当」と認められなければなりません。
遅刻や早退が数回あっただけで、すぐに懲戒処分を決めると、懲戒権の濫用と判断される可能性が高いです。
口頭での注意から始め、改善がみられない場合は書面による警告を行うなど、段階を踏んで指導しましょう。
遅刻の背景には健康上の問題や家庭事情など、やむを得ない事情が潜んでいるケースもあります。 一方的に処分を下すのではなく、本人と状況を共有しながら改善の道を探ることが大切です。
注意指導記録を残す
早退・遅刻が多い社員に対して、注意や指導を行った場合、内容や日時、本人の反応などを記録として残しておきましょう。たとえば、以下のような記録を残しておくことをおすすめします。
- 遅刻・早退の日時と頻度
- 注意・指導を行った日時と内容
- 本人の弁明内容や反応
- 改善を約束した内容
- 面談の際の第三者の立会人
「指導記録を残すのは面倒」と感じる管理者の方もいるかもしれませんが、簡単なメモで構いません。万一、訴訟に発展した場合も証拠として役立ちます。
雇用契約書や就業規則を確認する
懲戒処分を行う前に、就業規則や雇用契約書に、遅刻・早退に関する懲戒規定が明示されている必要があります。以下の内容を確認しましょう。
- 遅刻・早退が懲戒事由となること
- 懲戒処分の種類と段階
- 各処分の適用条件
たとえば「無断でしばしば遅刻・早退・欠勤を繰り返し、複数回の注意にも改善が見られない場合」など、具体的に記載されていることが望ましいです。
就業規則に明確な規定がない場合、懲戒処分が無効となる可能性があるため注意しましょう。また、就業規則を従業員に周知していなければ、効力が認められないことがあります。
弁明の機会を与える
懲戒処分を実施する前には、遅刻を繰り返す社員に弁明の機会を与えることが重要です。法的に明確な義務があるわけではありませんが、処分の妥当性を判断するうえで、「本人に弁明の機会を与えたかどうか」は重要視されています。
弁明の機会を与える際は、以下の点に注意しましょう。
- 処分の理由となる事実を具体的に示す(例:「〇月〇日と〇月〇日の遅刻」)
- 弁明書の提出期限は1週間程度を目安に設定する
- 可能であれば口頭での説明の場も設ける
- 弁明の内容を真摯に検討する
弁明の機会を与える必要があるのか、疑問に思う管理者もいるかもしれません。一方的に処分を決めるのではなく、本人の言い分を聞くことで、隠れた事情や誤解が明らかになることもあります。弁明を聞いたうえで最終的な処分を判断することが、公平な対応につながります。
段階的に処分を与える
懲戒処分は、軽いものから順に段階的に行うのが原則です。いきなり重い処分を行うと、懲戒権の濫用と判断される可能性が高まります。
一般的な懲戒処分の段階は以下のとおりです。
| 1 | 戒告・けん責 | 口頭または書面による注意。けん責では始末書提出も求める。 |
| 2 | 減給 | 一部給与を減額(※労働基準法91条による上限あり) |
| 3 | 出勤停止 | 一定期間の出勤を禁止。給与は無給。通常1日~1週間程度。 |
| 4 | 降格 | 役職・資格等級を引き下げ。給与減少の可能性あり。 |
| 5 | 諭旨解雇(諭旨退職) | 自主退職を促し、応じない場合は懲戒解雇。社会的な配慮あり |
| 6 | 懲戒解雇 | もっとも重い処分。即時解雇。退職金不支給もあり得る |
まとめ
早退・遅刻が多い社員への対応には、職場の規律維持と個別の事情への配慮、両面の視点が求められます。繰り返される遅刻や早退は、業務効率の低下だけでなく、周囲の士気や職場全体のモラルにも影響を与えかねません。
一方で、介護や健康問題などやむを得ない事情が背景にある場合もあります。まずはていねいに状況を確認し、必要に応じた支援や働き方の見直しを検討しましょう。
怠慢や規律違反が原因の場合には、段階的な指導と適切な処分で対応することが重要です。冷静かつ公正な対応が、信頼される職場づくりにつながります。
