時間外労働と残業の違いを簡単に|定義と人事が最低限知っておきたい基本ルールを解説
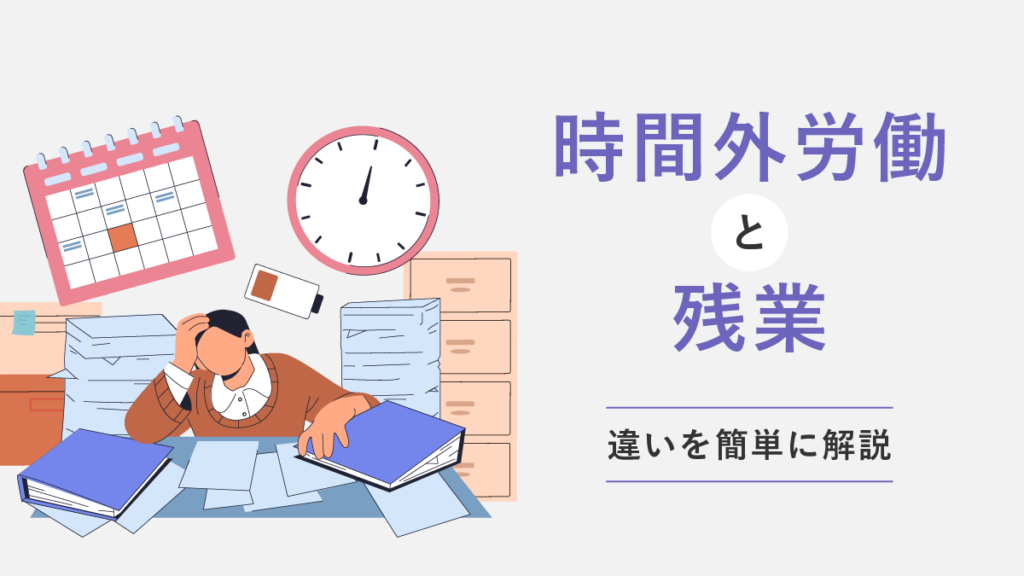
所定の終業時間後も会社に残って仕事をすることを、「残業」と呼びますか。それとも「時間外労働」でしょうか。
「残業」と「時間外労働」は似たような場面で使われますが、法律上では少し異なる意味を持つ場合があります。
本記事では「時間外労働」と「残業」の言葉の定義や使い分けをわかりやすく解説し、企業が最低限知っておきたい基本ルールも紹介します。
2019年4月以降の改正労働基準法の施行により、労働時間の管理がさらに重視されるようになりました。残業や時間外労働の管理の基本を身につけ、安心して業務に取り組むためにお役立てください。
先に労働時間の管理方法をより詳しく知りたい方は、以下の資料もぜひご覧ください。

 目次[表示]
目次[表示]
残業と時間外労働とは? 基本の定義を確認
まずは時間外労働と残業、それぞれの意味を整理していきます。2つの言葉は違う内容を指すことも、同じ意味を指すこともあるため、混乱してしまうことも少なくありません。基本的な定義をおさえていきましょう。
時間外労働とは
時間外労働は、労働基準法に基づいた法定労働時間を超えて働くことです。
労働基準法では、法定労働時間を「1日8時間」「1週間40時間」と定めています。法定労働時間を超える労働が発生した場合、超過分を「時間外労働」と呼びます。時間外労働には深夜労働(22時〜翌5時)や休日労働も含まれています。
たとえば、従業員が1日9時間働いた場合、8時間を超える1時間が時間外労働です。企業が従業員に時間外労働をさせるには36協定の締結が必要で、また割増賃金の支払い義務があります。
ただし、法定労働時間を超える「法定時間外労働」でなくても、企業が独自に定めた所定労働時間を超える労働を指して、「所定時間外労働」と呼ぶ場面もあります。
| 法定時間外労働(法定「外」残業) | 労働基準法で定められた法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えた労働 |
| 所定時間外労働(法定「内」残業) | 企業が独自に定めた所定労働時間を超えた労働 |
法定時間外労働に対しては割増賃金の支払いは必須ですが、所定時間外労働に対しては支払いは不要です。もちろん企業独自のルールで支払いを定めても問題ありません。
法定外と所定外の時間外労働について、より詳しく知りたい方は以下の記事もご確認ください。
法定労働時間はすべての職場で共通の基準であり、特定の職種を除いて、地域や職業によって異なることはありません。とくに繁忙期になると、意図せずに時間外労働が増える職場もあるでしょう。しかし、企業は常に法定労働時間を基準として、労働時間を管理するのが基本です。
残業とは
残業とは、従業員があらかじめ決められた勤務時間を超えて残って仕事をすることです。法律的な定義というより、日常的に広く使われる表現といえます。
企業が定めた所定労働時間が9時〜18時であるなら、18時を過ぎてからも仕事をすることが残業です。この場合、残業と時間外労働の意味は重なります。
ただし労働時間は企業ごとに異なるため、残業とみなされる基準も企業ごとに変わります。法定労働時間を超える時間外労働に該当しなくても、「残業」と呼ばれる時間があるのです。
たとえば、所定労働時間が9時〜17時である会社では、18時まで残って仕事をしても、法定労働時間の1日8時間は超えません。しかし、定時の17時を過ぎた1時間分は「残業」と呼ぶのです。
また企業の終業時刻を超えた労働だけでなく、始業時間前に働くことを「早出残業」と呼ぶのが一般的です。
残業は、所定労働時間からはみ出た時間で仕事をすることを指す、日常的な表現と理解するとよいでしょう。

残業時間と時間外労働の違いとは?
時間外労働と残業は業務上、意味が重なる場面も多くありますが、違いを明確にするのなら、以下の5つの項目で対比できます。とくに割増賃金の支払い義務については企業の労務管理上、おさえておきたい重要なポイントです。
| 残業 | 時間外労働 | |
|---|---|---|
| 定義 | あらかじめ決められた勤務時間を超えて残って仕事をすること | 法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働くことや、法定休日、深夜帯に働くこと |
| 法律 | 厳密には法律用語ではない | ・労働基準法で明確に定義されている ・残業を法律上定義した概念 |
| 基準 | 会社ごとに基準が異なる | 法律で定義されているため、全国一律どの業種や職種でも基本的に統一された基準 |
| 深夜労働・休日労働を含むか | 一般的に含まない始業時間前に働く時間は早出残業時間 | 含む |
| 割増賃金の対象か | 時間外労働と重なる残業に対しては割増賃金が発生するが、必ずしも割増賃金が発生するわけではない | 法定労働時間を超えた時間分や、法定休日の労働、深夜帯の労働に対して必ず割増賃金が発生する |

残業・時間外労働に関する基本ルール
ここからは企業が労務管理を行ううえで、残業や時間外労働について最低限おさえておきたいルールを紹介します。
企業が従業員に対して残業や時間外労働を命じる場合、法的にいくつかの重要な義務を果たす必要があります。
ルールを守らないと、企業は法律違反として罰則を受ける可能性があるだけでなく、従業員の健康やモチベーションを損なうリスクもあります。法律に沿った運用を徹底することが重要です。
| ルール1 | 残業を命じる場合は36協定の締結が必要 |
| ルール2 | 時間外労働には上限がある |
| ルール3 | 時間外労働の割増賃金の計算方法を把握する |
時間外労働を命じる場合は36協定の締結が必要
企業が従業員に時間外労働を命じるには、労働基準法第36条に基づく「36協定」を締結する必要があります。
36協定は、企業と労働者代表との間で合意されるものであり、法定労働時間を超えた労働をさせるための法的な根拠となります。
36協定は、単に締結するだけではなく、労働基準監督署長に届け出ることで有効となります。届け出を怠ると、違法な労働とみなされ、企業は法的なリスクを抱えることになります。
36協定の締結方法や管理を詳しく知るには、以下の記事もご確認ください。
時間外労働の割増賃金の計算方法を把握する
時間外労働に対して適切な割増賃金を支払う義務が労働基準法で定められています。
法定労働時間を超えた労働には25%以上の割増率が、60時間を超える労働には50%以上の割増率を適用しなければなりません。
また、深夜労働(22時~翌5時)や休日労働に対しても、さらに高い割増率が適用される場合があります。
割増賃金の計算方法は法律で厳密に規定されているため、企業は計算方法を正確に理解し、適切な賃金を従業員に支払う必要があります。
計算を誤ると、未払い残業代として従業員から訴えられる可能性があり、ミスを防ぐ仕組みづくりが重要です。
| 割増賃金の種類 | 条件 | 割増賃金率 |
|---|---|---|
| 法定時間外労働 | 1日8時間、1週間40時間を超えた労働 | 25%以上 |
| 法定時間外労働(60時間超え) | 中小企業を除く、1ヶ月に60時間を超えた法定時間外労働 | 50%以上 |
| 休日労働 | 法定休日に労働した場合 | 35%以上 |
| 深夜労働 | 22時~翌5時の間に労働 | 25%以上 |
割増賃金の計算方法を例を交えて詳しく知るには、以下の記事もご確認ください。
時間外労働には上限がある
働き方改革の推進にともない、時間外労働には厳しい上限が設定されています。
企業が従業員に月45時間、年間360時間を超える労働を課すことは認められていません。臨時的な特別の事情があっても、基本的な制限は大きくは変わりません。
たとえば、特別条項付き36協定を結んだ場合でも、月100時間未満、2~6か月間の平均で月80時間以内などの上限が定められています。上限を超える労働をさせると、企業は労働基準法違反となり、罰金や懲役などの罰則が科せられる可能性があります。
時間外労働の上限規制を遵守することは、法的リスクを回避するだけでなく、従業員の健康を維持し、働きやすい職場環境を守るためにも重要です。
時間外労働の上限規制を詳しく知るには、以下の記事もご確認ください。
残業・時間外労働の上限規制に関する注意点
時間外労働の上限規制を遵守することは、企業にとって不可欠です。法的な罰則を避けるだけでなく、従業員の健康や生産性を保つためにも、企業が注意したいポイントを整理しておきましょう。
| 注意点1 | 従業員の労働時間を適切に把握する |
| 注意点2 | 自社にあった36協定であるかを見直す |
| 注意点3 | 管理職の労働時間管理にも気を配る |
| 注意点4 | 勤務時間後に一定以上の休息を設けるよう努力する |
従業員の労働時間を適切に把握する
従業員の労働時間を適切に把握することは、残業・時間外労働時間の管理をするうえで、もっとも基本的な対応です。企業が労働時間を正確に記録していない場合、残業時間が予期せず増加し、上限を超えてしまうリスクがあります。
企業は勤怠管理システムの導入など、リアルタイムで労働時間を管理するツールを活用し、常に従業員の労働状況を把握できる体制を整えることが必要です。
労働時間の管理が効率的でないなど、勤怠管理に課題がある企業や乗り換えをご検討の企業は、以下の資料を参考にしてください。

自社にあった36協定であるかを見直す
企業は、定期的に自社の36協定の内容を見直し、現在の業務内容や従業員の働き方に適合しているかを確認することが重要です。業務の変化にともなって従業員の働き方も変化するため、協定内容が古くなっている場合や、現状にそぐわない内容が含まれている場合もあるでしょう。
36協定は有効期限がありますので、定期的に見直し、修正しましょう。更新について知るには以下の記事も参考にしてください。
管理職の労働時間管理にも気を配る
管理職(法律上の管理監督者)は、一般の従業員とは異なり休憩時間や休日、休憩の規定が適用されません。
しかし、労働安全衛生法の改正にともない、管理職の労働時間も適切に管理する必要性が増してきました。
とくに「名ばかり管理職」として労働時間が過剰に長くなる場合、健康に悪影響を及ぼし、最悪の場合、企業の信用を損ねるリスクがあります。
管理職に対しても、労働時間の管理を徹底し、適切な休息を取るよう指導しましょう。
勤務時間後に一定以上の休息を設けるよう努力する
長時間労働が続くと、従業員の健康が損なわれるリスクが高まります。過重労働対策の一環として、企業には「勤務間インターバル制度」の導入が推奨されています。
勤務間インターバル制度とは、勤務終了後から次の勤務開始までに一定の休息時間を確保し、過労による事故や健康障害を防ぐ仕組みです。従業員が十分に心身を休められる環境を整えることが重要です。
勤務間インターバル制度についてさらに詳しく知るには以下の記事もご確認ください。
まとめ
「時間外労働」と「残業」は日常的に混同されることが多いですが、法的には異なる意味があります。
一般的に時間外労働は、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働を指し、36協定の締結や割増賃金の支払い義務が発生します。一方、残業は企業が定めた所定労働時間を超える労働を指し、法定労働時間を超えない残業もあるのです。
企業は、時間外労働の上限規制や割増賃金の計算方法といった法的ルールを理解したうえで労務管理を行うことが重要です。
「時間外労働」と「残業」の意味を区別して、労務管理を強化し、安心して働ける環境を目指しましょう。
残業・時間外労働の管理に|One人事[勤怠]
One人事[勤怠]は、効率的な残業・時間外労働の管理をサポートするクラウド型勤怠管理システムです。
残業が多い従業員へのアラート通知機能や、残業の事前申請機能があらかじめ搭載されています。
One人事[給与]と連携すると、労働時間の集計から割増率の適用・計算まで、スムーズに業務を進められます。
「残業管理に課題がある」「法律に沿った勤怠管理に不安がある」という企業は、検討してみてはいかがでしょうか。もちろん貴社の課題に応じて、単一サービスだけの部分導入も可能です。
One人事[勤怠]の初期費用や気になる操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。当サイトでは、勤怠管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。勤怠管理をシンプルにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
