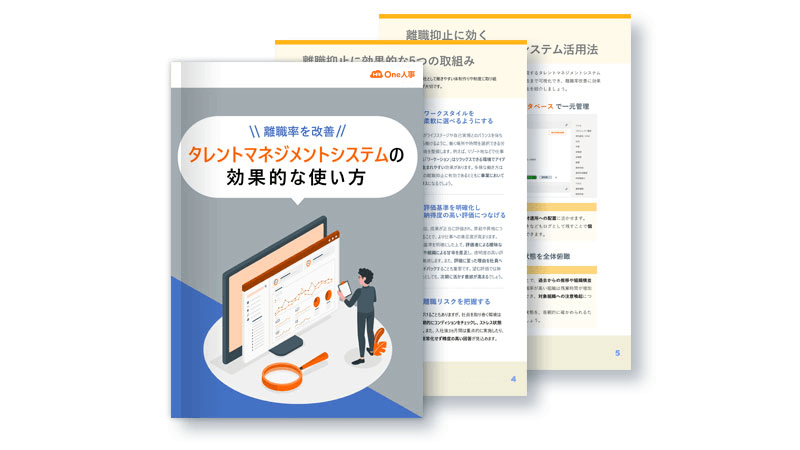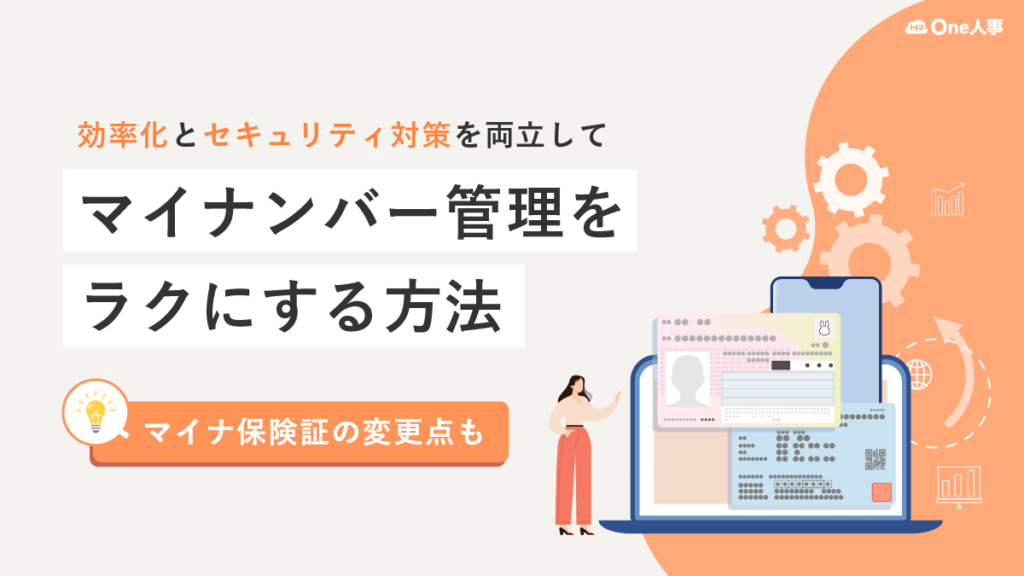人事労務管理とは? 基礎知識から最新法改正への対応と効率化のポイントを徹底解説
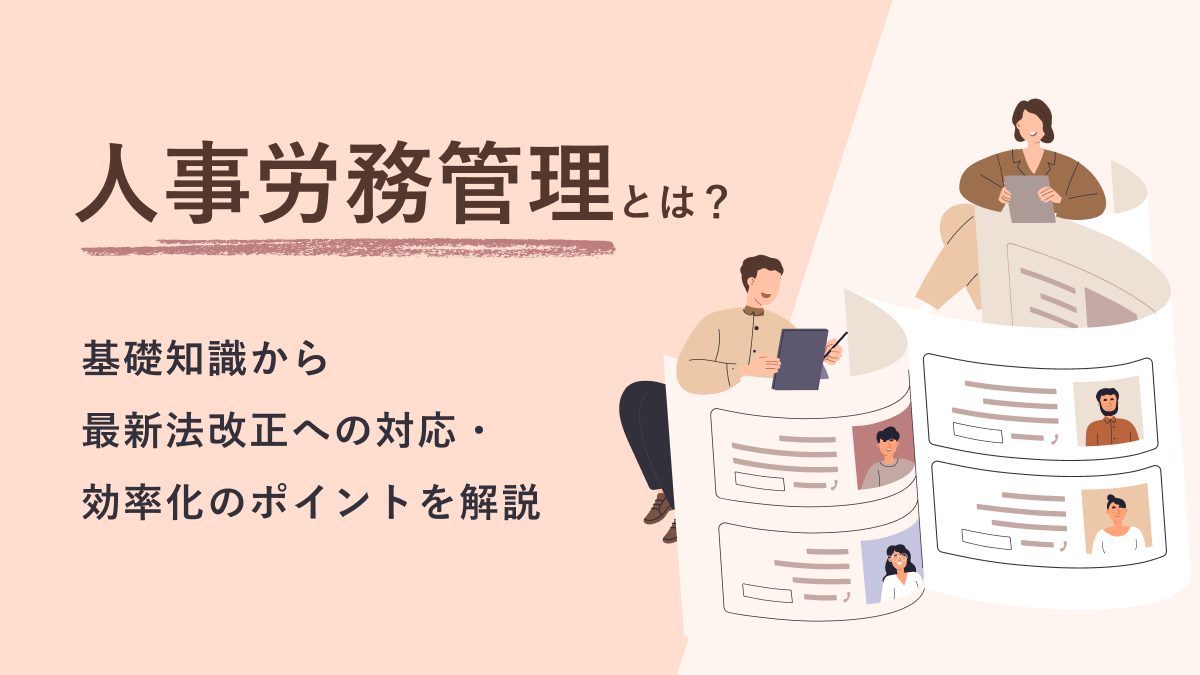
人事労務管理は、企業経営を支える欠かせない業務です。しかし、法律の改正や煩雑な手続きに追われ、負担を感じる場面も少なくないでしょう。
適切な人事労務管理は、社員の働きやすさを支えています。そのためにも、基本的な知識を整理し、最新のルールや効率化の方法をおさえておくことが大切です。
本記事では、人事労務管理の基本から2025年の主な法改正のポイント、日々の業務を効率化する具体策まで、わかりやすく解説します。ぜひ明日からの実務に役立ててください。
→人事労務管理を効率化する「One人事」の資料をダウンロードする

 目次[表示]
目次[表示]
人事労務管理とは?
人事労務管理とは、企業にとって大切な経営資源である「ヒト」を適切に管理し、活かしていく業務です。組織が持続的に成長し続けるための土台をつくる役割を担っています。
従業員の採用から退職までの一連のプロセスを管理し、働きやすい環境を整えることが大切です。同時に、一人ひとりの能力や個性を最大限に引き出し、人材の定着や成長を促していきます。
人事労務管理は、生産性の向上や法令遵守を実現するだけでなく、労務トラブルを防いだり、社員一人ひとりのモチベーションを維持したりすることにもつながります。
人事管理と労務管理の違い
人事労務管理は、「人事管理」と「労務管理」という2つの側面で成り立っています。どちらも深くかかわっていますが、目的や業務内容には違いがあります。
人事管理は、主に「人材を戦略的に活用すること」に焦点を当てている管理業務です。具体的には、採用から育成、評価、配置まで従業員を直接的に支援する活動が含まれます。
一方、労務管理は「労働環境を適正に整えること」が中心です。労働法に基づき、働く環境を整備したり、従業員の健康や安全を守ったりするなど、日常業務を円滑に進めることを目的としています。
人事管理と労務管理の違いをまとめると、以下のとおりです。
| 人事管理 | 労務管理 | |
|---|---|---|
| 主な目的 | 人材の戦略的活用・長期的育成 | 労働環境の適正化・法令遵守 |
| 主な業務内容 | 人材採用・配置、人材育成、人事評価、組織設計 | 勤怠管理、給与計算、社会保険手続き、労働環境整備 |
| 視点 | 戦略的・長期的 | 実務的・日常的 |
| 対象 | 個人の能力やキャリア | 組織全体の労働環境 |

人事管理とは
人事管理とは、組織の目的達成に向けて人材を効果的に活用するための管理活動です。従業員一人ひとりの能力を最大限に引き出し、組織全体の生産性向上につなげることを目指します。
人事管理の主な業務内容は、以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人材採用 | 経営計画に沿って採用計画を立て、求人から内定までの流れを管理します。応募者データを分析し、優秀な人材を効率的に確保します。 |
| 人材育成 | 社内外の研修やOJTを計画し、従業員の能力開発やキャリア形成を支援します。 |
| 人事評価 | 業績や能力を客観的に評価し、処遇へ反映する制度を設計・運用します。評価基準の明確化や多面的な評価が重要です。 |
| 人材配置 | 適材適所の配置や異動を行い、組織目標と個人の成長の両立をはかります。 |
| モチベーション管理 | キャリア面談や意見収集を通じて、従業員の意欲向上と定着を促進します。 |
採用や育成、評価にかかわる業務は、どれも将来の組織をつくる大事な役割です。目の前のタスクに追われがちですが、一つひとつが人事戦略につながっているといえるでしょう。
労務管理とは
労務管理とは、従業員の労働条件や職場環境を適切に管理し、法令遵守と働きやすい環境づくりを実現するための業務です。勤怠管理や給与計算、福利厚生の管理など、従業員の労働に関する事柄を幅広く取り扱います。
労務管理の主な業務内容は、以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 労働契約の締結・管理 | 労働契約書や労働条件通知書を作成し、労働条件を明確にして適正な契約関係を築きます。 |
| 就業規則の作成・管理 | 就業規則を作成・届出し、従業員に周知徹底することが義務づけられています。 |
| 勤怠管理 | 出退勤や残業、有給休暇の状況を記録し、適正に労働時間を管理します。 |
| 給与計算 | 勤怠データをもとに正確な給与計算を行い、税金や社会保険料を処理します。 |
| 社会保険の手続き | 健康保険・厚生年金・雇用保険などの加入や脱退、保険料計算を行います。 |
| 労働環境の改善 | 安全衛生や職場環境を整備し、ハラスメント防止に努めます。 |
| メンタルヘルスケア | 心の健康に配慮し、必要に応じて相談やカウンセリングを提供します。 |
| 健康診断 | 法律に基づいて定期的に検査を実施し、必要な健康管理を行います。 |
日々の勤怠や手続きは地味に思えても、社員の安心と信頼を守る大切な業務です。正確で丁寧な運用が、職場の安定につながります。

【2025年最新版】の主な労務関連の法改正への対策法
2025年は、企業の人事労務担当者が把握しておきたい重要な法改正が相次いで施行されました。また、一部は今後施行を控えています。改正内容は、従業員の働き方や人事制度に大きな影響を与えるため、適切な対応が欠かせません。
ここでは、2025年の主な労務関連の改正内容と、企業が取りたい対策を紹介します。
- 育児・介護休業法の改正
- 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化
- 雇用保険法の改正
- 高年齢者雇用安定法関連の改正

育児・介護休業法の改正1.育児と仕事の両立支援
2025年の育児・介護休業法改正では、子育てと仕事の両立をより柔軟に支援する仕組みが整備されました。休暇対象の拡大や柔軟な働き方の義務化が主な改正内容です。
| 主な改正ポイント | ||
|---|---|---|
| 子の看護休暇の拡充 | 2025年4月1日から | ・「子の看護休暇」が「子の看護等休暇」に改称 ・対象が小学校3年生修了までに拡大・取得理由に入園(入学)式、卒園式や感染症による学級閉鎖を追加 |
| 柔軟な働き方の措置義務化 | 2025年10月1日から | ・3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に短時間勤務、フレックス、テレワークなど柔軟な働き方を選べる制度を提示して労働者がその中の一つを選択できることが義務化 |
企業としては、まず就業規則や育児休業規程を改定し、対象者拡大や新たな取得理由を反映する必要があります。業務の引継ぎ体制や代替要員の確保といった運用面での対応も検討しておくとよいでしょう。
また、柔軟な働き方の選択肢については、自社の業務特性にあわせて実現可能な方法を検討し、制度設計を進める必要があります。
具体的には企業は3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、5つの選択して講ずべき措置のなかから2つ以上の措置を選択して提示しなければなりません。
育児・介護休業法の改正2.介護と仕事の両立支援
2025年4月1日から、仕事と介護を両立しやすい環境を整えるための制度が強化されました。介護離職を防ぎ、従業員が安心して働き続けられる仕組みの整備が目的です。
| 主な改正ポイント |
|---|
| ・家族の介護が必要になった際、企業が個別に介護休業や両立支援制度を周知し、面談や書面で利用意向を確認することが義務化 ・介護休暇の対象範囲が拡大(勤続6か月未満の従業員も利用可能) ・労働者が介護中にテレワークを選べるようにすることを努力義務 ・介護離職防止のための雇用環境整備を講じなければならない ・介護離職防止のための個別の周知・意向確認等が義務化 |
企業は、就業規則や介護休業規程を改定し、勤続要件の撤廃やテレワークの利用可能性を反映する必要があります。さらに、介護が必要になった場合に個別に制度を説明し、面談で利用意向を確認するフローを整備しなければなりません。
相談窓口を設置し、社員が安心して相談できる体制づくりや、担当者向けの研修を進めることも大切です。
雇用保険法の改正
2025年の雇用保険法改正は、労働者の自発的なキャリア形成を後押しし、労働市場の流動性を高めることを目的としています。失業給付の制限緩和や新たな給付金の創設が主なポイントです。
| 主な改正ポイント | ||
|---|---|---|
| 失業給付の給付制限期間の短縮 | 2025年4月1日から | ・自己都合退職者の失業給付制限期間が従来の2か月から1か月に短縮 ・直近5年以内に3回以上自己都合退職を繰り返した場合は3か月間の給付制限期間が適用 |
| 教育訓練休暇給付金の新設 | 2025年10月1日から | ・自発的な能力開発を支援する新たな給付金が新設(教育訓練に専念するために無給の休暇を取得した場合の給付金) |
企業としては、制度改正の内容を従業員に正しく周知し、とくに教育訓練休暇給付金について適用条件や利用方法をわかりやすく説明することが大切です。
あわせて、人材育成計画の見直しや、リスキリングを後押しする仕組みづくりを進めると、従業員のキャリア開発支援や定着強化にもつながります。
高年齢者雇用安定法関連の改正
2025年4月1日から、高年齢者雇用安定法が改正され、希望する労働者に対して65歳までの雇用を確保する仕組みが強化されました。これにより、継続雇用の対象者を限定できる経過措置が終了し、企業はより広い範囲で雇用を保障する必要があります。
| 主な改正ポイント |
|---|
| ・65歳までの継続雇用制度について、経過措置が廃止。「希望者全員」を対象とすることが義務化 ・定年の65歳引き上げは義務ではなく、60歳定年を維持しつつ全員を65歳まで継続雇用でも可 ・高年齢雇用継続給付金の支給率を最大15%から10%に引き下げ(雇用保険法の改正) ・70歳までの就業機会確保は引き続き努力義務 |
企業は、就業規則や継続雇用制度の規程を改定し、対象者を限定していた場合は希望者全員に拡大する必要があります。
あわせて、給付金の縮小を踏まえた定年後の賃金制度の見直しや、高齢者の意欲を維持できる処遇の検討も重要です。70歳までの就業機会確保に向けた取り組みも、今後計画的に進めていくとよいでしょう。
参考:『高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~』厚生労働省
人事労務管理で注意したいポイント
ここまで、人事労務管理の基本や近年の法改正について解説してきました。人事労務管理では、実際に日々運用するうえで、どのようなことに気をつけるとよいのでしょうか。
人事労務管理を適切に進めるためには、注意したいポイントが3つあります。
- 就業規則を最適化する
- 法令・法律を遵守する
- 人材が定着する組織を目指す
従業員の権利を守りつつ、組織の生産性を支えるために、ポイントの内容を詳しく解説します。
就業規則を最適化する
就業規則は、公平な職場運営を維持する基本ルールです。法令を反映し、自社にあった内容へ更新することで、トラブル防止や従業員の安心につながります。
たとえばテレワーク導入時は、在宅勤務に関する規定を追加する必要があります。また、専門用語を避け、わかりやすい表現に整えることも大切です。
就業規則の見直しを定期的に行い、入社時のオリエンテーションや研修を通じて周知することで、規則の理解と遵守を促せるでしょう。
法令・法律を遵守する
人事労務管理では、労働基準法や労働安全衛生法など多様な法律を守ることが欠かせません。
法令を正しく運用することで、従業員の権利保護や企業の信頼維持につながります。
違反すれば罰則やイメージ低下のリスクが高まります。
たとえば、法改正のたびに就業規則を見直す、コンプライアンス研修を定期実施するなどの対応が必要です。
常に最新情報を把握し、法令遵守を徹底する体制を築きましょう。
人材が定着する組織を目指す
優秀な人材の定着は、業務効率化と組織の成長につながります。そのためにはキャリア支援や公正な評価、ワークライフバランスの推進が重要です。
たとえば、研修やジョブローテーションで学びの機会を増やし、成果に応じた報酬を明確にする必要があります。柔軟な勤務制度や有給取得の促進も欠かせません。
こうした取り組みを積み重ねることで、従業員のモチベーションと帰属意識を高められるでしょう。
人事労務管理システムを導入するメリット
人事労務管理は、法改正への対応など幅広い知識が求められます。煩雑で負担の大きい業務を効率的に進めるには、人事労務管理システムの活用が有効です。
人事労務管理システムを導入すれば、従業員情報の一元管理や申請手続きのデジタル化が可能です。ミスを防ぎ、生産性を高めることにもつながります。
ここでは、システム導入によって得られる3つのメリットを解説します。
- 社員情報を収集しやすくなる
- 人事部門と労務部門の業務連携がしやすい
- 各種申請手続きをWeb上で完結する

社員情報を収集しやすくなる
人事労務管理システムを導入すると、従業員が自分でマイナンバーや住所、家族情報などを直接入力できるため、情報収集の負担が大幅に軽減します。
入力されたデータは自動で社員名簿に反映され、住所や扶養変更もリアルタイムで更新される仕組みです。これにより、人事担当者が紙の書類を集めたり手作業で転記したりする必要がなくなり、つねに最新かつ正確な情報を簡単に収集・管理できるでしょう。
社員情報を収集しやすくなる
人事労務管理システムを導入することで、従業員の基本情報や勤怠記録、給与データなどを一元的に管理できるようになります。必要な情報に迅速にアクセスできるため、検索や更新作業が効率化されます。
たとえば、従業員の住所変更や家族構成の更新なども簡単に行えるため、紙ベースでの手続きに比べて手間が大幅に削減可能です。データが一箇所に集約されることで、情報漏洩リスクも低減します。法改正があった場合でも、システム上でデータを見直し適切な対応が可能となります。

人事部門と労務部門の業務連携がしやすい
人事労務管理システムは、人事業務と労務業務を一括で管理できるため、部門をまたいだ連携を強化できます。採用や勤怠、評価、給与、労働条件など幅広い情報を一元化することで、データ共有や確認作業がスムーズになり、生産性が向上します。
さらに、マネジメント層が必要とする情報もリアルタイムで抽出できるため、迅速な意思決定を支援します。企業ごとに必要な機能を柔軟に組み合わせて運用できるサービスも多く提供されているのが特長です。
各種申請手続きをWeb上で進められる
人事労務管理システムでは、社会保険や雇用保険などの手続きをWeb上で、進められる機能も備えています。紙書類を郵送する必要がなく、手間と時間の大幅な削減が可能です。
たとえば入社時には、雇用契約書をオンラインで締結でき、印刷が不要です。また、入社後の帳票作成や電子申請の義務化に含まれる手続きにも対応しており、多くの手続きをスムーズに処理できます。
人事労務管理システムの活用により、業務効率化が実現します。
人事労務管理システムで対応できる業務
ここまで人事労務管理システムの導入によるメリットを整理してきました。では実際に、どのような業務をシステムで効率化できるのでしょうか。ここでは、対応可能な主な業務を具体的に紹介します。
社会保険の手続き
社会保険の手続きは、書類作成や提出が複雑で負担が大きい業務です。
人事労務管理システムを使えば、入社・退職・扶養変更などの情報を一元管理し、必要書類を自動作成できます。
たとえば健康保険や厚生年金の資格取得届、被扶養者異動届もスムーズに作成が可能です。
電子申請機能を使えばe-GOV経由で簡単に提出でき、手作業や二重入力を防げます。
2020年以降、特定法人に電子申請が義務化された背景もあり、人事労務管理システム導入の重要性は高まっています。
参考:『2020年4⽉から特定の法人について電子申請が義務化されます。』厚生労働省
給与計算・給与明細発行業務
給与計算は正確性が求められる重要な業務です。人事労務管理システムを導入すれば、勤怠データと自動で連携できるサービスが多く、ミスの少ない計算ができ、各種控除や手当も漏れなく反映することができます。
給与明細は紙ではなくWebで配布できるため、印刷や配布の手間が減り、従業員もスマホなどからいつでも確認が可能です。
年末調整にまつわる業務
年末調整は法改正や控除内容の確認が複雑で、毎年負担になりがちです。
人事労務管理システムを利用すれば、最新の税制に自動で対応している場合が多く、従業員がWebで必要事項を入力するだけで年末調整の申告書が作成されます。
入力状況は一覧で確認でき、提出漏れの催促メールも自動で送信が可能です。データは給与情報と連携しており、還付金の計算もスムーズです。
勤怠管理
勤怠管理もシステム化の効果が大きい分野です。
勤怠管理機能を含むクラウド型人事労務管理システムなら、PCやスマホから打刻でき、勤務状況をリアルタイムで把握できます。テレワークやフレックスなど多様な働き方にも柔軟に対応できるでしょう。
残業時間の自動集計や36協定の上限管理もでき、企業の法令遵守をサポートしています。
有給休暇の管理
有給休暇の取得義務化により、厳密な管理が求められるようになりました。
休暇管理機能がある人事労務管理システムでは従業員ごとの付与・取得・残日数を自動計算し、一元管理できます。
従業員がWeb上で残日数を確認・申請でき、管理者は取得状況を簡単に把握できます。
法定の年5日取得義務や時間単位の休暇にも対応が可能です。正確な管理により、法令遵守と従業員の働きやすさが両立されるでしょう。
マイナンバー情報の管理
人事労務管理システムを活用することで、セキュリティ性が高く、効率的なマイナンバー管理が可能です。
マイナンバー制度の導入により、企業は従業員の番号情報を適切に管理しなければならなくなりました。
マイナンバー管理機能があるシステムなら、番号情報を暗号化して保管し、権限設定によりアクセスも制限できます。情報漏えいや不正利用のリスクを最小化できるでしょう。
管理されたマイナンバーは、源泉徴収票や社会保険手続きにも自動で反映されます。安全性と効率を両立する管理体制を構築できるでしょう。
台帳の作成
システムを使えば、人事労務管理で必要になる多くの台帳の電子保存が可能です。
従業員情報や勤怠・給与データをもとに、労働者名簿や賃金台帳、出勤簿(法定三帳簿)を自動で生成できます。
たとえば、手作業による転記や集計が不要になり、記載ミスや抜け漏れのリスクを大幅に減らせます。保存・検索も簡単になるため、監査対応や確認もスムーズです。
クラウド型人事労務管理システム|One人事[労務]
「One人事」は、社内に分散する人事と労務の情報を集約して管理し、業務効率化を助ける人事労務管理システムです。
労務・勤怠・給与・人事管理の領域をカバーしており、各種連携により、情報活用の高度化が期待できます。
人事労務管理システムを活用して、複雑になりがちな業務をシンプルにし、組織全体の生産性を高めてみませんか。
初期費用や操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門のスタッフが貴社の課題をお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、人事労務の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。人事労務をラクにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |