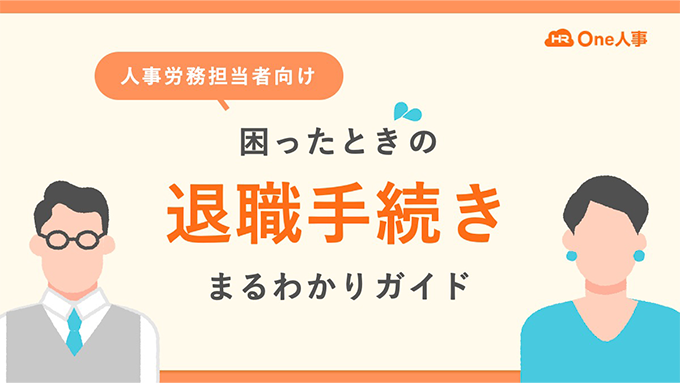退職時の社会保険手続きガイド【会社側・退職者側】必要書類と雇用保険も解説

退職時の社会保険手続きは、期限までに対応しないと退職者に不便をかける場合があります。企業の人事労務担当者が手続きを遅らせると、従業員が無保険状態になったり、予想外の立て替え払いが発生したりするため、すみやかに対応することが重要です。
本記事では、退職時に必要な社会保険・雇用保険の手続きを、会社側・退職者側それぞれの視点でわかりやすく解説 します。スケジュールや必要書類を確認し、社会保険手続きをスムーズに進めましょう。
退職手続きに不安がある方は、いつでも見返せるように以下の資料もぜひご活用ください。
 目次[表示]
目次[表示]
退職時に必要な社会保険の手続き|会社側の対応を解説
退職時には、健康保険や厚生年金など社会保険の手続きが欠かせません。雇用保険や住民税の処理、必要書類の作成も含めると、企業側が対応しなければならない手続きは多岐にわたり、準備に時間がかかります。とくに、社会保険の資格喪失手続きは提出期限が明確に決まっており、遅れると 退職者の保険加入に影響が出るため、早急に対応しましょう。
退職者に関する手続きは以下の記事でもご確認いただけます。
人事担当者が注意したい退職者の社会保険の手続き
社会保険や雇用保険に関する退職手続きには、期限の決まった届け出があります。手続きの遅れや不備があると、本来脱退しているのに社会保険料が徴収されたり、失業給付を受けられなくなったりします。
また、退職時は社会保険手続きだけでなく、退職証明書の発行が求められることもあります。労働者が請求した情報を正しく記載しなかった場合、労働基準法違反で罰金が科せられるため、適切な対応が必要です。
会社と退職者との間で労使トラブルを防ぐためにも、事前に手続きを確認し、期限内に進めましょう。
以下では、社会保険に関係する手続きを中心に、人事労務担当者が行う退職手続きや必要書類を退職前・退職日・退職後に分けて解説していきます。
社会保険の手続きをまとめて確認するには、チェックリスト付きの以下の資料もご活用ください。

退職日の2週間前から退職日までの手続き
まずは退職前に、残りの日数で対応しなければならない会社側の手続きを紹介します。
正式に退職の意思を確認したら、以下の項目について整理しましょう。
- 健康保険の任意継続の意思
- 住民税の徴収方法
- 退職証明書・離職証明書は必要かどうか
- 退職所得の受給に関する申告書への記入(退職金を支給する場合)
以上の項目を確認したら、退職者の求めに応じて、必要な書類を準備します。企業が発行にかかわる書類は以下のとおりです。
| 書類名 | 概要・用途 | 要不要 | |
|---|---|---|---|
| 転職先が決まっている | 決まっていない | ||
| 雇用保険被保険者離職票(ー1、2)(必要に応じ) | いわゆる「離職票」と呼ばれる書類。 | 不要 | 一般的に必要 (失業給付申請に必要) |
| 退職証明書(必要に応じ) | 退職の事実を証明する書類 | 転職先の求めに応じて必要 | 必要(離職票が発行される前に国民健康保険・国民年金の手続きをする際) |
| 源泉徴収票 | 所得税の支払い状況を示す書類 | 必要(転職先に提出必須) | 必要(本人の確定申告に必要) |
| 給与支払報告、特別徴収に係る給与所得者異動届出書 | 住民税の徴収手続きに必要な書類。 | 必要 | 必要 |
雇用保険被保険者離職票と退職証明書は、基本的に退職者の希望に応じて発行するものです。しかし、退職者が59歳以上の場合、高年齢雇用継続給付金の給付額を決めるため、離職票の交付は必須です。
源泉徴収票や給与支払報告などは、新しい職場が決まっていようとなかろうと、必ず準備します。
各書類を退職者へ渡すタイミングが遅くなってしまうとトラブルにつながるおそれがあるため、退職日が決まったら、早急に準備を進めましょう。
また、以上のような公的手続きのほかに、退職金を支給する場合は、控除額も含めて退職金を計算しなければなりません。退職金にかかる正確な税率を反映させるため、「退職所得申告」も提出してもらいましょう。
退職金の計算については以下の記事もご確認ください。
退職日当日の手続き
退職日当日は、会社が退職者へ渡すものと、退職者から回収するものがあります。
| 退職者へ渡すもの | |
|---|---|
| 年金手帳 | 転職先でも同じ物を使用するため、必ず本人に返却(年金手帳を会社が預かっている場合) |
| 雇用保険被保険者証 | 会社で保管しているケースが多い。雇用保険給付の手続きで必要になるため、必ず退職者に返却 |
| 退職者から回収するもの | |
|---|---|
| 健康保険被保険者証・資格確認書 | 保険証は退職日いっぱいまで有効であるため、退職者が退職日当日に使う場合には保険証または確認書のコピーを渡し、保険証本体は当日預かることもできる |
| 社員証、名刺 | 社名が入ったものは返却対象。取引先からもらった名刺も個人情報に該当するため、返却してもらう |
| 会社の備品 | パソコン、携帯、制服など。細かい備品については、退職者が「もらったもの」と思い込んでいるケースもあるため、返却物の一覧表を準備しておくのが望ましい |
| 事業にかかわる資料・データ | 過去のレポートやボツになった開発データなどを含め、事業に関連した資料について回収または破棄 |
企業側が行う書類の準備と同様に、退職者に返却してもらうものについても事前に伝えて準備してもらうことで、スムーズな退職手続きにつながります。
退職日の翌日から5日以内
退職日の翌日から5日以内に、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の脱退手続きを行う必要があります。
会社を管轄する年金事務所や事務センターに健康保険・厚生年金保険の「被保険者資格喪失届」を提出し、退職者から回収した健康保険証または資格確認書を添付します。
期限を過ぎても提出は可能で、罰則もありません。しかし、退職者が国民健康保険や転職先の社会保険に加入できなくなってしまう可能性があるため、期限内の対応が必要です。
社会保険の中でも雇用保険の脱退手続きは、退職日の翌日から10日以内が期限です。「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」をハローワークに提出します。
手続きがされないと離職票が交付されず、その間、退職者は失業給付の手続きができなくなってしまうため、早めに対応しましょう。
退職日の翌日から14日以内
退職者が退職後に国民健康保険への加入を希望している場合は、退職者本人が、退職日の翌日から14日以内に市区町村へ届け出る必要があります。その際「健康保険被保険者資格喪失確認通知書」の提出を求められます。
退職者の手元に「健康保険被保険者資格喪失確認通知書」がない場合は、各自治体のホームページで「健康保険資格喪失連絡票(社会保険喪失連絡票)」をダウンロードして利用できます。発行が間に合わない場合は案内すると親切です。
国民年金の手続きも同様に、退職日の翌日から14日以内に行う必要があるため、退職者に案内しましょう。
各種保険手続きの対応一覧は以下のとおりです。
| 社会保険の種類 | 手続きの場所 | 期日 | 必要書類 |
|---|---|---|---|
| 国民年金 | 市区役所・町村役場 | 退職日の翌日から14日以内 | ・退職日がわかる証明書(資格喪失証明書、退職証明書・離職票など) ・基礎年金番号がわかる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書など) ・本人確認書類 |
| 国民健康保険 | 市区役所・町村役場 | 退職日の翌日から14日以内 | ・健康保険の資格喪失証明書または退職証明書、離職票 ・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど) ・本人確認書類( |
| 失業保険 | ハローワーク | 退職日の翌日から1年以内 | ・雇用保険被保険者離職票(ー1、2) ・個人番号確認書類 ・本人確認書類 ・最近の写真2枚(正面上三分身、縦3.0×横2.4cm) ・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード |
退職者が期限内に手続きを完了できるよう、早めに案内をして必要な書類を渡してあげると、円滑に進められるでしょう。
退職時に必要な社会保険の手続き|本人側の対応を解説
続いて今度は退職者本人に向けて、必要な社会保険の手続きを解説していきます。企業の人事労務担当者も、退職者から質問があった場合に、正確に答えられるよう基礎を理解しておきましょう。
労働者が注意すべき退職時の社会保険の手続きと注意点
退職時の社会保険の手続きにおいて退職者がとくに注意したいのは、退職後に入る保険によって手続きの方法や期限が異なることです。
現在加入している保険を継続するのか、国民健康保険に個人で加入するのか、家族の扶養に入るのかで、手続きの窓口や申請期限が変わります。
また、雇用保険(失業保険)を申請する場合は、離職証明書を受け取ったらすみやかに手続きを進めます。手続きの方法や必要書類がわからない場合は、申請先に直接質問するのがおすすめです。
退職日の1か月前から退職日まで
退職する従業員は退職するまでに、どの保険に加入するかを決める必要があります。
退職後は以下の3つの選択肢があります。
- 現在加入している保険を継続する(任意継続制度)
- 国民健康保険や国民年金に個人で加入する
- 家族の扶養に入る
それぞれの選択肢における手続き方法は以下のとおりです。
| 退職後の保険の選択肢 | 申請先 | 申請期限 |
|---|---|---|
| 任意継続制度 | 継続する健康保険組合 | 退職の翌日から20日以内 |
| 国民健康保険・国民年金への加入 | 居住区域の市区町村役場 | 退職日の翌日から14日以内 |
| 扶養届の申請 | ・(国民健康保険の扶養届)居住区域の年金事務所または事務センター ・(社会保険の扶養届)被保険者の勤務先を経由して日本年金機構や健康保険組合 | 退職日の翌日から5日以内 |
家族の扶養に入る場合は退職日の翌日から5日以内に手続きしなければなりません。。期限が短いため、前もって手続き方法や必要書類を確認しておくのがよいでしょう。
退職日当日
退職日の当日は、会社から支給されているものや、業務にかかわる資料・データなどを返却します。
同時に保険証も会社に返却しなければなりません。ただし、保険証は退職日当日まで有効のため、当日に病院を利用する予定がある場合はコピーを取っておくと安心です。
そして会社からは、以下の書類を受け取ります。
- 雇用保険被保険者証(雇用保険に加入している証明)
- 雇用保険被保険者離職票(ー1、2)(失業保険を受給するために必要)
- (離職票を交付しない場合)雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失証明書(国民健康保険に切り替える場合に必要)
- 源泉徴収票(自分で確定申告をするときに必要。後日発行される場合もある)
- 年金手帳
以上の書類は大切に保管し、必要なときがきたら、すぐに提出できるよう準備しておきましょう。
退職日から14日以内
退職後に国民健康保険へ加入する場合、手続きの期限は、退職日の翌日から14日以内です。退職者が住む地域の市役所や区役所にある健康保険の窓口で申請します。
社会保険料は市役所や区役所などで事前に教えてもらえるため、退職前にあらかじめ確認しておくことも可能です。前年の所得に応じて決まります。
| 必要書類 |
|---|
| 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、通帳、印鑑、マイナンバー |
手続きの遅れを防ぐために、余裕をもって申請を進めましょう。
退職日から20日以内
退職前に加入していた健康保険に最大2年間継続加入できる「任意継続制度」を利用する場合は、退職日の翌日から20日以内に手続きする必要があります。社会保険手続きは期限を過ぎても遡及できるものがほとんどですが、任意継続の加入申し出は期限を過ぎると加入できないので注意しましょう。
任意継続制度を利用するには、退職する前に2か月以上健康保険の被保険者であることが要件です。
期限までに保険料を納めなければ任意継続の資格を喪失してしまうため、支払い漏れがないようにしなければなりません。
手続きは、継続する健康保険組合の手続き方法に沿って行います。
| 必要書類 |
|---|
| 健康保険の任意継続被保険者資格取得申出書、本人確認書類、印鑑 |
任意継続制度は一度資格を喪失すると再加入ができないため、継続を希望する場合は期限内の手続きを確実に済ませましょう。
会社を辞めたあとの健康保険はどうなる?
ここまで紹介したように、従業員が退職したあとの健康保険には「任意継続制度」「国民健康保険」「家族の扶養に入る」と3つの選択肢があります。
退職後の健康保険は、状況によって選べる選択肢が異なります。ここからは、すぐに転職する場合やフリーランスになる場合など、本人の状況に応じた対応や注意点を解説します。
すぐに転職する場合(空白期間がほとんどない)
退職した従業員がすぐに新しい職場へ転職する場合は、扶養している家族の分も含め、健康保険証を会社に返却しなければなりません。
転職先の健康保険に加入するには「健康保険資格喪失証明書」が必要になる場合があります。
転職までに期間がある場合
すぐに転職する場合と同様、扶養している家族の分も含め、健康保険証を会社に返却します。
その後「現在加入している保険を継続する(任意継続制度)」「国民年金や国民健康保険に個人で加入する」「家族の扶養に入る」の3つから、退職後の保険を選びます。
フリーランスになる場合
フリーランスになる場合も、「任意継続」「国民健康保険」「家族の扶養に入る」の3つから加入保険を検討します。
任意継続には、扶養家族の保険料を払わなくてよいというメリットがあります。扶養家族の年収が130万円未満など、いくつかの条件があるので、扶養家族が多いなら、任意継続を選択したほうがお得に感じることもあるでしょう。
退職前に加盟していた健康保険組合の福利厚生が、引き続き受けられるのもメリットといえます。家族の扶養に入る以外は自分で保険料を全額(※)支払う必要があるため、フリーランスの報酬見込みを考慮し、可能な限り負担を抑えられる保険を選択するのがポイントです。
(※)在職中は、健康保険料の半分を会社が負担していましたが、任意継続は保険料を全額負担しなければなりません。
失業保険を受給する場合
すぐに転職せず、失業保険の給付を受ける場合の対応を紹介します。
雇用保険(失業保険)の申請は、退職の翌々日から10日以内が期限です。
退職後にあわてないよう、在職中に「雇用保険被保険者証」の有無を確認しましょう。また、会社がハローワークに提出する「離職証明書」は、離職前に退職者本人が氏名を記載するため、離職理由などの記載内容についても確認する必要があります。
退職後に「雇用保険被保険者離職票」が届いたら、住居を管轄するハローワークで「求職の申し込み」を行ったあとに提出します。
雇用保険における失業給付の要件は、求職の申し込みを行い、就職の意思と能力があるにもかかわらず、職に就けない状態」であることです。過去2年間に通算12か月以上の保険加入期間が必要です。
ただし例外もあり、離職理由によっても条件は異なるため、提出書類とあわせて、詳細はハローワークの公式サイトで確認しましょう。
また、万一会社から離職票が交付されなかったり、事業主が行方不明であったりする場合は、住居地を管轄するハローワークに問い合わせる必要があります。
親族の扶養に入る場合
転職の予定もなく、親族の扶養に入る場合は、扶養者の勤め先へ申告しなければなりません。
期限は退職の翌日から原則として5日以内と短いので、早めに手続きを進めましょう。
扶養に入るには要件があるため、あわせて確認しましょう。
- 被保険者により生計を維持されていること
- 年収が130万円未満、かつ同居の場合は被保険者の年収の2分の1未満であること。別居の場合は、被保険者からの仕送り額未満であること
- 配偶者、子、孫、兄弟姉妹、父母、祖父母などの直系尊属、同一世帯の3親等内の親族
| 必要書類 |
|---|
| 健康保険被扶養者(異動)届や、年収要件を確認する書類など ※扶養に入る人の状況によって必要書類が異なるため、健康保険組合に確認が必要 |
健康保険によっては、失業保険の給付を受けていると要件から外れてしまうケースがあるため、家族が加入している健康保険組合に問い合わせる必要があります。
万一、失業保険の受給によって扶養に入れない場合は、国民健康保険に加入するか、健康保険の任意継続を選択することになります。
海外で働く場合
退職後もしばらく国内にいる場合は、一時的に国民健康保険に加入する、任意継続を選択する、または家族の扶養に入るという選択があります。
海外での勤務開始まで期間が空く場合は、保険の空白期間ができないよう注意が必要です。
また、海外の就職先で社会保険に加入できるか、現地の医療制度の内容を確認しておくことが重要です。 会社の福利厚生に健康保険が含まれているか、民間の海外旅行保険や現地の健康保険制度への加入が必要かを事前に把握しましょう。
国内企業に就職して国内企業から給与の支払を受け海外に赴任する場合は、日本の社会保険の適用を受けます。
扶養に入らない場合は、国内にいる間の保険料負担を抑えるため、国民健康保険と任意継続保険の保険料を比較して選ぶのがおすすめです。
従業員の退職手続き一覧とチェックリスト【人事労務担当者向け】
ここまでの社会保険に関する退職手続きを整理するために、人事労務担当者向けのチェックリストを紹介します。
| 退職手続きチェックリスト |
|---|
| ◻︎ 退職届の受理 |
| ◻︎ 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格喪失 |
| ◻︎ 雇用保険の資格喪失 |
| ◻︎ 退職時誓約書の締結 |
| ◻︎ 退職金の支給手続き |
| ◻︎ 所得税や住民税に関する手続き |
退職手続きだけでなく入社手続きもあわせて確認するには以下の記事もご確認ください。
退職時の対応で注意したい3つの事例
退職手続きでは社会保険以外でも必要な対応があります。退職手続きで注意したい事例として「財形貯蓄」「社内融資制度」「外国人の退職」における3つの注意点を解説します。
退職者が財形貯蓄をしている場合の注意点
「財形貯蓄」とは、従業員の財産形成を支援する福利厚生です。「一般財形貯蓄」「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」の3種類があります。
転職先に財形貯蓄の制度がある場合は、退職から2年以内に手続きすれば移換が可能です。転職先に財形貯蓄制度がない場合、退職後一定期間が経過すると課税扱いとなります。すぐに再就職しない場合、退職から2年以内であれば、もとの金融機関に保管できます。
転職して2年以内に積み立てを再開しない場合は、非課税の優遇措置がなくなり、課税扱いとなるため覚えておきましょう。
退職者が社内融資制度を利用している場合の注意点
退職者が社内融資制度を利用している場合は、返済期間や返済残額を確認します。
一般的に、退職すると社内融資の優遇金利が適用されなくなるため、金利の変動や繰り上げ返済の必要があるかを確認しましょう。社内規定によっては、 最終給与や退職金から差し引くことができるかもしれません。規定にしたがって、残金の返済を求めましょう。
外国人の従業員が退職する場合の手続きの注意点
外国人の従業員が退職する場合、就労ビザの期限や、在留資格の更新・変更手続きに影響が出るため、とくに注意が必要です。
企業はハローワークに「外国人雇用状況届出書」を提出する義務があり、対応が漏れると法律違反となる可能性があります。
本来であれば退職証明書の発行は任意ですが、外国籍の退職者の場合、在留資格の変更・更新、就労資格証明書の交付申請に必要であるため、必ず準備します。
日本に長期滞在する予定のない外国人従業員は、年金の脱退一時金制度を案内することが望ましいでしょう。
退職時の届け出書類の一覧
退職時には、会社と退職者の双方が適切に書類を準備し、手続きを進めることが重要です。以下に、退職時に必要な書類をまとめましたので、漏れがないか最後に確認しましょう。
| 退職者に提出してもらう書類 | 注意 |
|---|---|
| 離職証明書の記載内容に関する確認書 | ※雇用保険受給の場合 |
| 秘密保持誓約書 | ※退職時 |
| 健康保険被保険者証(保険証) | ※扶養する家族の分も含む |
| 退職所得の受給に関する申告書 | ※退職手当を支給する場合 |
| 会社が退職者に渡す書類 | 注意 |
|---|---|
| 雇用保険被保険者証(雇用保険に加入している証明) | ー |
| 用保険被保険者離職票(ー1、2) | ※失業保険を受給するために必要 |
| 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用) | ※離職票を交付しない場合 |
| 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失証明書 | ※国民健康保険に切り替える場合に必要 |
| 源泉徴収票 | ※自分で確定申告をする時に必要。後日発行になる場合もある |
お互いに書類の受け渡しが遅れると、退職後の手続きに支障をきたす可能性があります。スムーズに進めるためにも、事前に準備し、必要に応じて早めに対応しましょう。
まとめ
退職手続きは、事前に流れを把握しておけば、あわてることなくスムーズに進められます。
会社は、社会保険や雇用保険の資格喪失手続きを期限内に進め、必要な書類を準備する責任があります。手続きが遅れると、退職者が次の保険加入や給付を受ける際に影響が出るため計画的に進めるのがポイントです。
一方で、退職者も「保険の切り替えはどうするか?」「必要な書類はすべて受け取ったか?」といったポイントを整理し、手続きを確実に進めることが大切です。
退職後に「手続きを忘れていた」と焦らないよう、会社側も退職者側も、余裕をもって準備を進めましょう。
社会保険に関する退職手続きを効率化|One人事[労務]
One人事[労務]は、従業員の退職手続きの効率化を支援する労務管理システムです。社会保険の喪失手続きの電子申請などペーパーレス化を助け、担当者の負担を軽減します。
One人事[給与]の初期費用や気になる操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門スタッフが、貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、給与計算の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。給与計算をシンプルにして「本来やりたい業務」に集中したい企業は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |