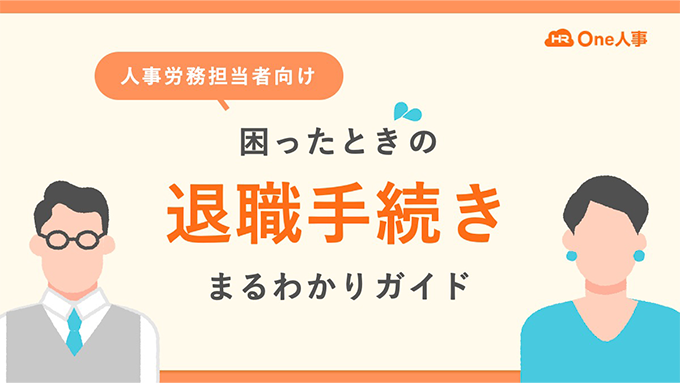離職票の必要書類は退職日の翌々日から10日以内に提出しないと罰則の可能性も! 発行の流れや注意点を解説

退職者が出たタイミングで、企業はさまざまな書類を発行する必要があります。代表的な書類の一つが「離職票」です。
離職票自体に期限はないものの、発行には事実上の提出期限が設けられています。離職票の発行申請に必要な離職証明書に「退職日の翌々日から10日以内」という提出期限があるのです。提出期限を超過した企業には、罰則が科せられる恐れもあるため、担当者はとくに注意しなければなりません。
そこで本記事では、離職票の提出期限を過ぎた場合の罰則や従業員の退職が決まったあとの手続き、退職手続き関連でよくあるトラブルについて解説します。従業員が退職するときの手続きについて知りたい方は、ぜひお役立てください。
 目次[表示]
目次[表示]
「雇用保険被保険者離職票(離職票)」とは
そもそも離職票とはどのような書類なのでしょうか。
離職票は退職時に交付する書類
離職票の正式名称は「雇用保険被保険者離職票」です。雇用保険の失業手当を受給申請するために必要な書類であり、所属する企業を介して手続きを行い、ハローワークから交付されます。
離職票は2種類で構成される
離職票は「離職票−1」と「離職票−2」という2種類の書類で構成されています。
| 離職票−1 | 退職者の氏名や離職年月日、事業所名や、事業所番号などが印字された書類 |
|---|---|
| 離職票−2 | 在籍中の賃金や退職理由などが記載された書類 |
従業員の退職が決まったあとの手続き
従業員が退職する際は、離職票の交付以外にも保険や税金関連の各種手続きが必要です。
退職者に離職票を交付
退職者が希望する場合は、離職票の発行手続きを進めます。
離職票は、雇用保険の失業手当の受給申請に必要な書類です。退職者からの要望に応じる形で、企業を介してハローワークから交付されます。離職票の発行に必要な書類は「離職証明書」と「雇用保険被保険者資格喪失届」の2種類です。
なお、離職証明書を作成する際は、記載内容に間違いがないか退職者本人にも確認してもらい、署名を受けなければなりません。上記の書類を提出すると、ハローワークから企業に離職票が送付されます。ハローワークから離職票が到着したら、退職者の自宅まで郵送するか、会社まで直接受け取りにきてもらいましょう。
離職票以外に渡す書類など
従業員が退職する際は、離職票以外にも渡す書類があります。
| 退職時に渡すもの | ・退職証明書 ・年金手帳 ・雇用保険被保険者証 |
|---|---|
| 退職後に渡すもの | ・離職票 ・源泉徴収票 ・健康保険被保険者資格喪失確認通知書 |
なお、労働基準法第22条により「退職者の希望に応じて、企業は退職証明書を遅滞なく交付しなければならない」と定められています。また、退職理由など、退職者本人が望まない項目の記入は禁止されている点に注意しましょう。
保険・税金などの手続き
従業員の退職時には、保険や税金関連の手続きも必要です。
健康保険・厚生年金保険
「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届」と「健康保険証」を所轄の年金事務所へ提出します。提出期限は、退職日の翌日から5日以内です。共済組合や健康保険組合の健康保険に加入している場合は、別途手続きを行います。
住民税・所得税
住民税の手続きには「給与支払報告書」と「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」が必要です。
退職日の翌月10日までに、上記の書類を退職者が居住する自治体に提出しましょう。なお、退職者の再就職先が決まっている場合は、提出書類を本人に直接渡します。
一方、所得税の手続きには「源泉徴収票」が必要です。退職日から1か月以内に、退職者本人に源泉徴収票を渡します。住民税、所得税の手続きはそれぞれ必要書類や提出期限が異なるため、混同しないように注意しましょう。
| 必要書類 | 提出先 | 提出期限 | |
|---|---|---|---|
| 住民税 | 給与支払報告書 | 退職者が居住する自治体 ※再就職先が決まっている場合は退職者本人 | 退職日の翌月10日まで |
| 特別徴収に係る給与所得者異動届出書 | |||
| 所得税 | 源泉徴収票 | 退職者本人 | 退職日から1か月以内 |
退職日の翌々日から10日以内の期限を守らないと罰則の可能性も
雇用保険法により、離職票の発行は企業の義務として定められています。離職票自体に期限がないものの、離職票の申請に必要な書類に事実上の申請期限があり、正当な理由なく超過すると罰則が科せられる恐れもあるため注意が必要です。
離職後はハローワークへ届け出る
雇用保険法施行規則7条において「企業は、従業員が雇用保険の資格を喪失した日の翌日から10日以内に、所轄のハローワークに離職証明書と雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなくてはならない」と定められています。
雇用保険の資格を喪失するのは退職日の翌日なので、離職証明書の提出期限の起算日は「退職日の翌々日」ということです。
参考:『資格喪失届・離職証明書の交付に必要な書類』厚生労働省
申請期限を超過してしまうと雇用保険法施行規則7条の違反となり、罰則が科せられることもあるため注意しましょう。たとえば、下記のようなケースは雇用保険法第83条により、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
- 正当な理由なく離職票の発行手続きをしない
- 虚偽の届け出をした
- 離職票発行の依頼を、正当な理由なく拒否した
参考:『雇用保険法施行規則』e-Gov法令検索
参考:『雇用保険法』e-Gov法令検索
離職票の交付義務がある場合
離職票の発行・交付は、雇用保険法第76条3項に定められた企業の義務です。ただし、退職者の年齢が59歳未満かつ離職票を希望しない場合は、離職票を発行する必要はありません。
一方、退職者の年齢が59歳以上の場合は高年齢雇用継続給付の手続きに使用するため、本人の希望にかかわらず離職票の発行・交付が必要です。
| 高年齢雇用継続給付とは |
|---|
| ・60歳以上65歳未満の従業員が対象 ・60歳到達時点とそれ以降での給与の差を埋めるために支給される給付金 ※現在の収入が60歳到達時点の75%未満である場合に支給 |
離職時に回収すべきもの
従業員が退職する際にはさまざまな手続きが必要なだけでなく、従業員から回収すべきものもあります。
退職者から回収する書類・物品
従業員が退職する際には、下記の書類や物品を忘れずに回収しましょう。
- 健康保険被保険者証(本人、被扶養者分)
- 社章・社員証本人
- 取引先の名刺
- 制服・作業着
- 会社から貸与していた情報端末
- 業務・取引先の機密情報を記載した書類
健康保険被保険者証は、健康保険の資格喪失届を提出するために必要です。なお、退職の際に退職金が発生する場合は「退職所得の受給に関する申告書」をあわせて受け取りましょう。
離職時に起こりやすいトラブル
従業員の離職に関する手続きには、さまざまなトラブルが起こる可能性があります。リスクを事前に把握し、トラブルを未然に回避しましょう。
退職者の個人情報の流出
退職者の個人情報を理由なく保存していると、漏えいなどのリスクが高まるため注意が必要です。
労働基準法第109条では、退職者に関する書類について「使用者は、労働者名簿、賃金台帳および雇い入れ、解雇、災害補償、賃金、その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければならない」と定められています。
理由のない個人情報の保存はトラブルの元になるため、保存期間が過ぎた情報は適切かつ迅速に処理しましょう。なお、2020年4月の法改正により保存期間が3年から5年に延長されましたが、当面の間は経過措置として据え置きで3年が適用されます。
書類の法定保存期間の例
従業員の個人情報のなかで、とりわけ取り扱いに注意が必要なのがマイナンバー(特定個人情報)です。従業員のマイナンバーが記載された書類の保管に関してはさまざまな規定があり、場合によっては罰則がともなうこともあります。
参考:『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律』e-Gov法令検索
従業員のマイナンバーが記載される書類には保存期間が定められており、それぞれ以下のとおりです。
| 保存期間7年 |
|---|
| ・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ・給与所得者の保険料控除申告書 など |
| 保存期間4年 |
|---|
| ・離職票など雇用保険の被保険者に関する書類(雇用保険法施行規則第143条) |
| 保存期間2年 |
|---|
| ・雇用保険に関する書類(雇用保険法施行規則第143条) ・健康保険に関する書類(健康保険法施行規則34条) ・厚生年金保険に関する書類(厚生年金保険法施行規則第28条) |
参考:『No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間』国税庁
参考:『雇用保険法施行規則』e-Gov法令検索
参考:『健康保険法施行規則』e-Gov法令検索
参考:『厚生年金保険法施行規則』e-Gov法令検索
離職手続きのミス
離職票の交付が遅れると、退職者は失業手当の受給申請ができません。離職票の発行を申請する退職者は、次の就職先が決まっていない場合がほとんどです。
万が一、失業手当の受給が遅れてしまうと、退職後の生活設計に影響を及ぼしてしまう可能性があります。従業員が退職する際は、速やかに事務手続きに取りかかり、遅れやミスがないよう細心の注意を払いましょう。
離職票の再発行の方法
離職票の申請には事実上の提出期限があります。では、退職者から「離職票を紛失してしまった」と相談を受けた場合、再発行はできるのでしょうか。
離職票は再発行できる
結論からいうと、とくに発行回数の制限はなく、退職者が希望すれば何度でも再発行が可能です。
退職者から離職票の再発行を希望された場合は「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」を提出します。なお「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」は、ハローワークのホームページからダウンロード可能です。
また、紙の書類を使った申請だけでなく『e-Gov電子申請』からのオンライン申請にも対応しています。初回の発行時とは異なり、退職者自身が再発行を申請することもできます。
企業を介した場合と比べてスピーディーな発行が可能なため、退職者が急いでいる様子なら自分で申請可能なことを案内してあげるのがおすすめです。
離職票と似た書類
離職票と間違われやすい書類に「離職証明書」や「退職証明書」があります。それぞれの役割や記載内容の違いを詳しく解説しましょう。
離職票と離職証明書の違い
離職証明書は離職票を発行するためにハローワークに提出する書類で、正式名称を「雇用保険被保険者離職証明書」といいます。提出した離職証明書のうち、本人控えとして返却されたものが「雇用保険被保険者離職票−2」です。
離職証明書の記載項目
離職証明書には多くの記載項目があり、なかでももっとも重要なのが「離職理由」です。離職理由は失業手当の給付日数に影響を及ぼすため、退職者本人に内容を確認してもらい、最後に署名を受ける必要があります。
参考:『雇用保険被保険者離職証明書についての注意』厚生労働省
離職票と退職証明書の違い
退職証明書は、当該従業員が間違いなく退職したことを証明する書類です。離職票とは異なり公的な文書ではなく、退職後の手続きにおける必須書類ではありません。
ただし、退職証明書の発行は、労働基準法第22条で定められた企業の義務です。退職日から2年間は、企業は退職者の求めに応じて何度でも退職証明書を発行する必要があります。
退職証明書の記載項目
退職証明書は公的な文書ではないため決まったフォーマットなどはないものの、通常は在籍中の業務の種類や役職、賃金や退職理由といった項目を記載するのが一般的です。なお、労働基準法第22条3項では「労働者の請求しない事項を記入してはならない」と定められています。
退職証明書の使い方
退職証明書は公的な文書ではありませんが、公的手続きの代替書類として使用できる場合があります。代表的なのが、国民健康保険への加入手続きや国民年金の種別変更手続きです。
たとえば、会社を辞めて国民年金の種別変更をする場合、退職証明書を離職票の代わりに使用できます。また、前職の役職や賃金、退職理由などを確認するため、転職先の企業から提出を求められるケースもあります。
離職票の手続きは期限内に行いましょう
退職者から離職票の発行を求められた場合は、退職日の翌々日から10日以内に必要書類を提出しなければなりません。離職票の発行は雇用保険法に定められた企業の義務であり、正当な理由なく手続きが遅れた場合は罰則が科せられる恐れもあります。
従業員が退職する際は、さまざまな手続きが必要です。それぞれの提出期限を超過しないよう、速やかに手続きに取りかかりましょう。従業員の退職に関する業務負担は、決して軽くはないもの。
人事労務担当者の負担を軽減するなら「One人事」がおすすめです。
「One人事」は人事労務をワンストップで支えるクラウドサービスです。人事労務情報の集約からペーパーレス化まで、一気通貫でご支援いたします。電子申請や年末調整、マイナンバー管理など幅広い業務の効率化を助け、担当者の手間を軽減。費用や気になる使い心地について、お気軽にご相談いただけますので、まずは当サイトよりお問い合わせください。
当サイトでは、サービス紹介資料はもちろん、無料のお役立ち資料をダウンロードいただけます。業務効率化のヒントに、こちらもお気軽にお申し込みください。