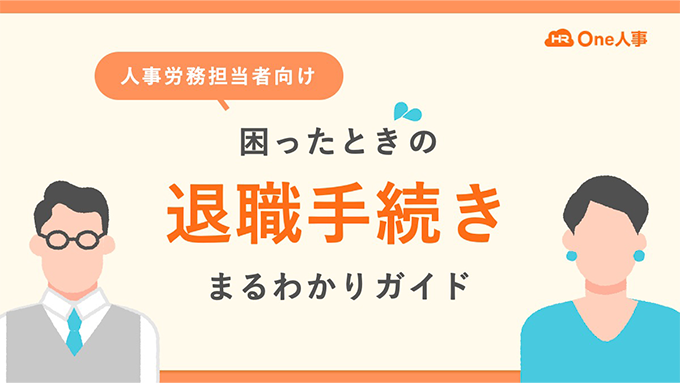定年退職手続きの流れ【会社側】回収物のチェックリストや効率化の方法も紹介

従業員が定年退職を迎える際の手続きは、つまずくことなく進められていますか。定年時の退職手続きには、社会保険や税金の手続き、貸与物の回収、システムのアクセス権削除など、通常の退職と共通する業務が多くあります。しかし、定年退職ならではの注意点 もおさえておきたいところです。
本記事では、実務担当者に向けて定年退職における手続きの流れを整理し、効率化の方法も解説します。回収・配付物のチェックリストも用意しているので、長年勤務した社員を気持ちよく送り出すために、ぜひご活用ください。
▼退職手続きに全般に不安がある方は、いつでも見返せるように、以下の資料もぜひご活用ください。
 目次[表示]
目次[表示]
定年退職時に必要な手続きの流れ
定年退職時も通常の退職と同様、法定期限内に、社会保険や税金など公的手続きを漏れなく完了させる必要があります。以下、主要な3つの公的手続きの流れを解説します。
- 健康保険・厚生年金保険の喪失手続き
- 雇用保険の資格喪失手続き
- 住民税の支払い変更手続き
1.健康保険・厚生年金保険の資格喪失手続き
従業員が定年退職を迎えるときは、退職日の翌日から5日以内に、手続きを完了しなければなりません。具体的には「被保険者資格喪失届」を日本年金機構や健康保険組合へ提出します。
加入する保険によって運営母体は異なり、提出先が以下の2つに分かれます。
| 加入している保険 | 提出先 |
|---|---|
| 協会けんぽの場合 | 年金事務所 |
| 健康保険組合の場合 | 健康保険組合 |
また、定年退職の前に以下の社会保険関係の書類回収が必要です。
| 回収区分 | 対象書類 |
|---|---|
| 必ず回収 | 健康保険被保険者証(扶養者の分も含む) |
| 発行されている場合のみ回収 | ・高齢受給者証 ・健康保険特定疾病療養受給者証 ・健康保険限度額適用 ・標準負担額減額認定証 ・遠隔地被保険者証 |
健康保険証がない場合は「健康保険被保険者証減失届」を、督促をしても提出がない場合は「健康保険被保険者証回収不能届」を添付しましょう。
高齢受給者証は、70歳以上の健康保険加入者が医療費の自己負担割合を示すための証明書です。定年退職時に健康保険の資格喪失とともに回収が必要となります。70歳以上の人に交付されるため、定年退職者ならではの回収書類といえるでしょう。
手続きが完了したら、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書」が企業に送付されるため、控えとして保管します。
▼社会保険の手続きをまとめて確認するには、チェックリスト付きの以下の資料もご活用ください。

資格喪失後の健康保険の加入手続き
定年退職した従業員は、健康保険の加入を「健康保険任意継続被保険者」「国民健康保険」「家族の被扶養者」の3つから選択し、各自手続きを行います。
| 保険の種類 | 概要 | 注意点 |
|---|---|---|
| 健康保険任意継続 | 定年退職前と同じ保険に継続加入 | ・2年間限定 ・保険料は在職中と変わらない ・定年退職日の翌日から20日以内 |
| 国民健康保険 | 居住地の市区町村で加入 | ・収入に応じた保険料 ・加入手続きは定年退職後14日以内 |
| 家族の被扶養者 | 配偶者等の健康保険に加入 | ・扶養条件あり ・扶養者の勤務先で手続き |
健康保険任意継続は、定年退職前の健康保険に継続して加入する制度です。
▼任意継続のメリットや概要は以下の記事でもご確認いただけます。
定年退職者が健康保険の任意継続を希望した場合、人事労務担当者は「健康保険任意継続被保険者資格取得届」を渡す必要があります。
国民健康保険は、住所地の市区町村で加入する制度です。
▼国民健康保険の切り替え手続きは以下の記事でもご確認いただけます。
扶養条件を満たせば、家族の被扶養者になることも可能です。扶養に入ると本人の社会保険料の負担はありません。手続きは扶養する家族の勤務先で行います。
2.雇用保険の資格喪失手続き
雇用保険の資格喪失届 も、定年退職時の手続きとして必要です。定年退職者の失業給付受給に直接かかわるため、期限内の確実に提出しましょう。
会社は定年退職日の翌日から10日以内に、ハローワークへ以下の書類を提出しなければなりません。
- 雇用保険被保険者資格喪失届
- 雇用保険被保険者離職証明書
賃金台帳または給与明細書、出勤簿、離職理由を確認できる書類のコピーなども添付資料として準備します
無事に手続きが受理されたあと、以下の書類を定年退職者へ渡します。
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
- 雇用保険被保険者離職票-1
- 雇用保険被保険者離職票-2
失業給付を受給する際に必要となるため、期限内に済ませられるよう、確実に本人へ渡すことが重要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出期限 | 退職日の翌日から10日以内 |
| 提出先 | 事業所を管轄するハローワーク |
| 提出方法 | ・ハローワーク窓口への直接提出 ・郵送による提出(特定記録や簡易書留推奨) ・e-Govを利用した電子申請 |
ハローワークでの手続きが完了すると、事業主保管用として雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)と雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)が発行されます。書類は事業所で適切に保管しましょう。
提出が遅れると定年退職者の失業給付にも支障が出ます。
とくに59歳以上の定年退職者は、高年齢雇用継続給付の手続きのため、離職票の発行が必須です。
3.住民税の手続き
定年時の退職手続きでは、住民税においても通常の退職と同様の手続きが必要です。
退職後は、給与からの特別徴収ではなく、普通徴収に切り替えなければなりません。
人事労務担当者は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を退職日の翌月10日までに、定年退職者の住所地の市区町村へ提出します。
定年退職の時期によって切り替え方法が異なるため、以下の一覧を参考にしましょう。
| 退職時期 | 徴収方法 |
|---|---|
| 1月1日~4月30日 | 残額を一括徴収または普通徴収に切替 |
| 5月1日~5月31日 | 6月分まで特別徴収、7月以降は普通徴収 |
| 6月1日~12月31日 | 退職月分まで特別徴収、翌月以降は普通徴収 |
手続きを忘れると、滞納の催促状が会社に送付される可能性があります。さらに未徴収分は定年退職者が一括で納付しなければならず、本人にとって大きな負担となるので、すみやかに対応しましょう。
とくに、退職者が定年後に転居する場合は注意が必要です。転出前後の市区町村それぞれに異動届出書を提出しないと、現年度分と新年度分の特別徴収予定が適切に処理されず、支払いに混乱が生じるからです。
住民税の徴収方法など基礎をおさらいするには以下の記事もご確認ください。
定年退職の手続きにおける回収・配付物【チェックリスト】
定年退職の手続きでは、通常の退職と同様に、書類や物品の回収・配付を確実に行う必要があります。
とくに、長年にわたって勤務していた従業員の場合、貸与物の種類が多かったり、特定の手続きが必要になったりするケースもあるため、より慎重に対応するとよいでしょう。
回収・配付漏れを防ぐため、以下のチェックリストを活用した管理をおすすめします。
定年退職者から回収するもの
定年退職者から回収する書類などのチェックリストは以下のとおりです。
| 回収物 | 用途・注意点 | |
|---|---|---|
| □ | 健康保険被保険者証 | 扶養家族分も含む |
| □ | 社員証・入退出カード | 最終出勤日までに回収 |
| □ | 名刺 | 未使用分も含む |
| □ | 貸与PCやスマートフォン | 会社支給機器 |
| □ | 業務関連資料・データ | マニュアルや作成資料 |
| □ | 退職所得申告書 | 退職金計算に必要 |
定年退職者に配付するもの
回収物だけでなく、定年退職者に配付する書類などもあります。項目はチェックリストをご活用ください。
| 定年退職時に配付 | 用途・注意点 | |
|---|---|---|
| □ | 源泉徴収票 | 退職年の収入証明 |
| □ | 雇用保険被保険者離職票-1,-2 | 3枚複写の3枚目 |
| □ | 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書 | 被保険者通知用 |
| □ | 退職証明書 | 本人請求時 |
| 定年退職後に配布 | 備考 | |
|---|---|---|
| □ | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書 | 本人請求時 |
| □ | 在籍期間証明書 | 本人請求時 |
定年退職者の手続きでは、通常の退職と共通する部分が多い一方で、貸与物の種類が多岐にわたったり、書類の用途が異なったりする場合があります。
チェックリストを活用しながら、漏れなく対応することで、定年退職者にとっても会社にとっても円満な退職となるでしょう。
定年退職の手続きとあわせて行うこと
公的手続きや回収・配布物のほかにも対応が必要な確認事項について解説していきます。主な確認事項は以下の4つが挙げられます。
- 有給休暇の残日数の確認
- 各ツールへのアクセス権の削除
- 財形貯蓄制度の解約手続き
- 従業員貸付制度
各種制度や権利の処理を確実に行うために一つずつ確認していきましょう。
有給休暇の残日数の確認
有給休暇は在籍期間中にしか取得できません。「気づいたら有給が残っていた」「消化せずに退職してしまった」 という状況を避けるためにも、早めに消化してもらいましょう。
たとえば、3月31日が定年退職日の場合、2月28日を最終出勤日として約1か月間を有給休暇とすることができます。
有給休暇の残日数は、給与明細や勤怠管理システムで管理・確認が可能です。とくに長年勤めた従業員の場合、有休が多く残っているケースもあるため、本人と相談し、消化の方針を決めるのも一案です。
各ツールへのアクセス権の削除
会社支給のPCやスマートフォン、業務システムへのアクセス権は、最終出勤日までに確実に削除します。
アクセス権が残っていると、退職後に不正アクセスや情報漏えいが発生するリスクがあります。
個人所有の端末に会社のデータが残っていないか確認するのを忘れないようにしましょう。
財形貯蓄制度の解約手続き
定年退職時、財形貯蓄は基本的に解約となります。ただし、退職後2年以内に財形制度のある企業に再就職する場合は継続が可能です。
解約手続きには金融機関での処理が必要となるため、即日完了しないケースもあります。
時間がかかることを考慮して、退職者の資産の引き出しに影響しないよう、スケジュールを決め余裕をもって進めることをおすすめします。
従業員貸付制度
従業員貸付金に残額がある場合は、一括で返済してもらいます。賃金から一方的に天引きするのは違法となるため、返済方法については従業員との合意が必要です。
長年勤務していた従業員ほど、貸付残額が高額になっている可能性もあります。本人の負担が大きくならない方法を検討しましょう。
退職金との相殺などの対応は、あらかじめ就業規則で規定しておく必要があります。
人事労務担当者が知っておきたい定年に関する情報は以下からご確認いただけます。
定年退職後も会社で保管する書類と期間
定年時の退職手続きが完了したあとも、会社には引き続き管理しなければならない書類があります。
以下の書類は、法令に基づいて一定期間の保管が義務づけられています。
| 保管期間 | 書類 |
|---|---|
| 2年 | 雇用保険関連の一般書類(被保険者に関する書類は4年) |
| 3年 | ・賃金台帳 ・労働者名簿 ・勤怠記録(出勤簿、タイムカード) ・退職に関する書類(退職届、退職証明書) ・災害補償に関する書類 |
| 4年 | ・雇用保険被保険者関連書類 ・資格取得等確認通知書 ・離職票 ・離職証明書 |
| 5年 | ・健康診断個人票 ・身元保証書、誓約書 |
| 7年 | ・源泉徴収簿 ・給与所得者の扶養控除等申告書 ・給与所得者の保険料控除申告書 ・請求書、領収書、振込通知書 |
※法定三帳簿(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿)などの書類は当面3年です。経過措置が終了すると完全に5年保存となります。
万が一、定年退職後に公的機関から確認を求められたり、本人や遺族から照会があったりした場合に備え、どの書類をどれくらいの期間保管したらいいか把握しておきましょう。
保管期間を過ぎた書類は、個人情報保護の観点から適切に破棄する必要もあります。
定年退職の手続きを効率よく進める方法
定年を迎える従業員の退職手続きは、人事労務担当者として短期間で多くの業務をこなさなければなりません。
手続きが煩雑になるとミスや遅れが発生し、退職者や関係部署に影響を及ぼすリスクもあるため、効率的に進めることが重要です。
最後に、退職手続きをスムーズに進めるためのヒントを紹介していきます。
労務管理システムを活用する
労務管理システムの導入により、退職手続きの効率化を実現できます。とくに社会保険や雇用保険の喪失手続き、源泉徴収票のWeb発行 などに活用でき、業務負担の軽減につながります。
給与計算システムと連携すれば、退職金の計算や税処理も自動化され、退職手続きをスムーズに進められます。
労務管理システムで詳しい機能、できることは、以下の記事よりご確認ください。
各種手続きに電子申請を利用する
e-Govと連携した労務管理システムなら、窓口に行かなくても、社会保険や雇用保険の喪失手続きがオンラインで完結します。
電子申請は24時間365日いつでも手続きが可能で、チェック機能を活用することで、記入ミスが減り、手戻りの手間も減らせます。
各種手続きの電子化によりペーパーレス化が進み、書類作成や保管の手間も大幅に削減されるでしょう。
対応チェックリストを準備しておく
定年退職の手続きを漏れなく実施するため、チェックリストの準備がおすすめです。
提出書類と期限の一覧、回収が必要な会社貸与物の一覧、各種手続きの担当者と期限、退職者への説明事項などを整理しておきます。
チェックリストを活用すると、期限内に確実に手続きが完了し、退職者を待たせることなく気持ちよく送り出せるでしょう。
とくに保険や税金に関する退職手続きは、期限が厳密に定められているため、スケジュール管理が重要となります。
退職手続きだけでなく、入社手続きもあわせて確認するには以下の記事もご確認ください。
定年退職の手続きはミスなく効率的に(まとめ)
定年退職の手続きは、通常の退職と共通する部分が多い一方で、長年勤務した従業員だからこその対応が必要なこともあるでしょう。
手続きの流れを整理し、必要な書類の回収・配付を進めることで、退職者をスムーズに送り出せます。
また定年時の退職手続きを効率化し、ミスを防ぐためには、労務管理システムや電子申請の活用が有用です。退職者データの一元管理やペーパーレス化により、人事労務担当者の負担を減らせます。チェックリストも活用しながら、効率的に進めましょう。
定年退職は、従業員にとって人生の節目であり、新たなステージへ進む大切な時期です。従業員への感謝と敬意を示しながら対応すると、退職後の関係性や企業の信頼にもつながるでしょう。
定年退職の手続きを効率化するには|One人事[労務]
One人事[労務]は、退職手続きに関連する電子申請を、Web上で完結できる労務管理システムです。
退職手続きにかかる、健康保険や雇用保険の資格喪失届や離職票などの手続きの電子申請に対応しています。
従業員ごとに書類を管理・参照でき、記入ミスを防止できるため、担当者の業務負担を大幅に軽減します。
One人事[労務]の初期費用や気になる操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門スタッフが、貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、労務管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。労務管理をシンプルにして「本来やりたい業務」に集中したい企業は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |