労働時間の定義とは|労働基準法ではどこまで? 勤務時間との違いや判断基準を解説
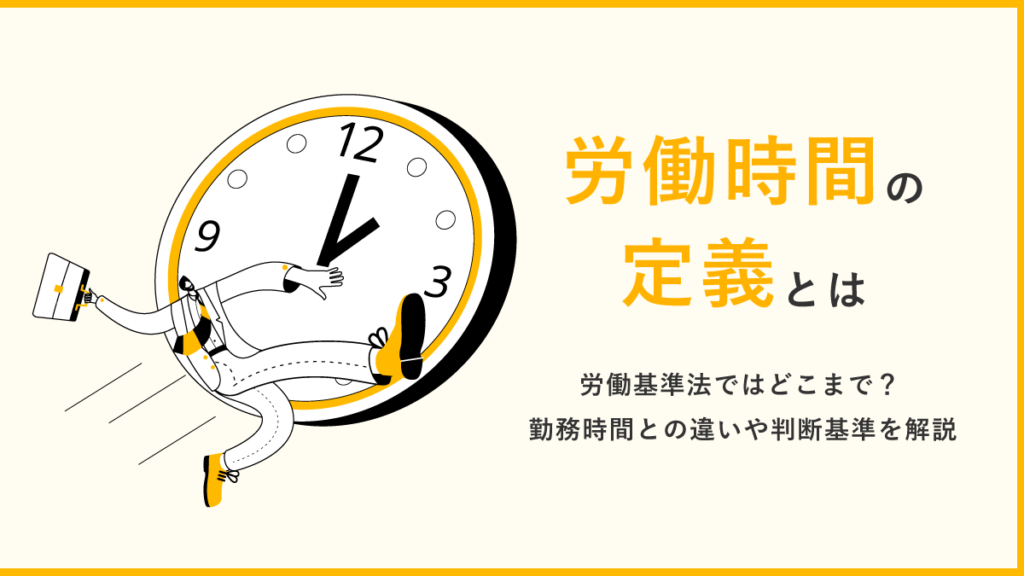
労働時間とは、始業から終業まで、働く人が会社の指示に基づいて仕事をしている時間です。
- 今の作業時間は労働時間に含まれる?
- 休憩時間や移動時間は給与の対象になる?
労働時間の定義を誤ると、未払い残業や行政指導につながるため注意しなければなりません。労働基準法では、どこまでを労働時間とカウントするべきか、厳密なルールが定められています。しかし実際の現場では「グレーゾーン」もあり、判断に迷うことも少なくありません。
本記事では、「労働時間とは何か?」を法律の考え方から明確にし、「どこまでが労働時間にあたるのか?」を具体的な判断基準とともに解説します。適切な勤怠管理に向けた基礎知識としてお役立てください。
▼労働時間の管理に不安がある方は以下の資料もご活用ください。

 目次[表示]
目次[表示]
労働時間とは? 労働基準法上の定義は?
労働時間は、最高裁判決で「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義が示されています。
有名な三菱重工長崎造船事件(最高裁平成12年3月9日判決) では、「使用者の明示または黙示の指示に基づき労働者が業務に従事する時間は労働時間にあたる」との見解が出されました。
就業規則や雇用契約書に書かれている時間にかかわらず、客観的に見て労働者が使用者の指揮命令下に置かれているのであれば労働時間です。たとえば始業時刻が9時の職場で、9時開始の会議準備を指示された従業員は、9時より前に労働時間はすでに始まっていると判断します。
では労働時間について労働基準法では具体的に規制があるのでしょうか。
労働基準法第32条
労働基準法第32条では、労働時間の上限を定め、超える場合に適切な対応を求めています。
労働時間は、原則として1日8時間、1週間40時間を超えてはいけません。労働基準法第32条に定義づけられた規制は、労働者の健康と安全を守るための基本的なルールです。
上限を超えて労働させると、時間外労働(いわゆる「残業」)となり、使用者には割増賃金の支払い義務が発生します。
労働基準法第119条
さらに労働基準法第119条では、労働時間に関する規定に違反した場合の罰則が定められています。違反した使用者(雇用主)は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
労働時間に関する罰則は、単なる行政指導ではなく刑事罰に該当するため、「知らなかった」「うっかりしていた」では済まされません。労働基準監督署の調査で違反が発覚した場合、是正指導だけでなく、刑事責任を追及されることもあるため、企業は日頃から注意して勤怠管理を行わなければなりません。
▼労働基準法の違反事例は以下も記事をご確認ください。
勤務時間・就業時間との違い
労働時間に対して勤務時間は、労働基準法や判決で示された定義はありません。
勤務時間(就業時間)とは、一般的に就業規則で定める始業から終業までの時間を指します。勤務時間のなかには休憩時間も含まれている一方、労働時間は勤務時間から休憩時間を除いた時間です。
労働時間は実際に従業員が労働をしていた時間、勤務時間や就業時間は就業規則に規定される拘束時間という点に違いがあります。
▼労働時間と就業時間の違いを詳しく知るには以下の記事をご確認ください。
労働時間の理解に欠かせない用語
2019年の働き方改革関連法の施行により、労働時間の適正管理がより厳格に求められるようになり、労働基準監督署の取り締まりも強化されています。
違反があれば、企業の信用を大きく損なうだけでなく、従業員から損害賠償請求を受けるリスクもあります。経営者や人事担当者は正しい知識を持ち、適切な勤怠管理を徹底することが重要です。

以下では労働時間の理解に欠かせない用語を5つ取り上げて解説しています。
法定労働時間
法定労働時間とは、労働基準法第32条で定められた、労働時間の法的上限です。原則として1日8時間、1週間40時間を超えて労働させることは禁止されています。法定労働時間は長時間労働による労働者の健康被害を防ぐために設けられた規制です。
ただし、変形労働時間制やフレックスタイム制など柔軟な制度を採用している場合は、固有のルールがあり、必ずしも規制を守る必要はありません。
法定労働時間を超えて労働させる場合は、時間外労働(残業)として扱われ、割増賃金(時間外手当)の支払いが義務づけられます。
所定労働時間
所定労働時間とは、法定労働時間の範囲内で、企業が独自に定めた労働時間です。所定労働時間を超えた場合も基本的に残業扱いとなりますが、割増手当の支払い義務は法定労働時間を超えているか否かで変わります。
▼法定労働時間と所定労働時間の違いや、手当の支払いに不安がある場合は、以下の記事もあわせてご確認ください。
実労働時間
実労働時間とは、労働者が実際に業務を遂行していた時間です。休憩時間は含まれず、雇用主の指揮命令下にあることが判断の分かれ目となります。
始業前の朝礼や準備、終業後の後片づけなども会社の指示があれば実労働時間に含まれます(詳しくは後述)。
実労働時間が法定労働時間を超えた場合、企業は残業代を支払わなければなりません。
拘束時間
拘束時間とは、職場で拘束される時間の総計を指します。実労働時間と休憩時間を合算したものです。時間外労働が発生した分だけ、労働者の拘束時間は延長されます。
拘束時間が長くても、休憩が適切に確保されていれば問題ありませんが、休憩時間中に業務を命じると実労働時間に該当するため注意しましょう。
休憩時間
休憩時間とは、労働者が業務から完全に解放される時間です。
労働基準法第34条では、6時間を超える労働には少なくとも45分、8時間を超える労働には少なくとも1時間の休憩時間を与えることが定められています。
休憩時間内に電話当番などの労働義務を課すことはできません。休憩時間は自由に利用できることが原則です。
労働時間と判断される基準|どこからどこまで?
労働時間だと判断するには、基準を把握しておくことが重要です。労働時間に含まれるものと含まれないものを紹介し、判断ポイントについても解説します。
| 労働時間に | |
|---|---|
| 含まれる(例) | 含まれない(例) |
| ・始業前の朝礼、機械点検、開店準備 ・終業後の清掃、報告書作成 ・所定労働時間内の業務に必要な移動時間 | ・労働者の自由意志で行った自己啓発・勉強 ・終業後の雑談 ・自由参加の研修 |
労働時間に含まれるもの
労働時間に含まれるものの具体例としては、主に以下のとおりです。
- 残業時間
- 業務の準備・後片付け(清掃など)
- 着替え時間(制服や作業服の着用が義務づけられている場合)
- 朝礼・夕礼
- ミーティング
- 研修時間(参加が義務付けられている場合)
- 仕事の引継ぎ
- 待機時間(手待ち時間)
- 電話当番・来客対応
- 社員旅行
- 仮眠時間
- 取引先への移動時間
近年、リモートワークなどにより、労働時間に含まれるか判断が難しいケースが増えています。客観的に見て、義務づけられたものかどうかが一つの基準となると理解しておきましょう。
労働時間に含まれないもの
労働時間に含まれないものの具体例としては、以下のような時間が挙げられます。
- 休憩時間
- 通勤時間
- タイムカードを打刻する時間
- 始業時間前の出勤
- 自由参加の研修時間
- 出張などの移動時間
- 自由意志での着替え時間
基本的に、労働者本人が自主的に行う時間は労働時間に含まれないと理解しておきましょう。
判断ポイントは「使用者の指示があるかどうか」
労働基準法や最高裁の判決から、労働時間は「使用者の指揮命令下にある時間」かどうかで判断されます。
単に作業をしている時間だけでなく、 上司の指示で待機している手待ち時間や準備・後片づけの時間も、自由に行動できない状況であれば労働時間です。
また、労働基準法第38条の2では、出張などで労働時間を算定することが難しい場合、特別な指示がなければ「所定の勤務時間分を働いた」とみなすとしています。

労働時間の上限と時間外労働の考え方
労働時間には上限があり、企業が従業員に 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせる場合には、 一定の条件を満たす必要があります。
ここまで解説してきた法定労働時間を踏まえ、超過労働時間について整理します。
36協定の締結により月45時間・年360時間まで
労働基準法では、法定労働時間を超える労働は禁止されていますが、労使間で「36(サブロク)協定」を締結し、労働基準監督署長へ届け出ると、一定の範囲内で時間外労働が認められます。
36協定を締結した場合も、上限は原則として月45時間・年360時間 です。上限時間を超えた労働を行わせることは 労働基準法違反に該当し、罰則の対象となります。
また、36協定の 対象期間は1年間 であり、継続する場合は有効期間が切れる前に再度協定を締結し、届け出をする必要があります。
なお、パート・アルバイトであっても適用される上限ルールは同じです。
特別条項の追加により年間720時間まで
業務量の大幅な増加など通常の範囲を超えた労働が必要になる場合、特別条項付きの36協定を締結することで、年間720時間までの時間外労働が可能となります。
ただし、臨時的な事情であっても、無制限に残業ができるわけではありません。以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 時間外労働が 年間720時間以内
- 時間外労働+休日労働の合計が 月100時間未満
- 時間外労働+休日労働の合計が、 2〜6か月平均で80時間以内
- 月45時間を超える時間外労働は、年6か月まで
規定を超えて労働させた場合、企業には罰則が科される可能性があります。
また、特別条項付きの36協定も、所轄の労働基準監督署への届け出が必要です。
労働時間を超えて労働基準法に違反した場合の罰則
労働基準法は、働く人の最低労働条件を定めた法律です。当事者の合意があっても変更や免除ができない強行法規であり、使用者として知らなかったでは済まされません。
法定労働時間を超える労働や以下の違反をした場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金対象となります。
- 残業代(時間外労働手当)の未払い
- 最低限の休憩時間を与えない
- 法定休日に働かせる
また、労働基準監督署からの是正指導や、従業員からの損害賠償請求の可能性もあります。企業の信用を守るためにも、適切な労務管理が必要です。
▼「労働基準法に違反したらどうなるか?」詳細は、以下の記事でご確認ください。
労働時間に関するその他のルール
労働時間の管理は、企業にとっても従業員にとっても重要なポイントです。法定労働時間を守るだけでなく、休憩や休日の確保、長時間労働への配慮など、気をつけたいポイントはいくつもあります。
- ルール1.労働時間が6時間を超えたら休憩を与える
- ルール2.適切な休日を与える
- ルール3.長時間労働の従業員に対して安全配慮義務を果たす
- ルール4.労働時間は客観的な方法で把握する
労働時間に関するルールのなかでも、とくに基本的なものを抜粋し、適切な労務管理に役立つ情報を紹介します。
労働時間が6時間を超えたら休憩を与える
労働基準法では、労働時間が6時間を超えたら休憩を与えることを定めています。
- 6時間超~8時間以内の労働:45分以上の休憩
- 8時間を超える労働:1時間以上の休憩
休憩時間は完全に業務から解放される時間でなければなりません。休憩中に業務の指示を受けた場合、「労働時間」とみなされるため、別途休憩を確保する必要があります。
また、休憩時間は労働時間の途中に与えなければなりませんが、労働時間の途中で与えれば、いつ与えてもかまいません。
なお、法定基準を超える休憩を設けるのは問題ないとされています。
適切な休日を与える
労働基準法第35条は、毎週1日以上または4週間で4日以上の法定休日を与えることを定めています。
企業は法定休日に加えて所定休日を設定でき、就業規則や雇用契約書に明記しなければなりません。
なお、労働基準法では労働時間を「1日8時間、週40時間」の範囲に収めなければならないと定められています。
そのため、1日の所定労働時間が8時間の場合は、週2日の休みとして土日を休日とする企業が多くあります。
長時間労働の従業員に対して安全配慮義務を果たす
企業には、従業員に対して、安全で健康的な労働環境を提供する義務(安全配慮義務)が生じます。
労働時間が長すぎると、うつ病や適応障害といった精神疾患を発症するおそれがあるため、労働時間を把握し、管理することが求められます。
疲労の蓄積が認められるときは、医師による面接指導を実施します。医師の意見に基づいて労働時間短縮などの措置を実施しなければなりません。
労働時間は客観的な方法で把握する
働き方改革関連法の施行により、企業は全従業員の労働時間を「客観的な方法」で把握することが義務づけられました。
タイムカードやパソコンの使用時間などを活用し、労働日ごとの始業・終業時刻を適正に記録する必要があります。記録は最低3年間保管し続けなければなりません。
管理しなければならない従業員には、管理監督者や裁量労働制で勤務する人も含まれます。
客観的な労働記録の管理には勤怠管理システムの活用が欠かせません。現在の勤怠管理に課題がある、そもそも客観的であると言い切れる自信がない方は、One人事[勤怠]をはじめ、システムの活用をおすすめします。
One人事[勤怠]は多様な働き方を支援するクラウド型勤怠管理システムです。画面がシンプルで見やすく、乗り換えや初めての導入にも抵抗感が少なくお使いいただけます。
→客観的な労働時間の記録を実現|「One人事」サービス資料を無料ダウンロード

労働時間のカウント方法
給与計算を正確に行うためには、労働時間を正確に算出することが重要です。労働時間は、基本的に以下の流れで計算していきます。
- 実労働時間を集計・算出
- 1日単位で残業時間を集計・算出
- 週単位で残業時間を集計・算出
まずは日ごとの勤務時間から休憩時間を差し引いて実労働時間を算出します。遅刻や早退の時間も勤務時間から控除しなければなりません。
次に1日単位で、所定労働時間を超過した時間を、法定内残業(8時間以内)と法定外残業(8時間超)に分けて算出します。
そして週単位で所定労働時間を超えた時間も、法定内残業(週40時間以内)と法定外残業(週40時間超)に分けて算出します。
具体例
具体例として、ある従業員が9:00から20:00まで勤務した場合の労働時間をカウントしてみましょう。
勤務時間は9:00~20:00の11時間ですが、昼休憩の1時間(12:00〜13:00)を差し引いて、実際の労働時間は10時間です。
10時間のうち、9:00~18:00(8時間)は法定内労働時間、18:00以降の2時間(18:00~20:00)が法定外残業時間に該当します。
週の別日の労働時間と合計し、週の総労働時間が40時間を超過した場合、超過分は週単位の法定外残業としてカウントします。
カウントされた労働時間は、法定内・法定外の区分に応じ、それぞれ異なる賃金率が適用され、給与計算に反映されるのです。
端数処理
労働時間は1分単位で集計されるのが原則ですが、端数が出る場合はどのように処理すればよいのでしょうか。
法律上、労働時間の端数は一定の基準で切り上げ、または切り下げて処理することが認められています。
たとえば、30分未満の端数は「一律」切り捨てるなど、あらかじめ明確に定めた基準があることが前提です。企業が意図的に労働時間を短縮する目的で端数を切り捨てることは認められません。
労働時間制度の種類
労働時間の管理・運用では、法定労働時間の範囲内で働くだけでなく、業務の特性や労働者の働き方に応じて柔軟な制度を採用できます。
企業は生産性とワークライフバランスを考慮し、最適な労働時間制度を選択する必要があるでしょう。
法定労働時間の規定に厳密に縛られない労働時間制度は、主に3種類あります。
変形労働時間制、フレックスタイム制、みなし労働時間制、それぞれの制度の特徴やメリット・デメリットを解説します。
1年単位の変形労働時間制
変形労働時間制は、業務の繁閑に応じて柔軟な労働時間配分を可能にする制度です。期間を通じた法定労働時間の範囲内で、繁忙期は長く、閑散期は短く労働時間を設定できます。
主な目的は、業務効率の向上と労働時間の適正化です。季節的な需要変動がある業種や特定期間に業務が集中する場合、とくに有効です。
メリットは、人員配置の最適化や残業代の削減、従業員の長期休暇取得の実現が挙げられます。一方でデメリットには、労務管理の複雑化や従業員の生活リズムへの影響があります。導入には労使間の合意と適切な運用管理が不可欠です。
なお、変形労働時間制には1年単位のほか、1か月単位や1週間単位の適用も可能です。
▼変形労働時間制を詳しく知るには以下の記事もあわせてご確認ください。
フレックスタイム制
フレックスタイム制は、一定期間の総労働時間を定めたうえで、日々の始業・終業時刻を従業員が選択できる柔軟な勤務形態です。総労働時間が遵守されれば、日によって労働時間を調整することが可能です。
多くの企業では、社内コミュニケーションを確保するため「コアタイム」を設定し、その前後に自由な出退勤が可能な「フレキシブルタイム」を配置します。ただし、コアタイムは必須ではなく、完全な裁量制を採用する「スーパーフレックスタイム制」も存在します。
フレックスタイム制は、従業員のワークライフバランス向上や生産性向上がメリットです。ただし、労務管理の複雑化やコアタイムがある場合の制約が課題といえます。また、チーム間の連携や顧客対応に支障が出る可能性もあるため、業務特性に応じた適切な制度設計が重要です。
▼フレックスタイム制を詳しく知るには以下の記事もあわせてご確認ください。
みなし労働時間制
みなし労働時間制は、外勤や在宅勤務など、実労働時間の把握が困難な業務に適用される制度です。実際の労働時間にかかわらず、所定の時間や通常必要とされる時間を労働したとみなして賃金を支払います。
実労働時間が所定時間より短い場合でも所定時間分の賃金が支払われる一方、超過しても追加の残業代は発生しないのが特徴です。
業務の柔軟性と管理コストの削減というメリットがある一方、長時間労働の可能性や実態に即した報酬が得られないというデメリットもあります。採用する場合、みなし時間の設定や想定される業務量について確認することが重要です。
▼みなし労働時間制を詳しく知るには以下の記事もあわせてご確認ください。
労働時間に有給休暇は含まれる?
有給休暇を取得した当日は、実際には働いていないため、実労働時間には含まれません。時間外労働や残業時間も発生しません。
しかし有給休暇は、労働基準法第39条に基づく従業員の法的権利であり、賃金が保証される休暇です。
実労働時間としてはカウントされませんが、通常どおり賃金は支払われ、給与計算上は「出勤」と同様に扱われます。
年次有給休暇の取得義務(5日間取得義務)が企業に課されていることを踏まえると、労働時間と同じように適切な管理体制を整える必要があります。
日本の労働時間は長い?
「日本の労働時間は長い」とよくいわれますが、本当なのでしょうか。
OECDの2023年の調査によると、日本の労働者1人あたりの年間実労働時間は平均1611時間と報告されています。アメリカ(1799時間)、OECD全体の平均(1742時間)よりも短い数値です。
また、厚生労働の資料からも緩やかに減少していることがわかります。所定外労働時間は2010年以降、120〜132時間の間で変動し、2020年以降は120時間を下回る水準が2年続いています。
働き方改革が推進されるなか、少しずつ改善されているといえるのかもしれません。しかし、一部では依然として長時間労働が常態化している職場もあります。
いずれにしても企業は、自社の労働時間の管理を徹底し、長時間労働が発生していないかを定期的にチェックすることが大切です。
参照:『OECD Data Explorer』 OECD
参照:『第1章 労働時間やメンタルヘルス対策等の状況』 厚生労働省
まとめ|労働基準法に沿って労働時間を適切に管理
労働時間は「使用者の指揮命令下にある時間」として判断され、実際の作業だけでなく、準備や後片づけの時間も含まれることを忘れてはいけません。また、1日8時間・週40時間の上限を超える場合は、36協定の締結と割増賃金の支払いが必要です。
単に法定基準を守るだけではなく、長時間労働を防ぎ、従業員の健康と企業の成長を両立させることが重要です。
自社では従業員の労働時間を正しく管理できていますか。労働時間の管理体制を見直し、より働きやすい環境づくりを進めるには、勤怠管理システムの活用も検討してみてはいかがでしょうか。
適切な労働時間の管理に|One人事[勤怠]
One人事[勤怠]は、客観的な労働時間の記録を実現する勤怠管理システムです。
- 勤怠の入力・打刻漏れが多い
- 月末の集計をラクにしたい
- 労働時間や残業時間を正確に把握できていない
勤怠管理に課題がある企業をご支援しております。
One人事[給与]と連携すれば、給与計算に自動で紐づけられるため、より速くより正確に業務を進められるでしょう。
One人事[勤怠]の初期費用や気になる操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門のスタッフが貴社の課題をていねいにヒアリングしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、勤怠管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。勤怠管理をラクにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
