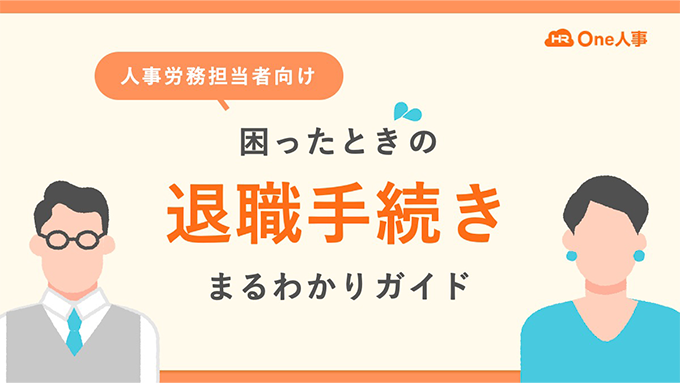退職届はいつまでに提出? 法律と就業規則どちらを優先? 書き方と2〜3か月前の提出が非常識ではない理由も

退職届は何日前までに提出してもらうべきでしょうか。従業員が退職する際は、まず退職届を提出してもらったあと、必要な手続きを案内するという流れが一般的です。
- 退職届の提出期限は法律上いつまでか
- 就業規則で決めたルールと法律、どちらが優先されるのか
その場になると迷ってしまう担当者もいるでしょう。
そこで本記事は、企業の人事労務担当者向けに「退職届」に関する法的ルールを解説し、トラブルを防ぐための対応も紹介します。
 目次[表示]
目次[表示]
退職届は法律上いつまでに提出してもらう?
退職届の提出期限に関する法的なルールは、民法や労働基準法などに基づいて判断されます。
じつは「退職届はいつまでに出せばよいのか?」という疑問は、法律では直接的に規定されていません。
そこで実際には「退職を申し出てから何日後に雇用契約が終了するか」というルールをもとに解釈するのが一般的です。つまり、退職申し出期限を退職届の提出期限と考えます。
とくに「自己都合退職」については、雇用形態によって法的扱いが異なるため、雇用形態ごとに退職届のルールを確認していきましょう。
正社員など無期雇用の場合
正社員のように期間を定めず雇用する従業員については、民法で次のように定められています。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
引用:『民法』e-Gov法令検索
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
無期雇用の従業員は、基本的にいつでも退職の意思を表明することが可能です。退職意思を伝えられてから2週間が経過すると雇用契約が終了するため、法律上は「退職の2週間前までに退職届を提出してもらうのが適切」と解釈できます。
契約社員など有期雇用の場合
無期雇用とは異なり、契約社員やパート、アルバイトなどの有期雇用では、契約期間中の退職は原則として認められていません。
やむを得ない理由がある場合のみ、例外として契約期間中の途中退職が可能です。「やむを得ない理由」にはどのような例が該当するのでしょうか。
- 従業員本人の病気やケガにより働くことが困難な場合
- 家族の危篤や介護など、深刻な家庭の事情がある場合
- セクハラやパワハラ、給与の未払いなど、会社側に問題がある場合
有期雇用であっても、契約から1年が経過している場合、従業員は自由に退職できます。ただし、当初予定していた契約期間が1年を超えていることが条件です。
退職届と退職願、辞表のどれを提出してもらうべき?
「退職届」「退職願」「辞表」は提出される場面が似ているため混同されがちですが、それぞれ異なる役割を持つ書類です。具体的には、次のような違いがあります。
| 書類の種類 | 概要 | 取り下げ可否 |
|---|---|---|
| 退職願 | 退職の打診を受ける際に提出される書類 | 可(退職の承認後は取り下げできない可能性もある) |
| 退職届 | 退職を認めたあとに提出してもらう書類 | 不可 |
| 辞表 | 公務員や経営陣が辞職する際に提出する書類 | 不可 |
退職願はあくまでも打診なので、承認前であれば従業員の取り下げ希望に応じることも可能です。一方、退職届は一度受け取ったあと、取り下げに応じることは基本的にありません。
退職届の提出期限は法律と就業規則のどちらが優先される?
正社員(無期雇用)の場合、退職届は法律上「2週間前までに提出すれば問題ない」とされています。 しかし、実務上は就業規則で「退職の○日前までに提出」と定めている企業が多いのが現状です。では、法律(民法)と会社の就業規則、どちらが優先されるのでしょうか。
原則として法律(民法)のルールが最優先されます。ただし、民法の退職規定は「任意規定」であり、 会社と従業員が合意すれば、柔軟に変更が可能です。特別な事情がない限り、退職届の期限も就業規則に沿うのが一般的となっています。
退職届がギリギリ2週間前に提出されると、引継ぎが間に合わなかったり、代わりの人員を確保できなかったりして、対応が難しくなるでしょう。実質的に「1か月前」「2か月前」に退職届を提出するルールを設けている企業が多いようです。
従業員には基本的に就業規則を遵守してもらうようにしましょう。ただし、退職までの期間があまりに長すぎると、無効になる可能性もあるため適切なルール設定が必要です。
退職届を2〜3か月前に提出しても非常識ではない
従業員にとっても、会社に退職届を提出するタイミングは難しい問題です。なかには退職の2〜3か月前に退職届を提出するのは非常識なのではないかと悩む方もいます。
しかし、退職届を2〜3か月前に提出するのは非常識ではなく、もちろん、会社側が受け取ることにも問題はありません。理由としては以下の3つが挙げられます。
- 法律上は2週間前に伝えればよいから
- 就業規則より法律が優先されるから
- 会社側は十分な時間を確保できるから
理由1.法律上は2週間前に伝えればよいから
民法の規定に基づいて考えれば、無期雇用の従業員は退職の2週間前までに退職届を提出すればよいことになります。
ほかに退職届の提出期間を「いつから」と定める法律はないため、従業員が2〜3か月前に退職届を提出しても問題はありません。
理由2.就業規則より法律が優先されるから
なかには就業規則で「退職届は半年前までに提出する」といったルールを設けている会社もあります。
しかし、前提として、就業規則に法的拘束力はありません。慣習としては就業規則にあわせるケースが一般的ですが、本来は法律が優先されます。退職届を2〜3か月前までに提出すれば、少なくとも民法上の規定は守っていることになるため、非常識とはいえません。
理由3.会社側は十分な時間を確保できるから
2〜3か月前に退職届を受け取れば、会社側は退職の手続きや欠員の補充などに十分な時間を確保できます。
引き継ぎにも時間をかけられるため、会社側としては退職直前に相談されるよりも助かる面が大きいといえます。
退職届の書き方・テンプレート
退職届の書き方も法律的な決まりはありません。退職届のフォーマットは自由ですが、必要な情報が抜け落ちると、手続きがスムーズに進まない原因になります。
必要な情報を漏れなく記入してもらうために、会社指定のテンプレートを用意するのがおすすめです。書き方の例やポイントは以下のとおりです。
| 冒頭行 | 「退職届」と記載 |
| 日付 | 退職届を提出する日付を記載 |
| 宛名 | 代表取締役など、会社の最高執行責任者の名前をフルネームで記載 |
| 所属と氏名 | 退職する従業員の所属と氏名を記載。末尾に捺印してもらう |
| 文の導入 | 所属と氏名から少し空けて、右寄せで「私儀」または「私事」と記載 |
| 本文 | 退職理由(一身上の都合など)と退職希望日を記載 |
| 文末 | 退職届は退職が確定してから提出してもらうので、文末は「退職いたします」と宣言する言い回しとなる |
退職届は「退職が確定してから提出」する書類のため、「退職いたします」という確定の言い回しを使います。提出された退職届は、労務管理の記録として適切に保管しましょう。
退職届を受理してから対応すべき手続き
退職届を受理したら、すみやかに退職に関する手続きを進めます。
社会保険や雇用保険の資格喪失手続きは期限が決められているため、漏れなく対応できるようスケジュールを管理しましょう。健康保険証の回収は退職日までに必ず行い、未返却がないか確認します。
退職時に交付または返却する書類は以下のとおりです。
また、以下の書類は、従業員本人が希望する場合に交付します。
| 退職証明書 | 退職したことを証明する書類。転職先から求められることがある |
| 離職票 | 失業保険の申請に必要 |
| 健康保険資格喪失証明書 | 国民健康保険に加入する場合に必要 |
退職者に対して行う手続きは以下の記事で詳細をまとめて解説しています。あわせてご確認ください。
退職届の受理から退職までのスケジュール
従業員が退職する場合に備えて、退職届を受理してからのおおまかな流れも把握しておきましょう。
| 2〜3か月前 | 退職の意思を伝えられる |
|---|---|
| 1〜2か月前 | 退職届を受け取り、引き継ぎを依頼する |
| 3日〜1か月前 | 引き継ぎが終わり次第、有給休暇を消化させる(任意) |
| 退職日当日 | 従業員からのあいさつ後、貸与物を回収する |
それぞれ以下で詳しく解説します。
1.2〜3か月前|退職の意思を伝えられる
退職に関する相談は、おおむね2〜3か月前に伝えられるケースが多いでしょう。
多くの場合、最初に相談を受けるのは従業員の直属の上司です。従業員と話し合いをして、具体的な退職日を決定します。
2.1〜2か月前|退職届を受け取り、引き継ぎを依頼する
退職日が決まったら、1〜2か月前に退職届を受け取ります。退職届を受理したら、業務の引き継ぎを依頼しましょう。必要な場合は、取引先へのあいさつ回りも依頼します。
会社側は、引き継ぎと並行して退職関連の事務手続きを進めていきましょう。
3.3日〜1か月前|引き継ぎが終わり次第、有給休暇を消化させる
引き継ぎが終わったら、有給休暇を消化してもらいます。有給休暇の残日数に応じて、引き継ぎをいつまでに終わらせるか、従業員と相談しながら計画を立てることが大切です。
引継ぎが十分に終わらない場合は、必ずしも消化してもらう必要はありません。
4.退職日当日|従業員からのあいさつ後、貸与物を回収する
退職日当日は、従業員から社内に退職のあいさつが行われます。会社側は、社員証や制服などの貸与品を忘れずに回収することが大切です。
従業員が最終出社日から退職日までの間に有休を取得する場合は、その前にあいさつや貸与品の返却を終わらせておくよう伝えましょう。
退職届の提出後に引き継ぎを拒否されたとき
退職届を受理したあと、従業員が「引き継ぎはしません」と拒否した場合、人事担当者としてどのように対応すべきでしょうか。
そもそも引き継ぎを強制することはできる?
「引き継ぎを強制することはできるのか」 という疑問を持つ方もいるかもしれませんが、結論として引き継ぎは強制できません。会社ができるのは、従業員に対して引き継ぎ指示を業務命令として出すまでです。
引き継ぎを拒否したことを理由に退職を認めないことは、違法性を問われる可能性が高いため注意しましょう。
とはいえ、引き継ぎをしないまま退職されてしまうと、業務が滞ったり、取引先との関係性がこじれたりするリスクがあります。
引き継ぎを拒否されそうな場合は、次のような対処法を検討するのがおすすめです。
有給休暇の取得要求に時季変更権を行使する
従業員が「有給休暇を消化したいから引き継ぎはできない」と主張した場合は、時季変更権を行使して交渉するとよいでしょう。
有給休暇の時季変更権とは、会社の正常な運営が妨げられることを理由に、従業員の有給休暇を取得する時季を変更できる権利です。
ただし、退職日を過ぎてからの行使は不可能です。退職日までに引き継ぎを終えてもらうようスケジュールを調整するか、退職日をずらしてもらう必要があります。
損害賠償請求をできる場合もある
従業員が引き継ぎを一切しなかったことにより、会社が損害を被った場合は、損害賠償を請求できる可能性があります。
ただし、実際に損害賠償請求を行うに難しい側面もあります。「引き継ぎがなかったこと」と「損害を被ったこと」の因果関係を証明するのは難しく、現実に請求が認められたケースはほとんどありません。
賠償請求は交渉材料として伝える場合もあります。いずれにしても、引き継ぎを拒否された場合の対応方針を、事前に社内で整理しておくとよいでしょう。
就業規則などに明記すれば、退職金を減額できる場合もある
「引き継ぎを拒否した場合は退職金を一部減額する」 という規定を就業規則に定めている会社もあります。あらかじめ減額の基準が明記されていることが前提です。
退職金を全額支給しないことは認められていません。引き継ぎ拒否による影響が大きい場合に限定して、一部減額の範囲におさめましょう。さらに中小企業退職金共済等の共済制度や確定拠出年金制度を利用している場合は、原則として一部減額も認められません。
退職届の提出にまつわる疑問
最後に、退職届の提出に関するよくある疑問に回答していきます。実際の業務で「この場合はどうすればいい?」と悩んだ際に、参考にしてください。
退職届に記載されている提出日を過ぎていたら?
退職届に記載されている提出日が過去の日付であっても、数日程度であればそのまま受理するケースが大半です。ただし、あまりにも前の日付が書かれている場合は、トラブル防止のために再提出を求めてもよいでしょう。
退職届は郵送で提出してもらってもいい?
退職届は対面での提出が基本ですが、病気やケガなどのやむを得ない理由がある場合は、郵送で提出してもらっても問題ありません。郵送では、万が一の紛失に備えて簡易書留や特定記録郵便で送ってもらうと安心です。
休職中に退職届を提出できる?
休職中であっても、退職届を提出してもらうことは可能です。出社が難しい場合は、郵送で送ってもらってもよいでしょう。
パワハラが原因のとき、退職届はいつまでに提出してもらう?
パワハラが原因で辞める従業員についても、退職届の提出期限は変わりません。基本的には就業規則に準じてもらい、法律上は2週間前までに提出してもらえば問題ありません。
パワハラでの退職は、会社がパワハラを事実として認める場合は、自己都合退職ではなく会社都合退職として扱います。会社都合退職は失業保険の給付で従業員にとってメリットが多くあります。給付申請に必要な離職票や退職証明書には、「会社都合」退職であることを正直に明記しましょう。
まとめ
正社員(無期雇用)の場合、民法上は「2週間前まで」に退職届を提出してもらえば問題ありません。しかし、民法の規定は任意規定のため、企業が就業規則で独自の提出期限を定めることも可能です。
実際には、多くの企業が「1か月前」や「2か月前」などのルールを就業規則で定め、運用しています。あまりにも早すぎる提出期限は、従業員の退職の自由を制限するため、無効と判断される可能性があります。
従業員とのトラブルを避けるためにも、企業は就業規則に退職届の提出期限を明記したうえで、社内周知を徹底することが大切です。
退職手続きを効率化|One人事[労務]
One人事[労務]は、退職手続きに関連する各種保険の電子申請を、Web上で進められる労務管理システムです。
- 【入退社手続き】書類管理や届出対応が煩雑
- 【行政手続き】転記・参照ミスが多い
- 【年末調整】記入漏れ・修正の対応に追われている
労務管理に悩みがある担当者の業務効率化を助けて手間を軽減。ペーパーレス化や工数削減、コア業務への注力を支援しております。
One人事[労務]の初期費用や気になる操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門スタッフが、貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、労務管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。労務管理をシンプルにして「本来やりたい業務」に集中したい企業は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |