一週間の労働時間は40時間まで? 上限を超えたらどうする? 対応方法と計算を解説

「週の労働時間は40時間まで」と聞いたことがあるかもしれません。しかし実際には、週の労働時間をどのように管理し、40時間を超えてしまったら、どのように対応すればよいか悩んだことはありませんか。
担当者には法的な理解と適切な手続きが求められます。誤って対応を間違えると罰則を科される可能性もあるため注意しなければなりません。
本記事では、週40時間を超えた場合の対応方法や罰則、労働時間の数え方などをケース別にわかりやすく解説します。
→労働時間の管理をラクにする「One人事」資料をダウンロード
労働時間の集計や管理に課題があるという方は、次の資料も参考にしてください。

 目次[表示]
目次[表示]
一週間の労働時間は40時間までが原則
企業が労働者に課すことのできる労働時間は、法律によって厳格に定められています。具体的には、労働基準法第32条で「1日あたり8時間、1週間あたり40時間まで」と法定労働時間が定められています。
| 【ポイント】法定労働時間 | |
|---|---|
| 1日あたり | 8時間まで |
| 1週間あたり | 40時間まで |
また法定労働時間を超える労働を「時間外労働」といいます。時間外労働をさせる場合は、労使間で『時間外・休日労働に関する協定』(以下、36協定)を締結しなければなりません。
さらに企業が1日8時間、週に40時間を超える労働をさせる場合は、一定の割増賃金を支払うよう義務づけられています。
法定労働時間を基準に「月単位」「1日単位」「年単位」での労働時間の上限を確認したい方は、以下の記事もご覧ください。
所定労働時間と法定労働時間の関係
あらためて確認すると、労働時間とは労働者が使用者の指揮命令下にある時間のことです。労働時間は、大きく「所定労働時間」と「法定労働時間」の2つに分けられます。
| 所定労働時間 | 業が就業規則や雇用契約書で定める労働時間 |
| 法定労働時間 | 労働基準法で定められた、企業が労働を命じられる上限の労働時間 |
所定労働時間は、業務形態にあわせて企業が任意で規定できるものです。一方で法定労働時間が「1日8時間・週40時間」までと定められているため、所定労働時間は、法定労働時間の範囲内で設定しなければなりません。
たとえば、時給を2,000円・所定労働時間を7時間と定めている企業において、従業員が10時間勤務した場合、給与を以下のとおり支払う必要があります。
| 所定労働時間 | 時給2,000円×7時間=1万4,000円 | |
| 法定内残業時間 | 時給2,000円×1時間=2,000円 | →割増賃金なし |
| 法定外残業時間 | 時給2,000円×2時間×割増率1.25=5,000円 | →割増賃金あり |
法定労働時間内の残業に対しては割増賃金が発生し、法定労働時間を超えた残業は、割増賃金が発生すると覚えておきましょう。
法定労働時間「週40時間」に含まれるもの
法定労働時間である「週40時間」は、法定休日労働と1日8時間を超える労働時間を除いた実働時間の累計と定義されています。
法定休日とは、労働基準法で定められた休日のことです。労働基準法では週に1日以上、もしくは4週間に4日以上の休日を設けるように定められています。法定休日に働くことを法定休日労働といいます。
企業が法定休日労働を課した場合は、法定労働時間の「週40時間」には含めず、従業員に対して割増賃金を支払わなければなりません。
一方で、労使間の合意に基づいて就業規則や雇用契約書で定められた法定休日以外の休日を、所定休日といいます。所定休日に勤務した場合は割増賃金は支払われないものの、「週40時間」には含まれると覚えておきましょう。
法定休日と所定休日の違いについて、さらに詳しく知りたい方は以下の記事もご確認ください。
| 週40時間に含まれるか判断に迷うもの | |
| 含まれる | 法定休日労働 |
| 含まれない | 所定休日労働 |

週40時間の上限が設定された背景
以前も労働時間の上限を定める規定はありましたが「特別条項付きの36協定」を締結すれば、いくらでも時間外労働をさせることが可能でした。その結果、長時間労働が常態化し、従業員の健康被害や過労死など、深刻な社会問題も表面化したのです。
2019年4月に時間外労働の上限規制が導入されてからは、多様な働き方の実現に向けて「働き方改革」が推進されています。
そして時間外労働についても罰則をともなう上限規制が設けられました。大企業では2019年4月より、中小企業においても2020年4月より規制が適用されています。
労働時間の上限「週40時間」を超えるとどうなる? 対応方法
法定労働時間である「1日8時間・週40時間」の上限を超えて従業員に労働をさせる場合、労使間で36協定を締結し、管轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
36協定を締結していても、時間外労働には上限が設けられています。労働基準法で定められた時間外労働の上限は「月45時間・年360時間」です。
臨時的に業務量が増えて時間外労働をさせなければならない場合は、特別条項付きの36協定を締結する必要があります。
| 特別条項付きの36協定で定める時間外労働の上限規制 |
|---|
| ・年720時間以内(法定休日労働を除く) ・月100時間未満(法定休日労働を含む) ・2~6か月の平均が80時間以内(法定休日労働を含む) ・月45時間を超えられるのは年6回まで |
上限を超える労働や、そもそも36協定の締結なしで週40時間を超える労働、特別条項なしで月45時間を超える時間外労働を課すのは違法です。6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
労働基準法違反で処分されると「従業員を大切にしない企業」「法律を守らないブラック企業」といった悪いイメージが広がる可能性があるため、確実に届け出をし労働時間を管理しましょう。

週40時間の労働時間の数え方・計算方法
「1日8時間・週40時間」を超える労働時間は、時間外労働として数えて把握する必要があります。
労働時間の正しい数え方と計算方法を理解することで、勤怠管理の適正化につながります。また、正確な割増賃金の支払いに欠かせず、将来のトラブルを避けられる情報となるため、2つの実例をもとに確認していきましょう。
- 例1.所定労働時間7時間、週5日、金曜に2時間残業
- 例2.所定労働時間7時間、週6日勤務
所定労働時間7時間の企業を例に、以下で詳しく解説します。
例1.所定労働時間7時間、週5日、金曜に2時間残業(日の法定労働時間のみ超える例)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 7+2=9時間 | 所定休日 | 法定休日 |
例1では、法定労働時間を超えた1時間を時間外労働として数えます。
| 週の実労働時間 | 7時間×4日+(7+2)時間=37時間 |
| 法定内残業時間 | 8時間(1日の法定労働時)−7時間=1時間 |
| 時間外労働(法定外残業時間) | 2時間−1時間=1時間 |
週の実働時間37時間は、1週間あたりの法定労働時間40時間を下回っているものの、金曜日の実働時間が8時間を超えた分の残業に対しては割増賃金が発生すると考えます。
例2.所定労働時間7時間、週6日勤務(週の法定労働時間のみ超える例)
月曜日から土曜日まで、毎日7時間労働したケースを考えてみましょう。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 法定休日 |
日曜日を法定休日としている企業の場合、土曜日に勤務したとしても法定休日労働とはみなされません。また、1日ごとの労働時間が法定労働時間を超えた日もありません。
しかし、週の実働時間が42時間となり、法定労働時間である週40時間を超過しています。
| 週の実労働時間 | 7時間×6日=42時間 |
| 法定内残業時間 | 0時間 |
| 時間外労働(法定外残業時間) | 42時間−40時間間(週の法定労働時)=2時間 |
40時間を超えた分の2時間は時間外労働とみなされ、割増賃金の支給対象となります。
1日8時間と週40時間どちらが優先される?
例1と例2で紹介したように、法定労働時間である「1日8時間・週40時間」のどちらの枠を超えても、時間外労働とみなされます。どちらか1つの枠を超えた場合も、2つの枠を両方超えた場合も時間外労働であることには変わりありません。
それでは両方の時間が超過した場合、どちらの時間外労働が採用されるのでしょうか。
ある週において「1日8時間・週40時間」の枠を両方超えた場合は、「超過した時間数が長い方」の時間外労働が優先されると覚えておきましょう。
どちらか1つの枠を超えた場合も、2つの枠を両方超えた場合も時間外労働です。
労働時間を数える際の注意点:週40時間の起算日
週40時間を超える法定外残業時間を数える際は、週あたりの労働時間を計算するための起算日が必要です。就業規則で起算日が定められていない場合は、日曜日が起算日として扱われます。
週の労働時間の数え方【勤務形態別】
労働基準法で定められている「1日8時間・週40時間」の法定労働時間は、基本的にどの勤務形態であっても適用されるルールです。
しかし勤務形態によって、管理上の扱いが異なる場合もあるため、「どのように数えればよいのか」「割増の発生条件は何か」など、疑問に思うこともあるかもしれません。また一部例外的な扱いをする業種もあります。
そこで週の労働時間の数え方を勤務形態別に、以下の7つのポイントに絞って解説していきます。
- 変形労働時間制の労働時間の数え方
- 裁量労働制におけるみなし労働時間の考え方
- フレックスタイム制の清算期間の計算方法
- 特例対象事業場の特例
- 繁閑差が激しい幅広い分野での特例
- シフト制の注意点
- ダブルワークの場合の注意点
勤務形態別の労働時間の考え方を理解し、ポイントをおさえることで、勤怠管理の効率化につながります。
変形労働時間制
変形労働時間制とは、繁忙期の労働時間を長くする代わりに閑散期の労働時間を短くするなど、労働時間を月や年など一定の単位で調整する働き方です。
変形労働時間制を導入していても、法定労働時間の上限を超えた場合には時間外労働として割増賃金が発生します。
変形労働時間制の場合は、月や年単位で労働時間の上限を考えなければならないものの、「週40時間まで」という基本となる考えに変わりはありません。
以下の計算方法で、対象期間における上限を把握できます。
| 労働時間の上限=40時間×(対象期間の暦日数÷7日) |
平均した際に1週間あたりの労働時間が40時間以内に収まれば、問題ないと覚えておきましょう。
裁量労働制
裁量労働制とは、労働者の裁量によって労働時間を定められる働き方です。
実働時間に関係なく、みなし労働時間分働いたとみなされるため、原則として日ごとや週ごとの時間外労働は発生しません。
ただし、事前に設定したみなし労働時間が法定労働時間を超えている場合は、超過分が時間外労働として計上されます。
さらに法定休日や深夜時間帯の労働が発生した場合も、割増賃金を支払う必要があると覚えておきましょう。
フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、労働者が始業・終業時間を定められる働き方です。フレックスタイム制では、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた分が時間外労働となります。
フレックスタイム制の清算期間における労働時間の上限は、以下の計算式で求められます。
| 労働時間の上限=40時間×(清算期間の暦日数÷7日) |
清算期間が1か月を超える場合は、月ごとの週平均が50時間を超えている部分も時間外労働とみなされるため、注意しましょう。
参照:『フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き』厚生労働省
特例対象事業場|週44時間まで可能
特例対象事業場とは、以下の業種に該当し、常時10人未満の従業員を使用する事業場のことです。
| 商業 | 卸売業や小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業 |
| 映画・演劇業 | 映画の映写や演劇、その他興業の事業 |
| 保健衛生業 | 病院や診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業 |
| 接客娯楽業 | 旅館や飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業 |
以上の条件を満たす事業場は、法定労働時間を週40時間から週44時間に変更できます。
従業員数には、パートやアルバイトも含めます。店舗や支店など事業場ごとに従業員を数えるため、同じ企業内で特例対象事業場の店舗と、そうでない店舗が混在するケースもあるでしょう。
繁閑の差が激しい一定の業種
繁閑の差が激しい一定の業種とは、以下の業種に該当する、常時使用する従業員の数が30人未満の事業場を指します。
- 小売業
- 旅館
- 料理店
- 飲食店
以上の業種において労使協定を締結すれば、労働基準法と労働基準法施行規則の定めにより法定労働時間を1日10時間まで延長できます。このような労働時間制を「1週間単位の非定型的変形労働時間制」と呼びます。
使用者は、原則として1週間単位で、かつ法定労働時間を延長する1週間前までに、対象の従業員に対して書面で労働時間の変更を通知しなければなりません。
ただし、やむを得ない事情がある場合は、前日までに書面で通知すれば、労働時間の変更が認められます。
シフト制(パート・アルバイト)
シフト制を採用するパートやアルバイトであっても労働時間は、法定労働時間である「1日8時間・週40時間」の上限にしたがいます。
労働時間や時間外労働の上限は、正社員だけでなく、非正規雇用の従業員にも適用されると覚えておきましょう。
非正規雇用においても上限を超えて労働を課す場合は、36協定の締結が必要です。
ダブルワーク(副業)
ダブルワーク(副業)でも、1日や1週間あたりの労働時間は通算されます。
ダブルワークによって法定労働時間を超過した場合の割増賃金の支払い義務は、原則としてあとから労働契約を締結した事業所が負わなければなりません。
| (先に労働契約を締結)企業A | 所定労働時間6時間 |
| (あとに労働契約を締結)企業B | 所定労働時間3時間 |
| 合計労働時間(日) | 6+3=9時間(※法定労働時間を1時間超過) |
以上の場合、企業Bに時間外労働手当(割増賃金)の支払い義務が発生します。
週40時間の労働時間を数える際の注意点
最後に、週40時間の労働時間を数える際の注意点を、特殊なケース別に紹介していきます。
労働基準法で定められている「1日8時間・週40時間」の法定労働時間は、企業が勤怠管理を行う際の基本的な指標です。
ただし週の労働時間を数える際、月をまたぐ場合や振替休日があった週など、特殊な状況では、どのように考えたらいいか悩みますよね。
以下の3つのポイントを解説するため、どんな状況でも週40時間の労働時間を数えられるようにしましょう。
- 月をまたぐ場合の労働時間の数え方
- 週をまたぐ場合の取り扱いと注意点
- 祝日がある週の対応方法
- 振替休日、代休を取得した場合の対応方法
以上を整理できると、勤怠管理において迷いがなくなり、適切な対応が可能となります。
月をまたぐ場合
月をまたぐ場合でも、起算日を基準に週単位で労働時間数えることが基本です。
労働時間の計算では、月をまたぐことは考慮しなくて問題ありません。起算日から数えて1週間分の労働時間で取り扱います。
週40時間の法定労働時間を超過した場合は、翌月の給与とあわせて割増賃金を支給します。
週をまたぐ場合
週をまたぐ場合も、就業規則で定められた週の起算日を基準に数え始めます。
たとえば、起算日を日曜日とする企業で、土曜日から日曜日にかけて日をまたいで労働させた場合は、日曜日の0時で週の労働時間を締めるのです。
この企業が日曜日を法定休日としている場合は、法定休日労働となり、日をまたいだ時間分の割増賃金が発生します。
祝日がある週の場合
祝日に働かせた分の労働時間も、基本的に週の労働時間の計算に含めます。就業規則で祝日を所定休日と定める企業では、法定休日労働にならないため、法定労働時間を超えていなければ割増賃金は発生しません。
振替休日や代休をとった場合
振替休日をとらせた場合は、あらかじめ法定休日と労働日を入れ替えているため、法定休日労働への割増賃金は発生しません。
ただし休日と労働日を入れ替えたことで、週の労働時間が40時間を超える場合は、時間外労働の割増賃金が発生するため注意が必要です。
一方で代休は、休日労働を行ったあと、代わりに別の労働日を休日とする対応です。実際に法定休日に働いた休日労働に対して割増賃金を支払う必要があります。ただし、週の法定労働時間の計算へ影響はありません。
週の労働時間の管理徹底を(まとめ)
1日の労働時間に比べて、週単位の労働時間は管理が複雑になりやすいものです。
とくに変形労働時間制やフレックスタイム制など、固定ではない勤務形態を採用している場合は、法定労働時間の超過が見過ごされる傾向にあります。
手集計や手計算による勤怠管理をしている企業は、管理の煩雑さを解消するのは難しいかもしれません。
労働時間の集計や可視化に課題があるなら、自社に適した勤怠管理システムの活用がおすすめです。管理の一部を自動化することで、法令遵守を徹底しましょう。
勤怠管理システムのタイプやできることを確認したい場合は以下の記事もご確認ください。
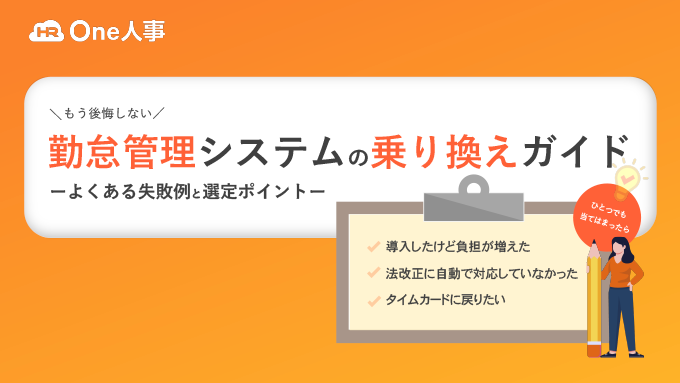
労働時間の管理をラクにする|One人事[勤怠]
週の労働時間を適切に管理するには、勤怠管理の効率化が不可欠です。
勤怠管理システムOne人事[勤怠]は、労働時間の超過アラートを出すなど、法律に沿った労働時間の管理を助けるクラウドツールです。
One人事[勤怠]の初期費用や操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門のスタッフが貴社の課題をていねいにヒアリングしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、勤怠管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。勤怠管理をラクにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
